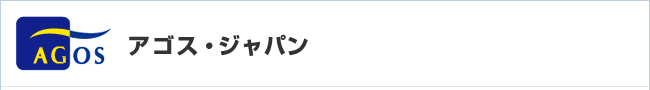◇ 2023年6月【オーストラリア・Griffith University 野口明純】祭りで落語披露
この記事を折りたたむ
|
◇ 2023年6月【オーストラリア・Griffith University 野口明純】祭りで落語披露
とっておきの思い出を語りたいと思います。Matsuri Brisbaneでの落語披露です。僕は駒澤大学で落語くらぶ(いわゆる落研)に所属しており、オーストラリアに行く事が決まった時から、現地で落語を披露したいと思っていました。グリフィス大学でJapan Club に所属する前から、クラブのイベントで披露できるか打診してきましたが、あまり前向きな返事はもらえていませんでした。そうこうしているうちに、一学期が過ぎ、二学期に入って新しい友達ができました。神田凌摩という男です。彼がある日「Matsuri Brisbaneっていうお祭りがあるらしいんやけど、ボランティア募集しているんやって。一緒に行かへん?」という内容のLINEをくれました。Matsuri Brisbaneというのは、年に一度、クイーンズランド州・ブリスベンで開催される、日本人による日本文化発信イベントのような、割と規模感のあるお祭りです。最初は、お誘いの通り、ボランティアとして参加するつもりでした。しかし、「もしや?」と思い、開催間近な中、ダメもとで主催者に落語パフォーマーとして参加出来ないか打診したところ、意外にもOKを頂き、手続きや用意する道具など、いろいろな調整が始まりました。
英語で、動物園(The ZOO)という落語を披露するのに、日本から持ってきた英語落語の本や、CDを聞いたり、自分で録音・録画して、繰り返し聞いたり(自分自身の音声・映像を見返すのは、消え入りたい程恥ずかしいです)と、準備を進めていました。
事前説明会に参加した際、ブリスベン在住の新しい友人が出来ました。お若い夫婦で、夫はサイバーセキュリティの仕事をされているそうです。ちなみに、お祭りや説明会が行われたブリスベンは、僕が住んでいるゴールドコーストから、電車で2時間くらいかかるところにあります。
本番では、雨が降っていました。雨の影響で、僕が予定していた時間より前の組が、土壇場でキャンセルとなり、代わりに僕が、当初予定していなかった、日本語の落語を披露しました(笑)。2本立て続けでした。その後、予定時間以外に、もともとかけるつもりだった英語落語を披露しました。現地に駆けつけてくれたJapan Clubの友人によれば、英語落語は大ウケだったそうです。オーストラリアで出来た沢山の人との繋がりを感じられたという意味で、とっておきの思い出になりました。
今回の落語披露では、会場関係者の方々に、直前のスケジュール調整、本番での柔軟な予定変更、座布団の自作と貸し出しなど、多くのサポートを頂きました。また、特にJapan Clubの多くの方が、僕の呼びかけに応じて、遠路はるばる会場に来てくれました。さらに、悪天候の中私の落語を聞いてくださった皆々様に、ここで、改めて感謝申し上げます。
写真はもちろん、僕の英語落語の一場面です。

|
この記事の先頭へ戻る
◇ 2023年4月【オーストラリア・Griffith University 野口明純】豪の食べ物のはなし
この記事を折りたたむ
|
◇ 2023年4月【オーストラリア・Griffith University 野口明純】豪の食べ物のはなし
箸休めに、オーストラリアの食べ物のはなしでもいかがですか?
クイズから行きましょう。次の3つのうち、税金がかからない食品はどれでしょうA.オージービーフB.アンザックビスケットC.コーヒー?正解は…とその前に、それぞれ一言コメントを。オージービーフは言わずと知れたオーストラリアの牛肉ですね。アンザックビスケットの「アンザック」はANZAC(Australian and New Zealand Army Corps:オーストラリア・ニュージーランド軍団)から来ていて、「ビスケット」の方が「クッキー」より格上だそうです。ココナッツの香りが美味さを引き立てます。コーヒーは毎朝食後に飲んでいました。シェアハウス(住人紹介 vol.1及びvol.2参照)ではインスタントコーヒーを色々試しつつ、他の人の家でその家のやり方で抽出されたコーヒーを飲んだりをしていました。お待たせしました、正解はA.とC.です。ただし、A.は未加工のものに限り、おそらく飲食店では課税されるでしょう。
オーストラリアでお寿司を食べるのは至難の業です。いや、あるんですよ?回転寿司も。でも、日本で食べられるような「寿司」、ましてや日本人が経営しているお寿司屋さんは、そうそう見つからないでしょう。僕がWoolworthsで買ったエビロール寿司は、それはそれは寂しいものでした。エビの天ぷらの巻き寿司なのですが、中身のエビが、鉛筆弱の細さだったのです。天かすも周りについていて、極めつけがメキシカンソースでの味付け。オーストラリアに入るなら、天然無添加の大トロや真イカ、甘えびなどは諦めましょう。情熱のある方は、タスマニアへ。タスマニアでは、食べられるお魚が多いそうです。
お魚からお肉に話を移しましょう。あちらでは、お肉はキロ単位で売っています。鶏モモ肉1.2kgがAUS$7.50であったり、T-ボーンステーキが1.5kgでAUS$20.00であったりなどです。今日、日本のスーパーで買った大豆ミートは100gで105円だったので、1kgでAUD$11.75といったところでしょうか。
野菜のお話も。オーストラリアのお野菜たちは、とにかくゴツいです。「俺様を食べるのか、いい度胸してるぜぃ」とでも言いたげに、スーパーに並んでいます。いろんな野菜たちを食べた中で、やはり、ハロウィンの季節に買ったカボチャを、電子レンジでふわとろにして食べたときの感動といったらありません。種も天日干しにして、丸かじりしました(真似をされる方は、自己責任でお願い致します)。
最後にAgosブログをご覧の皆様にとっておきの炭水化物情報を。” Quick Oats” は驚きのコスパです。私が何を言っているのか確かめたい方・再確認されたい方は、ぜひオーストラリアでお近くのWoolworthsへ。写真は、「カンガルー肉のトマト煮」です。

|
この記事の先頭へ戻る
◇ 2023年4月【オーストラリア・Griffith University 野口明純】Japan Club(ジャパンクラブ)
この記事を折りたたむ
|
◇ 2023年4月【オーストラリア・Griffith University 野口明純】Japan Club(ジャパンクラブ)
前回の記事で、さらっと「Japan Club(ジャパンクラブ)」と書きましたが、まだ紹介をしていませんでした。今回詳しく話していきたいと思います。
Japan Clubは、日本人と、日本に興味のある人が集まる部活です。グリフィス大学公認です。一学期と二学期で幹事が一新し、イベントも大きく変わりました。一学期には、新入生歓迎のバーベキューがあった後、基本的な活動として週二回の勉強会がありました。具体的には、火曜日の15:00~17:00にG31という建物で、木曜日の17:00~19:00にG30という建物で、日本語を教えたり英語の課題を助けてもらったりを、お互いにしていました。オーストラリアのスラングをハングマンで学んだ時や、幹事の一人が沢山の和食やセールだったクリスピークリームドーナツを差し入れてくれた時などは、特に印象に残っています。欧米の高等教育を受けるのは初めてだったので、一学期に課題の進め方や課題の要旨をつかむのに手助けを受けられたのは、PASS(「履修登録の話」記事参照)とはまた別の形で、非常に大きい助けになりました。英語力向上にも役立ちました。というのも、授業中に他の生徒の発言は聞けるものの、カジュアルな会話を、しかもちょくちょく日本語で意味を確認しながら聞ける機会は少ないからです。
一学期の終わりには、ゲーム大会がありました。映画館もびっくりの大きなシアターを貸し切って、大画面で「スマブラ」をやったり、別のモニターでマリオカートをやったりしました。僕はゲームをやるというより、友達と喋っていました。ゲーム大会中に、日本の落研仲間ともGoogle meet中継をしたのは、あたたかな想い出です。
二学期には、新幹事長が週2回教場に居続けることが困難であるスケジュールだったため、勉強会はほとんど行われませんでした。代わりに、Movie Nightという企画が、毎週金曜(花金!)に行われていました。英語・日本語の映画を、ネットフリックスにて、双方の字幕で見るという趣旨のものです。部員の持ち寄ったお菓子と、幹事長の買ってきたコーラ・スプライト・ポテチ・チョコなどを片手に、天気の子やシュレックなどを見ていました。僕もオススメ映画リストを新幹事長にLINEしました。が、一個も採用されなかった気がします笑。逆に自分では見ない映画が多く楽しめました。
写真は、一学期終わりのゲーム大会直前にて、ゲーム画面のプロジェクションの実験成功に湧く、当時の幹事長と「技術屋さん」です。

|
この記事の先頭へ戻る
◇ 2023年3月【オーストラリア・Griffith University 野口明純】授業の感想:アドバイス編
この記事を折りたたむ
|
◇ 2023年3月【オーストラリア・Griffith University 野口明純】授業の感想:アドバイス編
…さて、前回まで、1学期と2学期の授業について書きました。ここでは、2学期間グリフィス大学の授業を受けての、全体の感想やアドバイスを話したいと思います。
まず、オンラインか対面かです。対面を勧めます。生徒はその場で指差しなども使って質問できるし、先生も生徒の反応が分かり、より良い授業ができるそうです。
次に、履修に関するアドバイスとして、以下のステップを踏むと、僕は楽にコマ割りができました。まず5つのステップを書くので、後で各ステップの詳しい説明を読んでください。1.とる授業を決める→2.とる授業のウェブサイトを見る→3.Excelで、空いているコマ(クラス)を入力→4.固定された予定を青で塗りつぶす→5.とる授業を黄色で塗りつぶす。1.に関しては、「履修登録の話」記事の、一段落目が参考になると思います。2.では、授業一覧サイトから授業名をクリックすれば、各授業のウェブサイトに飛べます。選択欄から、該当する学期とキャンパスを正確に選び(←ここは非常に重要!間違ったキャンパスを選んだり、対面希望なのにオンラインを選んだりすると、検索時間が無駄になります!)ます。すると、サイトの下の方に、「いつのどこの授業が空いているか」が、表になってまとまっているので、とれる状態(定員一杯の状態では無い)クラスの曜日と時間を、自作のExcelに入力します。4.では、毎週必ず行っている事を、授業を取れない時間として塗りつぶしておきます。僕の場合は、日本のゼミ・部活のオンライン参加が、これにあたります。3.の後で4.を行うかどうかは、予定の優先度で変えて良いかもしれません。5.で、複数授業がかぶっている場合は、どちらかを選ぶか、どちらも別の曜日・時間にするなどして調整し、履修スケジュールを完成させます。
続けて、ノートのとり方です。Wordでとるか、紙に書くか。最初は両方試しましたが、PASSの先輩が「紙で書いた方が頭に残る」と言っていたので、はじめはスーパーマーケットで買ったノートに、二学期の途中からはコピー用紙に書くようになりました。罫線が無い上に、好きなページを持ってきての比較をできるコピー用紙は、結局便利でした。授業毎に、買ったノートの見開き毎に挟んでいきました。コピー用紙は、後で比較が楽になる様に、表面のみ使うようになりました。これは、いくつかの授業の内容をまとめる課題が出た時に、大いに助けになりました。
最後に、作文課題に取り組むときの(オリジナル?)アドバイスとして、「Excelを活用」というのがあります。文字数を記録し、一日平均何文字書けば終わるか、計算させていると、やる気が維持できました。
写真は、ジャパンクラブで集まった日本料理店です(筆者撮影)。ジャパンクラブでは課題について助けてもらった事が多くあります。クラブに関しては、今後詳しく書きたいと思います。

|
この記事の先頭へ戻る
◇ 2023年3月【オーストラリア・Griffith University 野口明純】授業の感想:2学期編その3
この記事を折りたたむ
|
◇ 2023年3月【オーストラリア・Griffith University 野口明純】授業の感想:2学期編その3
前回の続きです。2315AFE Econometric Analysisは、計量経済学の授業です。計量経済学とは?経済学という学問は、次の3つの柱で出来ているそうです。ミクロ・マクロ・計量経済学。この3番目にあたる計量経済学が、統計学とミクロ・マクロのテーマを混ぜたような事を学ぶものです。具体的に、「パンを売るには、看板を出した方がいいのか?CMをうった方がいいのか?」や、「GDPの伸びには、人口が関係しているのか?補助金の額の方が関係しているのか?」などを、データを元に調べている、と説明すると分かりやすいでしょうか。
「履修登録の話」記事をお読みになった方はお気づきかも知れませんが、この授業は授業番号が「2」から始まるわけで、2年生向けの授業です。また、今年度から、1年生向けの「統計の基礎」授業とを合体させて、いわば急ぎ足で2年分の計量を学ぶものなのだそうです。僕は日本にいる時に、統計の基礎を学んでおり、特に最初はついていきやすかったですが、途中から未知の領域に入り、とにかく手を動かしてついていきました。
この授業には、出会いの面でおもしろい話があります。一学期のある日、僕がいつも通り大学を歩いていたら、ある男性にコピー機のある場所を聞かれ、図書館に案内しました。二学期になり、僕が受けた計量経済学の担当の先生から「最初の授業に来られない。代役を用意する。」と全体に連絡がありました。その代理の先生が、一学期に案内した男性だったのです!その男性は、一緒に歩いていた時は、穏やかな印象だったのですが、いざ授業になると、これがなかなか早口でした。それに、質問に正解しても他の生徒に「…とAki(僕の事)は言っているが、君はどう思う」と正解かどうかは言わないという、なかなか手ごわい「先生」でした笑。ただ、別れ際に、「今度日本に行ってみたい」と言って下さって嬉しかったです。
この授業の課題は2つで、1つ目は、提出物系中間テストのようなもので、決められた日数の中で、与えられたデータを決まった項目に応えるかたちで、専用アプリで分析するものでした。2つ目は期末試験でした。問題の書かれたWordファイルを学校のサイトでダウンロードしそこに答えを書き込みました。データをアプリにかけるというより、分析結果が渡され、それをどう解釈するかを記述するものでした。期末テストは満点でした!
授業の担当の先生も僕と僕の国に興味をもって下さったようで、最後の授業終わりに「いつか日本に行こうと思う」と言ってくださいました。
写真は、最後の授業の授業ノートです。次回は、2学期間、グリフィス大学の授業を受けての、全体の感想やアドバイスを話したいと思います。

|
この記事の先頭へ戻る
◇ 2023年2月【オーストラリア・Griffith University 野口明純】授業の感想:2学期編その2
この記事を折りたたむ
|
◇ 2023年2月【オーストラリア・Griffith University 野口明純】授業の感想:2学期編その2
前回の続きです。1006GBS Why Money Mattersは、まず需要・供給曲線やGDPから始まり、経済の基礎を詳しく・丁寧に学びました。それらに関する小テストが、1番目の課題です。次に、財務諸表の各項目の計算方法や分析の方法、各項目が表している意味を学びました。実際の企業の財務諸表を分析するのが、2番目の課題でした。最後に、最近日本でも注目されている金融リテラシーについて学びました。3番目の課題は、それらの授業を踏まえて、割り当てられたオーストラリアの家庭の収支を分析し、彼らがお金を貯めて、守るには、どうすれば良いのか、提案をするものでした。この課題では、それに加えて、割り当てられたクイーンズランド州内の地域の中で、お金の面で弱い立場にいる人々に対する、財政的に負担の少ない救済策も提案するようになっていました。以上の3つが、1006の大きなテーマ、また、3つの課題でした。
最後の課題は、プレゼン動画を提出するもので、僕のパソコンの容量が心配でした。動画の形式で課題を提出するのも初めてだったので、上手くいくか、特に最初は不安でした。この課題にはコツがあって、PowerPointで撮影をすればスライド毎に録画できるので、一発通しで成功しなくても、大丈夫です。また、PowerPointには、スライド編集画面の下部に「ノートを入力」のボックスがありますよね?そこに、原稿(の一部)を入れておけば、いわゆるカンペが出来ます。録画画面の上部に自動であらわれます。ただし、録画中にスクロールバーを動かすと、いきなり「ピョン」と最上部に飛んだりするので、ご用心を。
学期間を通して、1006の先生が一番授業が上手だったと思います。先生の話がリアルで面白いのはもちろんの事、最初の授業で自己紹介をする時に「1つの嘘と2つの本当」ゲームを取り入れるなど、緊張を上手く和らげていました。また、生徒の集中が途切れないように、生徒の発言の機会を本当に多く作っていました。それもあって、授業中に生徒同士が喋ったり気になるような事があることは、ついぞ有りませんでした。とにかく、自分も含めて生徒が「参加している」と思えるような授業だったので、いい意味で、疲れますが実りの多い授業を過ごしていました。前回の記事に書いた「教室替え」を、自分以外の生徒が行い、途中から僕たちのクラスに参加するようになったという生徒もいたほどです。
最後の授業では、生徒でお菓子を持ち寄り、授業中に食べつつ、ざっくばらんに授業内容や課題について、ディスカッションしました。写真は、その授業が終わった後の、個別相談のようすです。
次回は、計量経済学の、2315AFE Econometric Analysisについて書くつもりです。

|
この記事の先頭へ戻る
◇ 2022年12月【オーストラリア・Griffith University 野口明純】授業の感想:2学期編その1
この記事を折りたたむ
|
◇ 2022年12月【オーストラリア・Griffith University 野口明純】授業の感想:2学期編その1
前々回の履修登録、前回の1学期に続き、ここでは2学期について書きたいと思います。2学期に登録した授業は、最後まで履修した3つ、1005GBS Engaging Australia and the Asia-Pacificと1006GBS Why Money Matters、それから、2315AFE Econometric Analysisに加えて、途中で放棄した2つ、1009GBS Grand Challenges for Businessと、2154IBA International Business Logisticsの、合計5つです。
1学期の時とは異なり、途中で放棄した2つの科目は、最初から授業を受けていませんでした。あくまで、他3つの授業があまりに難しかったり、興味からずれていた時の保険のためにとっておいていました。幸い、3つの授業が分かりやすく、非常に興味分かかったので、最後までついていけました。
1005GBS Engaging Australia and the Asia-Pacificでは、アジア太平洋の地理・歴史・政治・経済に加え、人種問題やコロナ問題が取り上げられました。特に、オーストラリアには、日本ではアボリジナル(やアボリジニ)と呼ばれる、” First Peoples Aboriginal and Torres Strait Islander”の存在があり、その学習は興味深かったです。なお、僕とは、取り組んでいる学問分野が大きく異なる、無機化学専攻の友達も、先住民に関する授業を受けたり、作文を書いたりしたそうです。オーストラリアに来て、「外国人(自分の事)に対して寛容だな」と感じていたのですが、先住民に対する理解を、教育で重要視しているという要素も、影響しているのかなと思いました。
提出物は3つで、全て作文課題でした(骨を折りました笑)。1つ目は、先住民の理解と共生について、2つのテーマの内1つを選んで書きました。僕は、先住民アートについて、その著作権の保護について書きました。2つ目は、「北or東南アジア」エリアと「太平洋」エリアの、指定されたリストから国を1つずつ選び、2つのSDGs目標に対する取り組み度合いと課題を比較しました。僕は日本とトンガを選び、SDGs5とSDGs14について比較を行いました。3つ目は、オーストラリアの産業をリストから1つ選び、別のリストから国を一つ選んで、選んだ国で、選んだ産業をどう展開していくのか、業界への提言書を書く、というものでした。僕は、日本で牛肉産業をどう発展させていくか、論文に基づいた、オージービーフのアピール案を書きました。
このコースに関しては、2学期間通して唯一、先生を途中で変えた授業です。授業は週に一回なのですが、同じ週に、別々の先生が、それぞれの曜日・時間・教室で、別々に授業を行っています。PASS( PASSに関しては、「履修登録の話」記事を参照してください)の1つに、2番目の課題対策の会があったのですが、「○○先生の授業はめちゃくちゃ助かる」と聞いたので、勇気を出して変更しました。
…と長くなってきたので、2学期の残り2つの授業は、次回以降詳しく述べたいと思います。写真は、近くのショッピングモールのモスバーガーです。今回話題にあがった、オージービーフを使っています。親友のインドネシア人と食べました。

|
この記事の先頭へ戻る
◇ 2022年11月【オーストラリア・Griffith University 野口明純】授業の感想:1学期編
この記事を折りたたむ
|
◇ 2022年11月【オーストラリア・Griffith University 野口明純】授業の感想:1学期編
1学期は、最初に5つの授業を登録していました。なお、履修登録に関しては、前回のブログで詳しく書いています。5つの授業は、2128IBA The Management of Business Process 、1307AFE Degital Economy and Analysis 、1008GBS Business Decision-Making 、3307AFE International Economics 、1043SCG Introduction to Environmental Sustainability です。このうち、最後の2つ(3307と1043)は、途中できりました。
まず、きった授業から説明したいと思います。前回のブログでも書きましたが、3307は、学部を卒業するレベルの人が受ける授業で、シンプルに、先生の言っていることがほとんど分かりませんでした。予習をいくら頑張っても、ついていける兆しが無く、3週目あたりで、履修を諦めた感じです。逆に、図書館員に授業のレベルのアドバイスを受けておいて、良かったです。1043は、先生が真面目すぎる印象で性に合いませんでした。他の授業がとても魅力的であったのもあり、2週目で放棄しました。ちなみに、履修放棄が遅いと、GPAに傷がついたり、授業料を返してもらえないタイミングがあるので、学校のカレンダーはチェックしておいて良かったです。
ここからは、最後まで履修した科目の解説・感想です。
2128では、ビジネスで行う工程(カフェでカプチーノを作ってお客様に提供など)を、図表に表し、改善点を理論的にも探る…という内容をやりました。最初こそ全体像をつかむのに苦労しましたが、一度図解のコツをつかむと、色んな工程に適応したくなり、楽しめました。2つの提出課題の内1つでは、僕がバイトをしていた塾のプロセスマップを作成し、改善点をあげました。もう1つでは、授業で学んだ理論を、オーストラリアに実在する企業にあてはめ、質問に答えました。SDGsに関する提言も、この課題で行いました。
1307では、経済学の基礎を学びつつ、それをデジタル社会にあてはめる、というような事を学びました。提出物は3つです。1つ目では、僕のマイブームのライブが、デジタル化でどのように市場に変化をもたらしたのかを書きました。2つ目では、課題のデータ分析と、コロナに関連する自由分析を行いました。3つ目では、統計学における仮説検定という、基本的な技術に関する問題を解きました。先生の教え方が分かりやすく、印象に残っています。※今、提出物を見返したら、堂々と日経の日本語記事を引用していました。日本語が読めない先生に対してはNGだったでしょうね。冷や汗ものです(-.-;
1008では、ビジネスにおける意思決定について、インクルージョン・脳科学・データサイエンス・グループ/組織の理論・コミュニケーション能力/理論・計画立て・リスク管理・データ分析…など、実に様々な観点から学び、議論しました。1つ目の提出物は小テスト。2つ目は、問題解答形式の、オーストラリア企業のデータ分析。3つ目は、オーストラリアのバイク企業がアメリカに進出するにあたって、どのような策をとるべきか、論文やデータに基づいて提言を行うというものでした。
全体を通して、なかなかボリューミーな課題を提出するだけあって、日本の大学の何倍も、授業の内容が身になっていると感じます。次回は、2学期編です。
写真は、2128の2つ目の課題に使った、自作のfishbone diagramです。1956年に石川馨が考案したそうです。

|
この記事の先頭へ戻る
◇ 2022年11月【アメリカ・University of Florida 金子舜汰】こんにちは!
◇ 2022年10月【オーストラリア・Griffith University 野口明純】履修登録の話
この記事を折りたたむ
|
◇ 2022年10月【オーストラリア・Griffith University 野口明純】履修登録の話
今回は、授業をとった時の話をします。履修に関しては、グリフィス大学が運営する、生徒専用サイトで、全て済ませました。僕は学部こそ、グローバル・メディア・スタディーズという、学際的な学部にいますが、ゼミは経済学中心のものに所属しています。よって、経済学系の授業をとろうとしていました。授業検索サイトで、(プログラムではなく、)コースでフィルターをかけ、経済学系、ビジネス系、環境系、物流系など、とにかく関心のある検索ワードを入力しました。そして、検索結果を、下からくまなくチェックし、自分にあうと思った授業を片っ端から履修の申請をしました。この履修の申請で承認された授業の中からのみ、実際に履修する科目を選べません。なので、この申請は多めにしておいた方が、選択肢が多くて良いと言われていました。
いざグリフィス大学に到着し、図書館員に予習用の本の探し方を聞いた所、「科目番号が2より大きい番号から始まっているコースは、難易度の観点でとらない方がいいと思うよ」と言われました。そう言われるまで知らなかった事として、科目番号の最初の数字(例えば、Business Decision-Making なら、1008GBSなど)は、その授業の対象となる、大学生の学年の目安なのだそうです!オーストラリアの学部生は3年間で卒業するようなので、3007MKTのMarketing for Behavior Changeなどは、相当専門的な知識を、前提としているという事なのでしょう。実際、僕が唯一お試しで受けた3から始まるコースである、3307AFE International Economicsは、経済学の用語やその内容・仕組みをある程度知っている前提で、理論を実際のデータと照し合せたりしていました。よって、ゼミに入ったタイミング的に、経済の勉強を2年もしていない自分は、議論にほぼついていけませんでした。対照的に、1から始まるコースは、1年生向けだけあって、予習用のサイトの内容が充実しています。また、世界中から生徒が集まっていることが多いので、国際的な環境に配慮(先生の英語が聞き取りやすいなど)を感じました。さらに、1年生向けコースには、多くにPASS(Peer-Assisted Study Sessions)という、同じコースを優秀な成績で終えた先輩(学生と近い年齢)が、課題の進め方や授業の分かりやすい復習をするという、補助プログラムがついており、助かりました。
添付した写真は、今回話題にもあがった、図書館です。
次回からは、1学期と2学期を終えての、授業の感想を書きたいと思っています。
※ 8月のクイズの答えは…上からアンドレス、よしき、アンドリュー、僕でした!自然派のAndressは香辛料をたくさん持っていますね。入居したてのよしき君は、ほぼインスタント麺しか持っていません。アンドリューの棚の奥には、大きいプロテインの容器があります。僕は日本の調味料が前面に見えます。

|
この記事の先頭へ戻る
◇ 2022年9月【カナダ・Brescia University College 山﨑愛巳】初めまして!
この記事を折りたたむ
|
◇ 2022年9月【カナダ・Brescia University College 山﨑愛巳】初めまして!
こんにちは、カナダのBrescia University Collegeに交換留学します、お茶の水女子大学 文教育学部3年の山﨑愛巳と申します。(出国は、8月末でしたが、到着翌日から毎日イベント続きでバタバタしており、書き直しをしていたら遅くなってしまいました(^^;)どうぞ宜しくお願い致します。
【今回のラインナップ】
1. 留学理由・留学先・出願過程
2. TOEFL対策
3. 留学準備
4. 今(機内で)の心境
因みに私のイチオシは、他の方より特殊な経験をしていたり、教訓があった③です!
1. 留学理由・留学先・出願過程
私は、お茶大の国際系コースを専攻しており、その過程で特に『多文化共生』に興味関心を持ち始め、実際に多文化主義国家であるカナダに身を置きながら学び、視野を広げて卒論研究もしたいと思ったことが留学を希望するきっかけでした。
そして、居心地の良い大好きなお茶大同様、女子大かつ少人数制リベラルアーツのBrescia大学を選択しました。
そのBrescia大学は、オンタリオ州ロンドン市内にあり、ダウンタウンまではバスで20分程の便利な場所に位置しています。近隣の協定校Western大学を本キャンパスと呼び、授業を取ったり、イベント参加や施設利用が可能なのも魅力の一つです。
私の大学では年に一度しか交換留学の選抜機会がありません。
具体的には、
10月:書類提出
12月:面接
12月冬休み直前:派遣先決定
4月初旬:派遣先に書類提出(TOEFLや残高証明書等)
という流れでした。
面接では、留学先でどのようなことを学び、それらをお茶大のみならず、日本にどのように還元するのか、また、派遣生としての責任もしっかり示す事で、面接官の心を掴めたのではないかと実感しました。
2. TOEFL対策
本来は選考前に条件をクリアしている事が望ましいですが、コロナ禍で留学の決断が遅かった私は、面接後の12月にTOEFLを初受験し、80ポイントが条件のところを60しか取れず、焦って冬休み中に自己対策はしたものの、翌月の再受験では3点しか伸びていなかった事に愕然としてしまいました。
もう時間も無い、効率的にスコアを獲得するしかない!と思い立ち、AGOS入会を即決しました。
アドバイスにより、すぐに効果が出やすいReadingとWritingに絞って受講しましたが、どちらの授業でも、それまで知らなかった解法テクニックやポイントを教えていただけました。
そして、入会前のReading14、Writing15から、最終的にはR24、W22まで伸ばすことが出来ました。
スコア80レベルの場合、短期間でアップするには戦略が重要だと実感、また、Practiceテスト10回分を購入した対策も大変役立ちました。
SpeakingはDMMで毎日25分間のオンライン授業を継続しました。そんなこんな、お陰様でスコア締切日にはギリギリ間に合いましたが、精神的にも追い詰められ、正直、病みそうでした。
これを読んで下さっている皆さんには、時間も気持ちも余裕を持って取り組まれることを強くお勧めしたいです。
3. 留学準備
ここでは、【ビザが間に合わない(T-T)】【コロナになってしまった(;-;)】【荷造り】の3本立てでお話します。
【ビザが間に合わない(T-T)】
8月末の出国予定でしたが、ビザの申請に必要な入学許可証が届いたのは、7月上旬でした。その後、大学の課題で手一杯になってしまい、7/20頃までビザ申請書類に手を付けていませんでした。
ふと、通学中に「そういえばビザ。。。」と思い調べてみると、公式サイトでは発効までに12週間かかると記載されていました。その時はかなり焦りましたが、結果として7/18に申請をし、8/2にバイオメトリクス(指紋認証)を浜松町に取りに行き、8/5にビザを取得することが出来ました。今回は何とかなりましたが、最悪の場合、Estaという6カ月未満の滞在者向けビザ(3~5日で取得可能)を一時的に取り、長期ビザが下りたら再入国しようとまで考えていました。実際、公式発表しているよりもビザは早く下りると思いますが、私のようにならないよう、交換留学の皆さんは、期末試験等で忙しい時期かと思いますが、早めの申請をお勧めします。
【コロナになってしまった(;-;)】
コロナ感染は誰にでもあり得ますが、私の場合は疾患時期が悪く、出国の3日前まで自宅療養しなければなりませんでした。
幸い、症状は軽く2~3日で良くなりましたが、予定を全てキャンセルし、また買い物にも行くことが出来なかったのは、かなりネックでした。その分、おうち時間を満喫することは出来ましたが、家族と隔離された生活を送っていたので、日本での最後の日常を過ごせなかったのは心残りです。
結果として、この時期に感染したのは不幸中の幸いでした。暫く会えなくなる友人達との約束を毎日のように入れていたので、それ以降に感染していたら出国できなかったと思うと恐ろしくなると同時に、自己管理の甘さを痛感しました。隔離期間も念頭に置いたスケジュール調整が必要だったと反省しています。
【荷造り】
私は大きなスーツケースを2つ持って行きました。
荷造りは出国2日前に買い出しをして、前夜に必要最低限の物を必死で詰めました。最後に家の体重計が壊れている事に気付き、フィーリングで規定の重さを超えている!と判断し、幾つか抜いてしまいましたが、実際に空港で量ってみると2つで10kgも軽く、後悔しました。結局、後日、置いてきた物を母に航空便で送ってもらう事になりました(涙)
4. 今(機内で)の心境
タイトルを見て??と思った方もいらっしゃるかと思いますが、このブログは絶賛機内で書いております。
心境としましては、見送りに来てくれた母と別れるときは少し寂しかったのですが、今は、とてもワクワクしています。私は窓際に座っているのですが、お隣席のご夫婦がとても親切で、代わりにご飯の注文や片付けも手伝ってくださったりと、初めての一人フライト・一人海外で中、少し不安でしたが、他人様の温かさに触れ、感謝の気持ちでいっぱいになっています。
次回はカナダでの生活をお伝え出来たらと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました!

【写真】トロント空港にて(人の顔の部分はハートの絵文字で隠してあります)
|
この記事の先頭へ戻る
◇ 2022年9月【アメリカ・University of California, Berkeley 奥埜豪】初めまして!
この記事を折りたたむ
|
◇ 2022年9月【アメリカ・University of California, Berkeley 奥埜豪】初めまして!
こんにちは!
はじめての投稿となります。
慶應義塾大学経済学部2年、アメリカのカリフォルニア大学バークレー校に1年間の交換留学で来ている奥埜豪です!
バークレーは他の大学に比べて学校が始まる時期が早く、8月17日からGolden Bear Orientationという新入生やTransfer Studentに対するオリエンテーションがあり、8月24日から授業がスタートしています!

本来はこのはじめての投稿を渡航前に書く予定だったのですが、渡航前にやらなければいけないことが多く、書く時間がなかったので、先延ばしにしていました…すみません…
予定では渡航前の心境などを綴る予定だったので、渡航までの時間を振り返りながら、留学までの準備がどのくらい忙しいのかを何回かに分けて、渡航前シリーズとして、お伝えできればと思います。
それでは、初回の内容として、UCEAPへの留学決定から、UC内での留学先決定までについてお話しします。(慶應義塾大学においての留学出願プロセスは他の方が書かれているようなので省かせてもらいます)
それでは早速、渡航前シリーズ①の内容に入りたいと思います!
まず、初めに、これを読んでいる慶應生が交換留学でUC Berkeleyに行きたい!と思った場合、交換留学の志望校先にUCEAPという項目を入れて出願する必要があります。
UCEAPとは、University of California Education Abroad Programの略で、カリフォルニア大学全体の留学プログラムの事です。
カリフォルニア大学には、
カリフォルニア大学バークレー校(UCB)
カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)
カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD)
カリフォルニア大学サンタバーバラ校(UCSB)
カリフォルニア大学デイビス校(UCD)
カリフォルニア大学アーバイン校(UCI)
カリフォルニア大学リバーサイド校(UCR)
カリフォルニア大学サンタクルーズ校(UCSC)
カリフォルニア大学マーセッド校(UCM)
カリフォルニア大学サンフランシスコ校(UCSF)(大学院のみ)
の10個のキャンパスがあります。(キャンパスといってもそれぞれが総合大学としてほぼ独立しているので、別々の大学といっていいと思います。)
その全てのUCの大学の留学を、UCが統括しており、慶應から申し込む場合はUCEAPのプログラムになるので、UCEAPにまず申し込む必要があります。
つまり、慶應義塾から、"君はUCEAPで留学していいよ!"と合格をもらった時点では行く学校は決まっておらず、その後、UCに対して、"〇〇キャンパスに行きたいです!"と出願する必要があるのです!
ということで、11月頃にUC留学への合格を慶應義塾からもらった後、1月の中旬までにUCに対してどのキャンパスに行きたいかを出願しました。
UCに対しての出願に際し、必要なのは(2022年度の場合)、慶應義塾に出した諸々の出願書類に加えて、UC内のキャンパスの志望校3つと、それぞれの学校への留学志望理由、履修計画、メジャーなどでした。
履修計画では、実際にどの授業を取るのか、前年度のシラバスなどを参考に履修を組んで、なぜその授業が取りたいのか示す必要があります。メジャーに関しては、大学によって受け入れている学部や条件が違う事があるので注意が必要です。
因みに自分は
1.UC Berkeley
2.UC LA
3.UC San Diego
の順番で提出し、すべて経済メジャーで提出しました。
結果は3月の下旬頃にメールで伝えられ、今現在滞在しているUC Berkeleyになりました! (いつ連絡が返ってくるのか不透明なので、辛抱です…笑)
という事で初回は、渡航先決定までのプロセスに関して少しお話ししてきました。
次回以降、渡航先決定から渡航までにやってきたことを話していきたいと思います!
ここまで読んでいただきありがとうございました!
|
この記事の先頭へ戻る
◇ 2022年9月【オーストラリア・Griffith University 野口明純】住人紹介 vol.2
この記事を折りたたむ
|
◇ 2022年9月【オーストラリア・Griffith University 野口明純】住人紹介 vol.2
(2022年7月のブログからのシリーズです)
今回は住人紹介です。まずはフィリピン人のAndressから。彼は、今は映像制作の勉強を考えているそうです。オーストラリアの自然は静かな印象が強いと話していました。はじめて飛行機から降り立った時、オーストラリアの自然から、”Welcome home.”と言われた気がしたのだとか。Andressのご家族に会った事はありませんが、個性的な方々な気がしています。例えば、母は神話を伝える物語を演じる人で、親戚にはチェスのフィリピン代表がいるのだそうです!フィリピンには、蛇の毒など、自然の産物に関する独自の科学をおさめている家族がいるそうです。フィリピンでは「侵略者」とされるマゼランを倒したのも、この蛇の毒だとか。ちなみに、僕が最初住む場所が全然見つからなかったという話をしたら、オーストラリアの一部の不動産は、高いお金さえ提示されれば、例え入居の予約が入っていても、それを勝手に取り消して、高額な家賃を払う人を泊めることもあると教えてくれました。僕が入国当初、「日中の眠気に悩んでいる」と相談したら、体力は心臓と繋がっているから、日中に有酸素運動を行うと良いと、アドバイスをくれました。実際効果があったので、すごい人だなと思っています。彼にとって1番大事なのは、respect。互いを尊重する気持ちは、争いの無い世界には必須だと考えているそうです。
次に、コロンビアからのAndrew。今は僕と同じくグリフィスに通っています。過去に、僕が今住んでいる所から少し北の、ブリスベンという所で、英語を学んでいたそうです。日本人の彼女もいた彼は、日本に行った経験もあり、日本語の書かれたTシャツを持っています。アジア料理のレストランでバイトをしていて、賄いの米や野菜料理などを貰っています。この前は、「冷蔵庫から好きにとっていいよ」と言ってくれました。
三人目は、日本人のよしきです。彼はインドアな僕とは反対にアウトドア派で、強靭な体力の持ち主です。平日は、ショッピングモールの中にあるという英語学校に、朝8時から通い、家での昼食をはさんで、鉄板焼き料理店のバイトを夜遅くまでこなしています。平日の帰宅時間は23時あたりです。多趣味な彼とは、アニメやYouTubeの話をしたり、将棋を指したりと、たまに訪れる、時間があうタイミングを、楽しんでいます。
最後に、今は引っ越しをしたJamesについて話させて下さい。彼は、進撃の巨人などの戦闘系大人アニメが大好きな、イギリスにルーツを持つネイティブのオーストラリア人です。彼がいた当時は、家のあれこれを色々教えてもらいました。一緒にカードゲームをした思い出は、深く心に残っています。
シェアハウスでは、大学の枠を超え、様々なバックグラウンドを持つ人と生活が出来ているので、貴重な経験をたくさんさせて貰っています。次回は授業履修の経験とアドバイスについて話すつもりです。
※写真は右上から反時計回りによしき、Andrew、Andress、Jamesです。先月のクイズの答えは、来月あたりまでお待ちください♪

|
この記事の先頭へ戻る
◇ 2022年8月【オーストラリア・Griffith University 野口明純】住人紹介 vol.1
この記事を折りたたむ
|
◇ 2022年8月【オーストラリア・Griffith University 野口明純】住人紹介 vol.1
(前回の私の記事の続きです)
今回と次回で、今住んでいるシェアハウスの住人などを紹介出来たらと思います。家主は、前回の記事に写真がのっておりますCross夫婦です。この家には、僕を含め4人の男性が住んでいます。Andress(フィリピン人)、Andrew(コロンビア人)と、よしき(日本人)です。よしきは、以前住んでいたJames(オーストラリア人、両親はイギリスから)と入れ替わりで入居しました。
まずは家主のVince CrossとMerridee Crossです。Vince は木と金属の加工を、Merrideeは料理を教えていたそうです。Vinceは、ゴールドコーストでもたまに見かける、ヨーダの様なご老人で、歩きなどは非常にゆっくりなのですが、重いものを持ち上げたりなど、力が不思議にある方です。現役時代に指導をしていただけあって、家のあらゆるメンテナンスを一人でこなします。Merrideeは、年齢こそ伺っていない者の、お若い女性です。家の掃除や金銭管理など、契約に関する事などを管理している様です。この家では、4種類の掃除仕事を週一回、ローテーションで担当しています。それをやっていない人には厳しく追及するのがMerrideeですが、逆にしっかりやっていると、VinceもMerrideeも大きな信頼をよせてくれる様です。僕は日本の大学を卒業後、オーストラリア国立大学などの、オーストラリア国内の大学院進学を考えているのですが、「ゴールドコースト辺りに来ることになったら、またここに住んでね」と、あたたかい言葉を頂いています。
掃除、と書きましたが、特にMerrideeはとても綺麗好きです。ただし、そのような人がオーストラリアには多いのかと言われると、そうでもないのかも知れません。というのも、先述のよしきは、ここに来る前のホームステイ先があまりに不衛生だったのが、転居の最大の理由だったそうだからです。また、このシェアハウスはパーティー禁止、門限は無いが、夜は静かに、がルールなので、私のような人間にはとても快適です。都会からも大学からも丁度良く離れていて、静かながら、徒歩通学にも、買い物にも、困らない場所です。家賃が周りと比べて安価である点も外せません。
次回はいよいよ、住人紹介編です。
※写真はクイズです! 棚の何段目がAndress、Andrew、よしき、僕のものでしょう?なお、五段あるうちの一つは、共用のスペースです(その棚には、賞味期限切れのものもありました笑)。次回の住人紹介をヒントに、考えてみてくださいね~。

|
この記事の先頭へ戻る
◇ 2022年8月【アメリカ・University of Florida留学予定 金子舜汰】初めまして!
この記事を折りたたむ
|
◇ 2022年8月【アメリカ・University of Florida留学予定 金子舜汰】初めまして!
こんにちは!
2022年秋から、University of Floridaに留学する金子舜汰(かねこしゅんた)といいます。私は現在、早稲田大学社会科学部の4年で、今回は当大学の協定校制度を利用した1年の交換留学に行きます!
―自己紹介
初めに簡単に自己紹介をさせていただきます。私は早稲田大学の体育会水泳部に所属しています。水泳部となると、どの泳法が専門かという質問にいくのが一般的かと思いますが、私は競泳選手ではなく、「飛込競技」を専門にしています。「ぐるぐる回って水に入る、飛沫が少ないといいやつでしょ!」とよく言われますが、そのやつです(笑)。この競技を、小学6年の頃から10年ほど続け、高3の頃に全国優勝をしたり、日本代表として海外遠征に参加させていただくなど、ニッチなフィールドではありますが、長く選手をやらせて頂いています。

―なぜ留学?
留学を決意したのは、大学2年の冬でした。その年は2020年で、年始には東京五輪の選考会がありましたが、自分はわずかに13点足りず五輪への切符を逃しました。その後すぐにコロナ禍となり、それまでがむしゃらに五輪を目指していた日々が落ち着き、自分を見つめ直す機会になりました。「次の五輪はパリ、その時にはもう学生は終わっている」、そんな状況を前にして、今後の競技生活についても考え直さなければならないと感じました。マイナースポーツであり、社会人で続けていくことの難しさも、多くの先輩を見ながら感じていた自分にとって、小さい頃から漠然と興味を抱いていたもう一つ夢である「留学」へと矢印が振れていきました。父や周りの人間に相談し、直感を信じて動いてみようという勢いで、とりあえずアゴスの相談日を決めました。そして、塾に入ってしまったらもうやるしかなくなって、ひたすらにTOEFLの勉強へと励みました。
―TOEFL。シンドイ。^^
まあ、TOEFLは楽しいものではありませんよね(笑)。私自身、元の英語力も低く、長時間の4技能テストにも全くの不慣れで、入塾時の模擬テストは47点くらいだったと思います。
初めの3ヶ月は基本的な内容で、意外とやっていけるななんて余裕をこいていましたが、模擬試験での点数は全然伸びておらず、SNSのアプリをいくつか削除するなど、焦りとともに本腰を入れて再スタートしたことを覚えています。
以前書かせていただいたことがありますが、スコアや英語力に変化を感じたのは、「今やっている作業の意味」を考えるようになってからでした。例えば、スラッシュリーディングは、ただ意味を即時に訳せることだけでなく、日本語から英語の語順に頭を慣らす意味もある、といったことなどです。作業の意味を意識するだけで、単純でシンドイ英語学習も、少しモチベーションを保ってできると思います!
(あと余談ですが、勉強で減ってしまう睡眠時間に対して、朝に日光が入るようにしておくだけで、寝起きがだいぶ良く、体内時計も出来て、日中の眠気だいぶマシになった記憶があるので、眠い方は試してみてください!笑)
―留学先
早稲田大学のプログラムでは、基本的に1人10校程度希望が出せて、空きのある優先順位が高い大学に順に振り分けられます。「なぜ留学?」の項目で話しきれなかったのですが、私が留学を決めた大きな理由には、「日本と違うフィールドで飛込競技をやってみたい」という想いがありました。そのため、留学先大学もアメリカ中の大学チームを調べて書き出し、インスタグラムやwebを見て、各大学のコーチにメールをして(そして8割は返信が来ず^^;)、競技の環境も見ながら決めていきました。そして、昨年12月に、フロリダ大学に決まりました。この大学は飛込が強くて環境も良く、非常に楽しみにしていました。
しかし、現地大学コーチとやりとりをする中でわかったのは、“交換”留学 では、現地大学チームに所属できないことでした。大学チームに所属するには、現地大学の学位を取得すること、つまり、現地大学に正式に入り、卒業することが求められます。そもそも、交換留学でスポーツも目的にしてくるケースは少なく、あまり前例のない形であったようですが、後から発覚したために色々と振り回されることも多かったです。このブログを読んでいる方の中に、交換留学で競技もやりたい、と考えている方がいたら、アメリカでは、大学チームの受け入れは国の大学機関のルールとして存在しないということを、同じ失敗をしないためにもお伝えできたらと思います。
そういった理由から、現在は大学周辺のクラブチームコーチと電話で事情をはなし、なんとか競技には関われそうになりました。現地に到着したら、早速挨拶しに行こうかなと考えています。
長くなりましたが、そんな形でなんとか来週には出発できそうです。
楽しみも不安も最大限ありますが、たくさん吸収していきたいと思います!
では、行ってきます!
金子舜汰

最近買った留学のためのモノたち*ほんの一部
|
この記事の先頭へ戻る
◇ 2022年7月【オーストラリア・Griffith University 野口明純】涙からの涙の、宿探し
この記事を折りたたむ
|
◇ 2022年7月【オーストラリア・Griffith University 野口明純】涙からの涙の、宿探し
「衣食住」という言葉があります。本当に、これらさえあれば何とかなる、逆に、これらのどれかが無いと、どうにもならないと感じたのが、オーストラリア到着後に痛感した事でした。
まず、「衣」は持参していたので、心配はありませんでした。
「食」についても、ホテル近くのスーパーで調達でき、問題なしでした。
問題は「住」で、そもそも、オーストラリア到着時にはまだ決まっていませんでした。日本で寮やアパートを申請しまくっていたのですが、どこからもこれといった返事がなかったのです。とりあえず出国前に予約していたホテルに到着(ゴールドコーストの空港に到着してからは、予約していた、グリフィス大学のピックアップ・サービスの車でホテルまで運んでもらう)したものの、そこから行く先、行く先、断られるか、「部屋が空くのを待ってくれ」の連続でした。体は動いて疲れるわ、期待は裏切られて心も疲れるわ。一番ひどかったのは、こちらのメールに返信をしてこなかったアパート主が、ドアホン越しに、聞き取りにくい声でしゃべったので、聞き返したら、”We are full!” とはっきり言った時でした。この時は心の中で泣きました。これがタイトル最初の「涙」です。
希望をくれたのは、Flatmatesというシェアハウス探しサイトで、唯一正確な住所を送ってくれたCross家でした。教えてくださった場所に行き、待っていたら、Cross夫婦が来ました。そこからは家具の使い方や週一でやって欲しい家事、契約書など、めまぐるしく用事をこなしました。最後に入居が決まり、次の夜に、ホテルから移動した荷物とともに「自室」で横になった時は、安心感につつまれながら心の中で泣きました。これがタイトル二個目の「涙」です。
このように書くと、入居はなんとか順調だったのだなと思う読者もいらっしゃるかも知れませんが、それがそうも行きませんでした。家主のCrossと、新しいベッドのシーツ一式を新調したのですが、それが不良品で、返品しなくてはいけない事に。Cross家は遠くに住んでおり、その日は帰らなくてはいけなかったので、翌日私はたった一人で返品の交渉をしなくてはいけなくなってしまったのです。まあ、返品自体は滞りなくできました。
この経験から得た教訓は、「留学では早すぎる到着はリスクかもしれない」という事。私は、自分が勉強を始める学期の、ひとつ前の学期が続いている時期に到着してしまい、寮などに大勢の生徒が残っている問題に直面しました。
次回は、この素敵な家の推しポイントや、住人紹介ができるかもしれません。それでは、またの機会に。
※写真は、Cross夫婦との写真です。

|
この記事の先頭へ戻る
◇ 2022年6月【アメリカ・Carnegie Mellon University留学予定 上田彬正】初めまして!
この記事を折りたたむ
|
◇ 2022年6月【アメリカ・Carnegie Mellon University留学予定 上田彬正】初めまして!
初めまして、慶應義塾大学商学部三年の上田彬正(うえだあきまさ)と申します。
8月下旬から約1年間アメリカのカーネギーメロン大学(CMU)のビジネススクールに留学する予定です!今回は慶應の選考について話していきたいと思います。私は当初、ビジネススクールに留学して金融を学びたいと思っていました。今は経営専攻ということもあり、ベンチャー投資やスタートアップに興味が移りましたが、CMUはどちらの分野の授業もあったため、ラッキーという感じです。こんな感じで、イタリアに幼少期在住していたこともありテキトーな性格なのですがお付き合いいただけると幸いです。
私の選考はこんな感じでした。
1次選考
結果:書類落ち
第1希望 カーネギーメロン大学
第2希望 ダートマス大学
以下、アメリカの大学を第6希望まで書いた記憶があります。
2次選考
結果:カーネギーメロン大学派遣
第1希望 ボッコーニ大学
第2希望 ESSECビジネススクール
第3希望 カーネギーメロン大学
第4希望以下はかなり倍率が低いイタリアやドイツの大学を書いた記憶があります。
目次
1. 選考の形態
2. 選考の実態
3. 落ちてもチャンスはある!実は計5回チャンスがある!
1. 選考の形態
私の時は、基本的に①ES提出→②面接、の二段階の選考がありました。①では、志望動機と学業計画、英語のスコアを提出しました。
・英語スコア
私の時は英語のスコアが多少足りなくても応募でき、合格してから候補生として英語のスコアを上げる猶予期間が与えられていたみたいですが、今後は完全にスコアで足切りすること、面接を廃止することの二点の変更点があるみたいです。英語のスコアは個人的にはIELTSの方が取りやすいのかなと思います。CMUはIBT100以上又はIELTS7.0以上という条件がありましたが、両方とも受けている私にとっては、はるかにIELTSの要件の方が軽いように感じました。私の英語スコアは確かIBT90~95点、IELTSは7.5(R 8.5 L 8.0 W 6.5 S 7.0)だったと記憶しております。私は帰国ですが、純ジャパの友達もIELTS7.0を取っていましたのでしっかり対策すれば超えられない壁ではないかと思います。
・ES
ここは、かなり厳しく見られます。よく言われるのは、過去→現在→未来を意識して書くことです。具体的には、過去にどういう活動をして、現在どういう活動をしていて、未来こういうことをしたい、よって〇〇大学に留学して未来の目標に近づきたいというテンプレです。私は、恥ずかしながら留学したいという思いしかなかったため、過去の部分が薄く、そこで他の方と差別化ができず、一次選考に書類落ちしてしまったのだと思います。学業計画も留学先でどの授業を取り、どう自分の活動に繋げていきたいか見られます。
2. 選考の実態
私はGPAが3を切っていたので、そのような方はかなり厳しくESと面接が行われます。ですが、GPAが高いと結構甘くなる印象があります。私は面接では、学びたいことについてかなり深く質問されましたが、GPAが高い友達は談笑で終わったなんて方もいました。ですが、今後は面接がなくなるみたいなので、GPAとESがより厳しく見られるので油断は禁物です。
3. 落ちてもチャンスはある!実は計5回チャンスがある!
慶應の留学のチャンスが3回しかないと思っているそこのあなた!実は5回あることをご存じでしょうか?留学の選考は①第1期 英語圏 ②第2期 ヨーロッパ ③第3期 オセアニアの計3回ありますが、実は2次募集なるものがあるんですねー。そのため、
① 第1期
② 第2期&第1期の2次募集
③ 第2期の2次募集
④ 第3期
⑤ 第3期の2次募集
の計5回チャンスがあるわけです。
私は第1期で書類落ちしてしまいましたが、第2期で幸運にも第1希望のCMUの枠が空いていたため、2次募集で応募し合格しました。そんなことがあるので1期で落ちてもあきらめないで2次募集を探してみることが大事です。ただ、2次募集のデメリットとしては、人気の大学は埋まってしまって応募できないというのはあります。ですが、とにかく留学に行きたいという方にはうれしい情報なのではないでしょうか。
こんな感じで今後もゆるくブログについて書いていこうと思います。この情報が少しでも皆様の役に立つことを願っております。では!次回はおそらく留学準備編、ビザ発行や飛行機予約等のことを書いていこうと思います。
|
この記事の先頭へ戻る
◇ 2022年6月【オーストラリア・Griffith University 野口明純】焦った国内線探し~日本からゴールドコースト~
この記事を折りたたむ
|
◇ 2022年6月【オーストラリア・Griffith University 野口明純】焦った国内線探し~日本からゴールドコースト~
お久しぶりです。野口です。
今回は、予告通り、日本出発から、留学先のゴールドコーストに着くまでをお話します。私は、日本から一旦シドニーへ入国、その後、国内線でゴールドコーストに行っています。
日本からオーストラリアへの移動で、特に問題に感じた場面は記憶にないです。むしろ、離陸前に英語の会話が聞こえて、ワクワクしていました。(大事にとっておいた午後の紅茶を、セキュリティ・チェックで早くも失うことになった時は、少し寂しかったですが。)
問題は、国内線への乗り継ぎでした。これを読んでいる皆さんも、単に、同じ空港の建物の中で、別の搭乗口に行けばいいと考えると思います。私もそう考えていました。しかし、いくら歩いても探している場所は見つからないどころか、該当する搭乗口を示す看板すらない。離陸時刻は迫るばかり。職員さんに聞き、示された道順の方向に行ってみたら、まさかの電車の駅に着きました。そう、私が乗る国内線は、電車で移動した先にある別のターミナルで乗るものだったのです。その場で調べたところ、運賃には、持っていたデビットカードが使えるようで、一件落着。移動した先でも、職員さんの案内で搭乗口を見つけ、一安心しました。
安心するとお腹が減ってくるのは、どこでも同じなようで、近くのフードコートを10分ほどかけて吟味し、、、結局マクドナルドのハンバーガーを食べました。留学らしさも何も無いと思われるかもしれません。ただ、果たして日本のマックと同じ味がするのか、気になったのです。結果としては、少しオージービーフのジューシーさを感じつつ(留学補正が入っている?)、ほとんど日本のものと変わらない。流石、世界に名だたるフランチャイズ店のクオリティでした。一応、書いておきますと、パネルで選んだオプション(ピクルス多めなど)は、一切反映されていなかった模様です。店員さんは、テキパキしていらっしゃいつつも、おおらかで、お優しい方々でした。
電車を探していた時から感じていたのですが、オーストラリアは案内板などの表示がシンプルですね。日本の地図や案内表示は、土地の狭さもあるのか、精密・緻密なことが多いと思う中、オーストラリアのそれらは一覧性に重きを置いている印象です。
甘さすら感じる、湿気ていて温かいシドニーの風を切って、国内線は離陸します。飛行機に乗っていて思ったのは、市街地でも住宅が平たいという事。とくにシドニーの上空からは、高層ビルは見えませんでした。ゴールドコーストには海岸沿いにビルが沢山見えましたが、内陸は森か、平たい建物か、といった感覚です。
次回は、涙からの涙の、宿探しメインでお送りする予定です。

|
この記事の先頭へ戻る
◇ 2022年6月【オーストラリア・Griffith University 野口明純】初めまして!
この記事を折りたたむ
|
◇ 2022年6月【オーストラリア・Griffith University 野口明純】初めまして!
初めまして、野口明純(のぐちあきすみ)と言います。
現在、オーストラリアのグリフィス大学に留学中です。
日本では経済学関連のゼミに入っていたこともあり、留学先では経済やビジネスに関する授業をとっています。
初回では、Agosを知ってから、日本出発までをお話します。
Agosに入ったのは、自分が浪人中の時です。大学に入りやすくなるように、また、大学入学後の留学も見据えて、TOEFLの必要性を感じたので、試しにAgosでTOEFLの模試を受けました。
TOEFL形式が初見の状態で受けた結果は、確か38点だったと思います。今では信じられない数字です。これを、Agosの授業を受け、宿題をこなすことで、大きく伸ばしていきました。
Agosでの授業を受ける中では、単語クイズの勉強や、問題を解くためのスキルを重点的に復習していた記憶があります。ただし、このブログを読んでる皆さんは、先生のおっしゃった課題を、できるだけこなした方がよいと思います。私は、完璧までは目指さず、とにかく手と頭を動かしていれば、より高得点を狙えた、また、留学先で分かる会話や授業内容が増えていたと思います。日本でも、ポッドキャストやYouTubeなど、手軽に英語のコンテンツが聞ける場があるので、英語脳になるために、聞いておいてよかったと思います。
一年の浪人期間の後、大学入学を果たし、首尾よくTOEFLの目標点突破・交換留学の試験の通過を果たしました。留学先にグリフィス大学を選んだ理由は、自分の大学の交換留学先の中で、オーストラリアの大学が一番レベルが高かったからです。しかし、その矢先、コロナがやってきました。留学は2年間、延期また延期を繰り返しました。それでも留学の権利を手放さなかったのは、留学を通して体験できる未知の可能性を、どうしても捨てきれなかったからです。
相談に乗って下さったAgosの方々、大学の国際センターの長きにわたる尽力、家族の理解、ゼミの先生の「なにはともあれ留学が第一」という言葉など、周りの皆様のおかげで、幸い、大学四年生分の期間で、留学に行けることになりました。
留学決定からは、行く先の大学のホームページをクリックしまくり、住居に関してはどのようなサポートが受けられるか、コロナの対策はどうなっているか、現地の生徒と、日本出発前に話すことはできるか、など、履修登録はもちろんのこと、多方面の準備にいそしみました。
留学決定がグリフィス大学の一学期の始まりに近かった為、とにかくバタバタしていたのを覚えています。Agosの松永先生がおすすめされていた、アマノフーズのインスタント味噌汁も調達しました。
次回は、日本を出てから、写真にあります、留学先、ゴールドコーストに着くまでを話す予定(あくまでも予定)です。

|
この記事の先頭へ戻る
◇ 2019年10月【アメリカ・University of Washington 市川実花】はじめまして!
この記事を折りたたむ
|
◇ 2019年10月【アメリカ・University of Washington 市川実花】はじめまして!
はじめまして!早稲田大学政治経済学部に所属している市川実花です。9月後半からアメリカのシアトルにあるUniversity of Washingtonで交換留学をしています。本当は到着してすぐにこのブログを書こうと思っていたのですが、気づけばいつの間にか一か月たってしまいました、、、。今は、最初の中間テストが終わって少し落ち着いているところです。今回は、出願の過程と英語対策について書こうと思います。授業やシアトルでの生活については次回をお楽しみに!
【出願の過程】
私は、高校3年生の夏に参加したサマースクールがきっかけで、留学したいと考えるようになりました。
高校が大学付属だったことや、様々な機会費用を考えた結果、日本の大学に行きそこで交換留学しようという目標に落ち着きました。私は、出願理由には本音と建前があっていいと思います。
というのも、“留学したい!”という内側から湧き上がるような欲望にwhy?をぶつけるのは無粋だと思うからです。自分の知らない世界を見てみたい!とか留学ってなんかワクワクする!とかそういう内的自己認識に論理的な理由はないんです。ただ行ってみたい、本音はそれでいいんじゃないでしょうか。でも大学が持っている枠を使って交換留学をするわけだから、アカデミックな要素で肉付けする必要はあります。けど、この学問を勉強したいからこの大学のこの教授の授業が受けたい!という模範解答みたいな志望理由を書いていて思ったのは、日本からもアクセス可能なリソースは無限にあるのだから、それだけじゃ弱いな、というかつまんないなということでした。
知識や見識を得たかったら大学の図書館で本を読んでいればいいんです。それでも足りないと思ったら留学すればいい。当時大学一年生の私はもちろん日本でそれだけやり切った!とは言えない状況でした。だから、建前の部分にも自分の本音を盛り込めるような場所に留学したい、と思うようになりました(もちろん建前らしい建前もしっかり書きましたし、〇〇を勉強したい、というのも嘘ではないです。あくまでも留学したい一番の理由ではないということ)。
そこで、早稲田大学のGLFP(global leadership fellows program)というプログラムに、オリジナリティを感じました。これは、「多様な価値観を尊重できる真のグローバル・リーダーを育成することをテーマに、1年間の海外留学に加え、留学前後にも特別な教育カリキュラムが組まれる、学部4年間を通じたプログラム」です(苦笑)。GLFPは日米学生によって作られるコミュニティとして機能していて、留学前後にその中で学べる環境に魅力を感じました。
前置きが長くなりましたが、ワシントン大学を選んだのは、このGLFPの協定校だったから、正直それ以外の理由はありません。本当は、自分の学びたいことと合致していたのはUCLAやUCBで、GLFPの中でもそちらを希望していました。しかし、GLFP合格が決まった後ワシントン大学に派遣されるというメールが来て、「ワシントン大学だったらGLFPのコミュニティに参加できるがどうするか」と言われたとき、GLFP以外で他の大学を希望することもできましたが、迷わずその道を選びました。それは最初に言った本音と建前で本音を重視したためです。抽象的な話になってしまって申し訳ないのですが、私の出願過程はざっくりこんな感じでした。
【英語対策】
高3の夏の時点で、出願まであと一年しかないと知り、一刻も早く集中して英語のスコアを向上させなければいけないことが分かりました。当時の私は、TOEFLの4技能のうち純ジャパにしてはスピーキングが少し得意なくらいで、他はかなり低い水準だったと思います。高校受験はエッセイと面接のみで、高校の授業も大学受験を意識したものではなかったので、文章を早く読むことや文法・語彙などは壊滅的でした。
高校3年生の12月まで文化祭や卒業論文で忙しく本格的に英語の勉強を開始することはできなかったのですが、1月からAGOSに通い始めました。当時私は東京から電車で約2時間かかる場所に住んでいたので、AGOSに通うのは正直大変でした。私が留学したいという思いを応援して、環境を整えてくれた両親にとても感謝しています。
そんなこんなで4月に大学に入学しました。私は、大学1年の春学期はほぼ全てをTOEFLの勉強に捧げ、人間関係作りやバイト・サークルは秋になってからやる気を出すことに決めていました。通学の電車の10分間に必ず単語帳の1ページ分を覚えると決め、休み時間や空きコマも図書館にこもって勉強して、交換留学に大事なGPAもかなり意識していました。具体的な勉強方法は、AGOSの授業で言われたことを本当にそのまま実行しただけです。それ以上でもそれ以下でもなかった、というか宿題の量が多すぎてそれ以上をやる余裕はありませんでした。勉強方法に関しては先生たちはプロなのでそれに従うのが正攻法だと思います。
ひとまずこんな感じです!長々とまとまりのない文章にお付き合いいただきありがとうございました!
|
この記事の先頭へ戻る
◇ 2019年9月【デンマーク・University of Copenhagen 岡本 達哉】はじめまして!
この記事を折りたたむ
|
◇ 2019年9月【デンマーク・University of Copenhagen 岡本 達哉】はじめまして!
皆さん、はじめまして!
早稲田大学からデンマークのコペンハーゲン大学に留学している岡本達哉です。10か月という限られた期間ではありますが、デンマークでの学校生活や実生活など様々なことを赤裸々にお伝えできたらと思います。よろしくお願いします。
【自己紹介】
幼少期は親の仕事の関係でシンガポールに4年、タイで2年を過ごしました。しかし、いずれも日本人学校に通っていたため、英語と触れる環境は限られており、英語力もそこまでという感じでした。
【英語の勉強について】
AGOSではTOEFL iBT105点コースを一通り受講しました。高校から大学へは内部進学だったため、時間的にも比較的余裕があり、高校3年の冬頃から受講を開始しました。ReadingとWritingが特に苦手でいずれも目標にしていた25点をなかなか超えることができませんでした。
Readingは読むのがとても遅く、時間内に全て解き終わらないということはザラで、大きな課題でした。Writingは考えてばかりで、なかなか手が動かず、これもまた不完全燃焼のまま終わってしまうことが多かったです。Readingが遅かった理由としては圧倒的な語彙力不足により、分からない単語が出るたびに立ち止まっていたことでした。そのため、『TOEFLテストボキャブラリー+例文3900』という単語帳をひたすら1日20~30個ずつ覚えて、復習することを反復していました。結果、時間内にReadingを終えるという課題も解決でき、Writingでも語彙力が増加したことにより、スラスラと考えていることを吐き出すことができるようになりました。
点数は伸びましたが、最終的にはどちらも目標としていた25点は超えられませんでした...泣 正直、今でも不甲斐ないので、帰国後にまた再挑戦しようかと考えています 笑
【1ヶ月過ごしてみて】
留学先のコペンハーゲン大学では、今期3つの授業を受講しています。少ないように見えますが、それぞれの授業でreadingがしこたま出るため、これ以上授業は増やせないなという感じです。
こちらの授業に参加し、まず感じた違いは授業の開始時間です。授業初日に授業開始時間の10分前に教室に到着したら、誰もおらず、不安になっていたところ、授業開始時間になり、やっと他の学生たちが教室にぞろぞろとやってきました。結局授業が始まったのは予定時間の15分後でした。どうやらこちらでは授業開始時間(シラバスとかに書いてある時間)の15分後に授業を開始することが普通らしく、少し戸惑いました。
もう一つ驚いたこととしては、その試験の形態です。もう試験の話かという気もしますが....笑 こちらでは日本のように試験の日に一斉に筆記の試験を受けるということはほとんどなく、長いエッセイの随筆、またはオーラル(口述試験)になります。試験形態が違えば、対策も変りますよね.... これは3か月後にある試験に向けてじっくり考えていこうと思います。不安しかないですね 笑 想像もつかないです。授業では多少のカルチャーショックを受けながらも、授業外の時間にはWelcome Partyなどに参加するなどする他、生活に慣れるだけであっという間に1か月が過ぎてしまいました。
【なぜデンマーク?】

大学のロビーの様子です。照明がいいですね。
デンマークに興味を持ったきっかけは、メディアなどでもデンマークが世界屈指の幸せの国と称されていたことにあると思います。デンマーク人を幸せに感じさせている、その本質的な部分は何か、そもそも本当に幸せなのか(この疑問は1ヶ月過ごす中でさらに強くなりました)という疑問とともに、デンマークという国が持つ社会制度や文化、デンマーク人の物の考え方それ自体にも興味が湧くようになりました。
もちろん、デンマーク人がなぜ幸せなのか、という疑問に対する解は10ヶ月やそこらでは氷山の一角すら知ることはできないかもしれないが、10ヶ月で自分自身を納得させる自分なりの仮説や見解を持つことを目標にしたいと考え、デンマークを選択しました。これ以外にもデンマークを選んだ理由はいくつかありますが、長くなりそうなので、この辺りにしておきたいと思います。
それではまた次回!
|
この記事の先頭へ戻る
◇ 2019年8月【シンガポール・Singapore Management University留学後 廣瀬達也】帰国から4ヶ月、出発から1年経って
◇ 2019年3月【シンガポール・Singapore Management University 廣瀬達也】あなたにとっての留学とは?
◇ 2019年2月【アメリカ・University of California, Berkeley 松崎悠吾】UC Berkeleyの日常 (授業編)
この記事を折りたたむ
|
◇ 2019年2月【アメリカ・University of California, Berkeley 松崎悠吾】UC Berkeleyの日常 (授業編)
みなさん、お久しぶりです!
UC Berkeleyに留学中の松崎です。
気付いたらアメリカに来てから半年が経っていました。早いです。
今回はBerkeleyでの授業に関して、お伝えできればと思います。
【授業】
Berkeleyの1学期あたりの最低必要単位数は学部によって違いますが、だいたいの学部が12~13単位です。なので、ほとんどの生徒は1学期に3~4つの授業を履修します。私もその例に漏れず、専攻であるEconomicsの授業を2つ、中国語の授業を1つ、計3つの授業をとっています。
加えて、交換留学生はminimum GPA (2.7くらい?)をとらないとVisaに支障をきたすため、きちんと勉強をする必要があります。
この学校の授業は基本的にBerkeley timeといって、アナウンスされている時刻の10分後に始まります。張り切って10分前とかに行くと20分間暇になります。
経済学部の授業は(おそらく他の専攻も)ほとんどがLectureとDiscussion sectionをセットで履修する必要があります。Lectureはいわゆる授業のようなもので、日本と同じように多いクラスだと数百人単位で授業が行われます。Sectionは週1回1時間で、数人から数十人のグループに分かれ、GSI (Graduate Student Instructor)と呼ばれる教授補佐の大学院生とともにディスカッションをしたり、授業で教わった難解な部分の復習などを行います。個人的にこのSectionのシステムはすごく気に入っていて、少人数かつ年齢が近いGSIとともに学習できるため、質問などもしやすく理解を深めるのに大いに役立ちます。また、LectureやSectionで使われたスライドやプリントは、ほとんどの場合bCoursesと呼ばれるサイトにアップロードされます。かなり便利です。

(Lectureの様子です。日本とあまり変わりません。ただ、質疑応答だけは盛んです。)
ここに来る前に卒業生など色んな方に「Berkeleyは勉強量すごいよ、しんどいよ」と言われました。実際に勉強量はかなり多いと思います。朝起きて勉強して授業行って勉強していたら1日終わっています。
理由としてあげられるのは、授業のレベルの高さと課題や予習復習の多さです。Berkeleyは世界トップレベルの大学であり、授業内容はやはり難しいです。また、Econの授業では1学期あたり4~5つの課題、中国語に関しては毎日相当量の課題が出ます。特に専攻であるEconの課題はとても難しく、復習をきちんとして理論をちゃんと理解する必要があります。
(特にEconの授業について言及すると、SociologyやPolitical Scienceといった他の社会科学に比べると、Readingとして読むべき文献や本は少ないように思います。主に授業で習った理論をきちんと理解するのに時間をかけるイメージです。一方でSociology majorなどの友達は何百ページもあるようなReadingをひたすら読んでいます。その点、Econは社会科学専攻という枠組みの中では少し特殊かなという気がします。ちなみにアメリカではEcon majorは理系という認識らしいです。文系っていうのは数学を使わないPhilosophyやHistory majorとのこと。)
ここまで少し脅すような書き方をしてしまいましたが、留学する前に興味のある学問を学べる基本をしっかり身につけて、予習復習をきちんとしていれば良い成績もとることができると思います。また、クラブ活動に参加したり、週末に友達とごはんに出かけることも十分可能です。生徒はみんな学びたいことを勉強しに大学に来ているので、たとえ授業が難しかったり、課題が多くても充実感はとてもあると思います。(リアルな目線でいうと、寮に帰っても他にすることがないので、みんな自然に勉強します。)
ということで今回は授業について書かせていただきました!
次回はBerkeleyでの生活についてお伝えできればと思います。
最後まで読んでいただきありがとうございました!
P.S.
・月曜日から金曜日まで毎日中国語で授業を受け、常に課題が出るので、もはや中国に語学留学に来たのではないかと最近思いはじめました。
・この大学に多いのか、アメリカに多いのかは分かりませんが異常に左利きが多いです。
・シンガポールではアリが大量発生しているらしいですが、Berkeleyではアライグマとリスが大量発生しています。

(松崎 悠吾)
|
この記事の先頭へ戻る
◇ 2018年11月【スロベニア・University of Ljubljana 柳沢甫】スロベニアでの留学生活あれこれ
◇ 2018年11月【シンガポール・Singapore Management University 廣瀬達也】秋学期を終えて
◇ 2018年10月【スロベニア・University of Ljubljana 柳沢甫】なぜ、スロベニアへ??えっ、なんで??
この記事を折りたたむ
|
◇ 2018年10月【スロベニア・University of Ljubljana 柳沢甫】なぜ、スロベニアへ??えっ、なんで??
みなさん、はじめまして。立教大学異文化コミュニケーション学部に所属している柳沢 甫です。9月後半から、スロベニアのリュブリャナ大学文学部アジア研究学科 (University of Ljubljana Faculty of Arts Department of Asian Studies) に留学しています。そして、来年7月後半からロンドン大学アジア・アフリカ研究学院 (University of London, School of Oriental and African Studies SOAS)のサマースクールを受講する予定です。スロベニアでは、主に日本語教育・文化教育、イギリスでは、国際関係学を勉強しに行きます。
今回は、私が留学をしようと思った理由・なぜ、非英語圏のスロベニアを選んだのか・英語対策について(苦労したことやアゴスでの思い出など)・奨学金準備の4点についてお話ししたいと思います。
【なぜ、スロベニアを選んだのか?】
私は、もともと国際関係学・紛争研究に興味を持ち、本学部に進学しました。しかし、「基礎演習」という学部授業で、外国人労働者が増加すると共に外国学生生数も増加している問題を扱った時に、日本語教育について興味を持ちました。授業では、公立学校で日本語指導が必要な児童学生は増加し、学生対象が多様化している中で、そのうちの2割が日本語指導を受けることが出来ていない状況を学びました。
この問題を知ると同時に「日本語学概論A」という日本語学を学ぶ授業では、非日本語母語話者への日本語教育の意義について学びました。外国人が日本語を学習していくうえで、母語話者は、どのような方法で何を重要視し教えることが必要なのか、そして、外国人と日本語を介する時、どのようにコミュニケーションを取ったら良いのかについて疑問を持ちました。そこで、リュブリャナ大学では、日本語教育や日本語学をより深く学ぶことができ、また後期に授業インターンが出来るという魅力があり。そこで、日本から遠く離れたところで日本語を学ぶ学生たちに、何を、どう教えたらいいのかと、試行錯誤することで、新たな発見が生み、見いだせられるのではないかと感じました。
また、リュブリャナ大学は、生徒数で世界最大規模の総合大学です。よって、他の大学とは違い、様々な国や地域から留学してきている点で、多種多様な考えに触れることができ、そのうえ、様々な文化にも触れることができます。日本語に対する多種多様な意見を聞け、様々な人たちと交流することで、前述したコミュニケーションのあり方についても学ぶことができるという点も含め、リュブリャナ大学を志望しました。
【英語対策・書類作成について】
スコア・書類提出が、大学一年の秋学期はじめだったので、IELTSのスコアを伸ばそうと必死に課題や先生方とのアドバイスを聞き、自習漬けの日々でした。多忙を極めながらも、アドバイザーの田中さんと適宜面談をしながら書類作成をしていただいた。その結果、勉強と書類作成をバランスよく行うことができ、最後に慌てて書類を書き上げるといったことがなく、余裕をもって終わらせることができました。私は、5月初めにAGOSに入塾し、残り3か月でスコアを1.0あげなければならなかったので、とてもつらく、自分との勝負でした。Academicなテストなので、単語が難しすぎて覚えにくく、一度あきらめかけたこともありました。しかし、積極的に先生に質問し、授業内容以外のメンタル面の維持や勉強法なども質問したことで、IELTS対策はもちろんのこと、日々の勉強姿勢そのものも変えることができ、英語そのものに対する取り組み方の姿勢を変えることもできました。
自分で心掛けていたことは、①毎日単語を30語覚える②毎日BBC NEWSを聴く③授業で学んだことは、その日中に復習する、の単純なことを日課としていました。単純な心掛けに見えますが、意外と継続することは難しかったです。ですが、3週間継続して続けられれば、良い結果に結びつくことに気づきました。
【奨学金について】
私は、第9期トビタテ留学JAPANと、埼玉県発海外行き「埼玉県学生親善大使」奨学金、スロベニア政府奨学金、立教大学のグローバル奨学金・校友会成績優秀者奨学金の5つの奨学金受給生として、留学生活を送っています。なかでも、トビタテ生として、6月にスロベニアで行われる”Japan Day”での書道パフォーマンス披露といったプロジェクト、また埼玉県学生親善大使として、スロベニアにおいて埼玉県の和紙のPRを行いながら、奨学生として遂行しています。
これらの出願については、とても労力を費やしました。特に、トビタテは、書類審査・面接審査(個別面接・グループ面接)をクリアしなければならず、とても大変でした。特に私は多様性人材コースの志望でしたので、人一倍にユニークさや面白さを要求されました。AGOSアドバイザーと、大学のトビタテOBなどに面接練習などを頼むなどして、無事トビタテ生として現在羽ばたくことができました。
埼玉県発海外行きに関しても、書類選考で問われることは少ないものの、面接選考で、質問責めの嵐でした。しかし、トビタテ選考の際に、「留学で自分がしたいことは何か」について自分で明確なビジョンを描けていたため、自分の答えに自信を持ち続けることができました。
ここで、さらにトビタテ生の魅力などをお話ししたいのですが、字数も限られているので、ここまでにしたいと思います。今後のレポートでも適宜、魅力についてお伝えできればなと思います。
今後とも、スロベニアでの留学生活に加え、各国周遊記、スロベニアの魅力、トビタテのプロジェクト進捗も随時お伝えしますので、楽しく読んでいただけたら幸いです! では、一年間よろしくお願いします!!
(柳沢 甫)
|
この記事の先頭へ戻る
◇ 2018年10月【アメリカ・Western Michigan University 山崎実也】皆さんはじめまして!
この記事を折りたたむ
|
◇ 2018年10月【アメリカ・Western Michigan University 山崎実也】皆さんはじめまして!
皆さんはじめまして!
慶應義塾大学からウェスタンミシガン大学に交換留学している山崎実也です。
これから8か月の留学生活の中で、驚いたことや印象的だった出来事を中心にこのブログで発信していこうと思います。よろしくお願いします。
軽く自己紹介させて頂くと、現在法学部法律学科の2年生で留学先でも法律、とりわけ英米法を学ぶ予定です。小学生の頃、シンガポールに3年ほど住んではいたのですが、日本人学校だったので、英語力は完全な純ジャパです。笑 なので今回の留学で人並みに喋れるようになりたいと思っています。笑
前置きはこのくらいにして今回は、履修システムについて紹介します!
通常、日本の大学では(慶應もそうですが)、人気の授業は抽選で決まる場合が多いですよね?自分も来る前はそう思っていましたが、実際に来てみると自分が履修したいと考えていた授業は埋まっていました・・・。
そこでアカデミックアドバイザーに相談したところ、wait listという補欠登録の方法を教えてもらいました。wait listについて説明しましょう。例えば自分が履修したい法律の授業の定員が250人で既に埋まっていた場合、履修することは出来ませんよね?しかしながらwait listに入れておけば、もし法律の授業とは別の授業を履修する人が出てきた場合、その人の分の枠が減ります。そういったことが起きたときに初めて、wait listに登録されている人が履修を許可されるという仕組みです。
でも、実際そんなに変更する人はいないのでは?と思われるかもしれません。ところが、意外と学期がスタートしてみるとかなり変動がありました。自分も半ばあきらめ半分で2つの授業をwait listに入れていましたが、運よく2つとも空きが出て履修することが出来ました!なぜ学期がスタートしてから履修を変更する人が多いのかということについてですが、最初の1週間は授業見学期間なるものが存在し、実際に授業に参加してみて、「思っていた内容と違う」とか「教授の声が小さすぎて聞き取れない」だとか、初めてわかることが多々あるためです。そのため、自分を含む交換留学生は初めの段階では、希望の授業を履修できずにみんな不安がっているという状況でしたが、最終的にはほぼほぼ予定通りに取りたい授業を履修する事が出来たように思います。
せっかく自分の希望が叶う形になったので、しっかり取り組みたいと思っていますが、聞いてはいたけど教授の話すスピードは本当に早くて、正直ついていくのは大変です。笑
次回はそのあたりについても詳しく触れられればと思います!それではまた!
|
この記事の先頭へ戻る
◇ 2018年9月【シンガポール・Singapore Management University 廣瀬達也】皆さんはじめまして
◇ 2018年8月【アメリカ・University of California, Berkeley 松崎悠吾】皆さんはじめまして!
この記事を折りたたむ
|
◇ 2018年8月【アメリカ・University of California, Berkeley 松崎悠吾】皆さんはじめまして!
皆さんはじめまして!
慶應義塾大学経済学部3年の松崎悠吾と申します。
私は現在カリフォルニア州にあるUniversity of California, Berkeleyに交換留学生として来ています。早くもこちらに来てから約1週間が経ち、生活にもかなり慣れてきました。
今回は、1年間ブログを書くのに先立ち、少し自己紹介をさせていただこうと思います!
【自己紹介】
海外在住経験のないいわゆる純ジャパで、中高となんとなく過ごしてきました。
高校生の時に短期でイギリスに留学に行った際に「海外で学びたい」と思い、大学で交換留学をすることを決めました。BerkeleyではEconomics Majorとしてゲーム理論や行動経済学を学ぶ予定です。
【UC Berkeley】
1868年にできた州立大学で、10大学からなるUCシステムの中でも最も長い歴史を誇ります。世界一の公立大学として知られていて、教員や生徒たちはそれをすごく誇りに思っています(ちなみにライバルは同じカリフォルニア州にあるStanfordでことごとくネタにされています笑)。ほとんどの学部が全米でもトップクラスで、入るのがとても厳しいと同時に授業もものすごくタフだそうです。

【留学を志した理由】
中学からなんとなく英語が好きで勉強していましたが、やはり高校でイギリスに少し留学したことが大きかったです。留学先の高校の生徒はOxfordやCambridgeに行くような生徒ばかりですごくレベルが高かったことに加えて、日常でも様々な価値観を知ることができたり、新たな視点から物を見られるようになったことから、大学でもぜひそのような環境で学びたいと思いました。
Berkeleyを選んだ理由は色々ありますが、「世界のトップ大学で色んな生徒に出会いたい」「専攻である経済学をもっとacademicに学びたい」というのが主でした。
1年間しかいることが出来ないので、楽しみながらめちゃめちゃ勉強しようかなと思っています!
私もそうでしたが、日本からではなかなか海外の大学の情報を得るのが難しいため、このブログでは留学先での生活の「生の声」をお届けしたいです!これからも引き続きよろしくお願いいたします。
P.S. この辺実はめちゃめちゃ寒いです。8月なのに夜は10℃くらいだし、カリフォルニアってハワイのようだと思っていた私は凍えそうです。
ちなみにスポーツチームの愛称はBearsで、オリエンテーションでは「Go Bears!」ばっかり言っています。とりあえず「Go Bears!」って言っておけば仲良くなれるのでオススメです。
|
この記事の先頭へ戻る
◇ 2016年6月【アメリカ・ノートルダム大学より帰国 前田陽介】日本人初!NDアメフト部でマネージャーやってみた(後編)
この記事を折りたたむ
|
◇ 2016年6月【アメリカ・ノートルダム大学より帰国 前田陽介】日本人初!NDアメフト部でマネージャーやってみた(後編)
帰国してから2週間程が経とうとしている。
帰国直後は時差ボケにKOされた。3~4日の完全休養を経て、恋しさの募っていた居酒屋やラーメン屋、銭湯などを巡りながらのんびりしていたら、あっという間に2週間が経っていた。自分の帰国を祝しておかえり会を開いてくれる友達が大勢いて嬉しい限りである。
6月6日からの数日間、在学中の慶應義塾大学では「留学フェア」という留学情報交換会が開催され、帰国生として情報提供側として参加した。帰国後十分に一息ついた今、そして現在留学を選択肢の一つとして考えている下級生の相談を受けてみて、改めて留学とは一体全体何だったのか、考えさせられる。
結果から言うと、留学は「自分にしか語れないストーリーを探す旅」だ。全く新しい環境で過ごした10ヶ月を、一行の言葉に凝縮するのは大変困難だとすぐに気付いた。しかし、先の言葉なら、なんとか頷けるくらい的確に凝縮できているかな。なんて考えている。
留学前の自分に、自分にしか語れないストーリーは、あっただろうか。幸運にも、僕の周りには経験豊富で優秀な先輩が沢山いた。彼らの語るストーリーはユニークで、面白い。いつも尊敬していた。彼らの周りにいれば何とかなるだろう、と甘んじていた時期もあったかもしれない。だから、留学の志望理由書の作成には苦戦した。慶応の提携校のリストを眺めて、大学のランキングを調べて、ランキング上位だからきっと有名校なんだ!というような曖昧なリサーチばかりしていた。そんな甘いリサーチを元に、根拠もそこそこに有名校の名前を志望校欄に連ねた。
一次募集でどの学校にも引っかからなかったのも頷ける。1週間は泣いて、立ち直って、AGOSの横山さんや松永さんのお世話になりながら、何としてもアメリカに留学したいという思いだけを頼りに、必死に考えを捻り出して、二次募集でノートルダム大学への道が開けた。こんなきっかけではあったが、こうして僕はノートルダム大学のあるサウスベンドの街へ飛んだ。
ありきたりの人間になってはいけない、とノートルダム大学は教えてくれた。1万2千人を超える学生数、多様なバックグラウンド、世界中から集まる留学生。人と比べっこしていては、何十年あっても足りない。指をくわえて人のことを見ていては、ストーリーなんて生まれない。何かやりたいことはないかな。何かできることはないかな。初めてアメフトの試合観戦をしたのはちょうどその時だった。武者震いした。アメフト部に心の底から興味を持った。何か、なんでも良い、自分がここでできることはないか。学生マネージャーの応募がかかった時、僕は飛びついた。
球拾いから機材の管理まで何でも全力でやった。
自分がこのチームにいれるのは、僅か一年間。後悔のないよう、やれることはなんでも、やってみたかった。例えば、通常、誰もが避けるスパイクの磨き作業にも授業の合間を縫って参加した。アウェー戦のテレビ中継で選手達のスパイクが黄金色に輝くのを見て、ニヤニヤしていた。今思えば、ちょっと変なやつだ。
確かに、裏方の地味な仕事も多かった。しかし、何よりも嬉しかったのがマネージャーとして活動することによって数多くの学びを得られたことだ。僕がノートルダムで学んだ貴重な教えの一つに、「一流であり続ける」という教えがある。たまたま配属されたチームのキッカー部隊が先生だ。ある日の練習の後、一番仲良くしてくれたキッカーのJustin選手に一つの質問をしてみた。
「キッカーは常に得点シーンで試合に登場する。8万人に囲まれながら、相当のプレッシャーがあるだろう。それなのに、ジャスティンはいつもクールだ。スッとフィールドに駆けてきて、ルーティーンを卒なくこなし、綺麗なフォームで脚を振り抜く。あの時は、何を考えているの?前のキックで失敗している時とか、特に。」
ジャスティンの答えは単純明快だった。「やることをやるだけだよ。ハハッ。」微笑みながら答えた。気になったのでも食い下がる。「なんだよそれ、やることをやるだけって。」彼はこう答えた。「いつも練習見ていて分かると思うけど、おれたちは練習の時から私生活まで常に一流を目指しているんだ。みんなが本気でそう思っているから、試合のキックも練習のキックも一緒。何万人に囲まれても一緒。やることをやるだけ。」おそらく、一流の選手と二流の選手の境界線は、競技の熟練度ではなく、その選手の考え方や哲学などの深いレベルに存在する。つまり、一流になるには、技を真似するだけでなく、思考や哲学レベルまで参考にしないと、本質に辿り着けない。(最後に「まあ、結構疲れるんだけどね」と付け足す彼は、人間味溢れる良いやつだ笑)
そう言われると、選手達が練習中に見せるさり気ない行動や態度にも、意味があることに気が付き始めた。練習と練習の間は素早く移動し開始の笛が鳴った瞬間に次の練習メニューを始める・仲間の気の抜けたプレーがあればすかさず声を上げて指摘する・チームメイトは仲間でありライバルであるという関係etc... 「ノートルダムだから強い」というよりか、「選手一人一人が強い」という感覚だ。これは、一般的に強いとされている組織にも共通して言えることではないだろうか。
僕はまだまだこれから成長していかなくてはいけない。しかし、一流の仲間達に出会うことができたし、彼らの持つ一流としての本質を垣間見ることもできた。これは僕の財産だ。一流になる努力をしなければ、と気が引き締まる。ノートルダムアメフト部は僕に大切なレッスンを教えてくれた。
他にも、両親の寛大な心と温かい支援のお陰で沢山の経験をさせてもらったが、僕の留学生活で最も価値があったのは、アメフト部での経験である。こういった「自分にしかない経験」が、自分にしかない視点を形成し、自分を特別な存在にする糧になっていく、と信じたい。
だから、留学は自分にしか語れないストーリーを見付けてくることに重要性があるのだと感じる。海外にいることは大きなチャンスだ。新しいアイディアや視点に溢れている。固定観念など迷わず取っ払って、その土地で感じたこと・面白そうなことを素直に受け入れ、何でも挑戦すると良いと思う。もちろん、留学の目的は人それぞれで良い。英語力を◯◯まで向上させたい、国際政治の領域で海外の学生と本気で議論したい、現地の文化に触れながら日本文化をちょっとでも広めていきたい、何でも良い。その目標の達成のために全力を尽くすことは、スタートラインに立つ作業だ。スタートラインに立ったら、そこに自分にしか発揮できないスパイスを探してほしい。そのスパイスが、その土地・学校ならではのスパイスだと、なおさら面白い。先日オーストラリアに旅立ったサーフィン好きの友達に、「勉強の合間を縫ってサーフィンしてたら、プロサーファーになっちゃいました」くらいのストーリーの方が面白いとアドバイスした。その過程で様々な人や価値観、学びと遭遇することができるからだ。冗談だと思われたかもしれないが、僕は本気で言ったつもりだ。
もし自分が、留学に行っていなかったら。ノートルダムじゃなかったら。
何をしていただろう。何を語るのだろう。
※末筆ながら、この一年間、当ブログをお読み頂き誠にありがとうございました。前田陽介からは、当記事にて最後の投稿とさせて頂きます。振り返れば、留学時代の甘いも酸いも描かれたブログとなりました。出国前のワクワクと緊張の入り混じった自分や、アメフト一辺倒な自分(笑)、ちょっと気が緩んだ自分、帰国して少し時間が経った自分... 読み苦しい内容や未熟さが露呈する内容もありましたが、これが等身大の自分です。謹んで受け止めて、これからも精進して参ります。こんな自分にブログを投稿させていただいたAGOSの皆様にも感謝申し上げます。
|
この記事の先頭へ戻る
◇ 2016年5月 【アメリカ・ライス大学 小松夏実】海外経験ゼロの理系女子がアメリカで感じたこと...
この記事を折りたたむ
|
◇ 2016年5月 【アメリカ・ライス大学 小松夏実】海外経験ゼロの理系女子がアメリカで感じたこと...
こんにちは、ご無沙汰になってしまってすみません!慶應義塾大学理工学部の小松夏実です。米国ヒューストンのライス大学での約9ヶ月の交換留学が先日終了し、これから8月までカナダのウォータールー大学で研究生活です!(ライス大学で研究もしており、そのご縁でウォータールー大学の教授から研究オファーをいただき、今に至ります。) ウォータールーは大学以外何もありませんがとても綺麗なところです。
さて、今回再びブログを書かせていただけるということで、何をご紹介すれば皆様の参考になるのか悩んだのですが…
①学部交換留学をおすすめする理由、②理系の学生に留学をおすすめする理由、そして③総括の三本立てでお送りしようかと思います
1.学部交換留学をおすすめする理由
留学方法はたくさんありますが、私は学部での交換留学が一番金銭的にも、期間的にも、そして学部であるという点でも“お得”だと思っています。
*金銭的にお得
まず、一番大事なお金の話からさせてください(笑、でもほんとに一番大事ですよね!) 基本的に、各大学から協定校へ派遣される交換留学では、自分の学校に授業料を払い続け、在籍校が派遣先に授業料を払ってくれます。特にアメリカなどでは授業料が高いので、とても得ができるシステムです。
私の場合、留学費は全て自己負担だったので最初は金銭面での不安が大きかったのですが、この授業料の制度のおかげで無事留学できました!
*期間がちょうど良い
交換留学は通常約一年間(半年の場合も)です。一年という期間は、他国に本当の意味で“慣れる”という点においてちょうど良い期間なのではと感じました。例えば、私の語学力の変遷を振り返ると…3ヶ月で全神経を集中させなくても授業が聞けるようになり(笑)、5ヶ月で同じことを毎回二度言わなくてもよくなり(苦笑)、7ヶ月目位でようやく英語が苦じゃないと思えるようになりました。英語がわかるって便利だし楽しいなと思えるようになったのもこの7ヶ月目以降だったので、英語力ひとつとってみても一年くらいのまとまった期間留学できるのには意味があると思います。
*学部生ならではの経験
では高校や大学院留学と比べてどうなのか。学部留学は学部生ならではのお得な経験がたくさんできると思います。例えば、寮生活。半強制的に異文化の中に飛び込める最高のシチュエーションです。片付けができないし夜な夜なパーティーする隣人にイライラすることもあれば、何かあったときすぐそばに友達が24時間体制でいる環境に救われたこともあります。自分の留学生活を振り返ったときに寮生活は異文化経験面と精神面でとても大きかったです。
2.理系の学生に留学をおすすめする理由
理系の皆さん、ぜひぜひ留学目指してみてほしいです!!とっても!!というのも、日本人研究者は技術は素晴らしいのにそれを伝える“発信力”がないと思うからです。まず、英語がしゃべれれば、それこそ世界中の人とコミュニケーションを取ることができます。ブレイクスルーには多様性が必要不可欠ですよね!また、アメリカの学部では理系の授業であれプレゼンテーションやディスカッションをしたり小論文を書いたりするは当たりまえです。つまり、理系学生に学部留学は英語力をつけるという意味でも発信力をつけるという意味でもぴったりなんです!
そして、もし理系学部留学ができたなら、絶対試してほしいことが2つあります。
*研究をする
自分の留学先のいろいろな研究室のホームページを見て、興味のある分野の教授にメールしてみてください。海外では学部1年生から研究室に加わることも多いので、意外と受け入れてもらえます。(さらに研究室活動で単位を取れることも多いです。) 現金な話をすると、研究経験があればそれを履歴書に載せられたり、論文に名前が載ったり、教授に推薦状を書いてもらえたりするので将来とっても有利です。ただ、私が自分の研究経験から得た一番の財産は“問題解決力”かなと思います。目標があって、計画を立てて、実行に移す。もちろんうまくいきません。原因を究明して、打開策を考える。でも失敗する。考え直し。私の研究はそんなことの繰り返しでした。でもだからこそ、資料の探し方、他者とのディスカッション、基礎を重んじること、健康でいることの大切さを学び、失敗や問題にどう向き合えばいいのか少しわかった気がします。私は研究経験から勉強面だけでなく人間的にも成長できたと感じるので、これから留学する方にもぜひ挑戦してほしいです。
*大学院レベルの授業をとる
ずばり利点は2つ、少人数授業(が多い)ことと大学院生と知り合えることです。少人数授業なら例え内容が難しくても教授やTAの時間をたくさんさいてもらうことができます。さらに、私は院生と話す中で大学院のイメージが変わりました。さらに海外の大学院を目指している人なら、おすすめの勉強方法や出願のこつなどもたくさん聞けます。
3.最後に
自分の留学生活を振り返って思うのは、畏れ多い程恵まれていたということです。ライス大学という素晴らしい大学で勉強ができ、研究の指導教官、研究パートナー、研究テーマにも恵まれ、さらに大切な友達がたくさんできました。今まで支えてくださった全ての方に感謝してもしきれません。本当に、信じがたいほどラッキーでした。そして今は、浅はかで理想主義的ではありますが、「私をここまで押し上げてくれた“教育”をもっとたくさんの人に」という思いから、教育の普及に私の武器である科学技術をいかして携われる道を模索中です。
もし、この記事を読んでくださっている方の中で留学を迷っている方がいるなら、自信を持って留学をすることをおすすめします。もちろん大変なことも辛いこともたくさんありますが、大変だし辛いからこそやる価値が、得られるものがあるのではないでしょうか。そして!楽しいことや素晴らしいこともきっとたくさん待っています。この記事が少しでも参考になれば幸いです、何かお手伝いできることがあればいつでも連絡してください!
|

ライス大学にて

ウォータールー大学近くの公園
|
この記事の先頭へ戻る
◇ 2016年5月 【アメリカ・ノースイースタン大学 余語憲太】なにごともなかったかのように
この記事を折りたたむ
|
◇ 2016年5月 【アメリカ・ノースイースタン大学 余語憲太】なにごともなかったかのように
午前9時、僕はいつもの食堂に向かっていた。
ある試合を生で見ることができないので、
速報情報サイトでcommand+Rを押し、更新しながら試合の流れを追いかけようと思っていた。
だから僕はパソコンを片手に持ち、向かっていた。
食堂に入ると、そこに人影はほとんどなかった。
試験が最近になって終わり、学生は帰路に就いているらしい。
まずオレンジジュースを飲み、目玉焼きをもらって、テレビが目の前にある席に何気なく座る。
車のCMが流れていたが、このテレビは音がでない。
誰が見るんだと思いつつも、パソコンを開き、試合がそろそろ始まることを確認した。
「Leicester City vs Manchester United」
確かにそうテレビには映し出されている。まもなく試合が始まった。
---------------------------------------------------------------------------
留学には失敗した。
そもそも知らなかったことが多すぎる。
例えば
僕はよく勘違いをしている。それも考えすぎたことからの勘違いなので非常に厄介だ。
でも不思議とその「勘違い」を数日前でさえもしていて悪かったと思ったことは一度もない。
なぜだろう?
もう一つ
ボストンに来る前にはボストンに来る理由があったはずだ。
しかし、ここで生活している中で、ボストンでも日本でも関係ないことがわかった。
そうとは言ったものの、ボストンに来なければこのことに気づけなかったと思っている自分もいた。
なぜだろう?
そうやって色々考えての結果、様々な小さな決断を積み重ねていっていた。
そうしている内に勝手に大きなものに変貌していっていた。
--------------------------------------------------------------------------------
レスターシティの今シーズンの目標はあくまでも残留のはずだった。
(開幕前、レスター優勝についた配当予想は5000倍。つまり優勝は夢のまた夢のまた夢)
幾度となく「一時的な」や「奇跡的な」など簡単な言葉で勝手に片付けられてきたが、彼らは勝ち続けた。
そうしてようやく、この試合に勝てば優勝できる状況になった。
レスターの選手達は目の前の1試合1試合がすべてだった。
強豪チームはリーグ戦以外にも色々な大会があった。色々な選択肢があった。
けれど、レスターにはリーグ戦しかなかった。それが当たり前だった。
レスターと強豪の違いは何か
レスターにも強豪にも二つの選択肢しかないのではないか。
レスターは95%ぐらいは世間が思うように「負ける」チームだった。
残り5%は「たまたま」勝ったと言われて勝つ試合をしていた。
では強豪はどうだろうか?
彼らは勝って当たり前だと「世間」がいう場所。
95%は世間が思うように勝ち、残り5%はたいした敗北ではないけれど負ける。
要するに、強豪はほぼ負けない。弱小チームはほぼ負ける。
強豪が弱者に勝つと「当たり前」を生むが、
弱者が強豪に勝つと「大番狂わせ」を生む。
ここで当たり前のことだが、
強豪から弱小クラブへは、一人の決断で”自由”に行くことができる。
なぜなら彼らは、「一時的に」強豪にいたから。スキルや実力はある。
では弱小クラブはどうだろうか?彼らは自分の意志で強豪へは残念ながら行くことはできない。
あなたは強豪と弱小チームどちらを応援しますか?
そしてもう一つ
あなたはどちらの世界で生きていたいですか?
-----------------------------------------------------------------------------
敢えてひとつ、失敗だったと公言した留学生活での収穫を言うとすれば
自分のペースを作りあげたことかもしれない。
昔は、世界中の独特の環境に平然と適応する人には一目置いていた。
日本にいたら日本の環境に適応する。
アメリカにいたらアメリカの環境に適応するといったことだ。
だが、僕は自分自身に適応できると信じている。
つまり、日本に帰ったらゆっくりするなど、何か新しいことをするなどという考えは出てこない。
残念ながら、留学中に楽しかったことなどあまり覚えていないし、よくわからない。
なぜなら、「今日」が1番正しく楽しいと思っているから。
そして、ただ今日やっていることの「続き」をする「明日」が気になるからだ。
そこに曖昧さはない。
----------------------------------------------------------------------------
レスター vs マンチェスターユナイテッドの試合は結局1対1の引き分けに終わった。
結局優勝は次節に持ち越しになった。もしかしたら2位のチームが逆転優勝するかもしれない。
結論はまだ出なかった。そして、誰にもわからなかった。
試合終了と同時に食堂を後にし、図書館に向かった。
図書館の備え付けパソコンには自分以外が使いたがらないように少し工夫をしてある。
毎日同じ席に座りログインをする。周りの人から視線を浴びているようだ。何でだろうか
手ぶらで何が悪い。自分のパソコンは目の前にあるじゃないかと言わんばかりの目つきを作り
「よし、昨日の続きをしよう」
その翌日に、日本への飛行機に乗るとも知らずに「Code Complete」という本を読み始めようとした。
その数秒後、何か大切なことを忘れている感じがした。
---------------------------------------------------------------------------
後になって聞いた話だが、
食堂にパソコンが堂々と置かれていたらしい。
試合開始数十秒前の0対0が表示されている画面と共に
思わずCommand+Rを押してしまった。
-----------
以上、余語憲太でした
|
|
この記事の先頭へ戻る
◇ 2016年5月 【アメリカ・ノートルダム大学 前田陽介】日本人初!NDアメフト部でマネージャーやってみた(前編)
◇ 2016年4月 【アメリカ・ノースカロライナ州立大学シャーロット校 今井瑠美】ラスト1か月
この記事を折りたたむ
|
◇ 2016年4月 【アメリカ・ノースカロライナ州立大学シャーロット校 今井瑠美】ラスト1か月
アメリカ・ノースカロライナ州立大学シャーロット校に留学中の今井瑠美です。
10ヶ月間の留学生活も、もう残り約一ヶ月で終わりを迎えようとしています。
最近よく友達に聞かれるのは、「日本にいつ帰国するのか」「日本に帰る準備はできているか」という質問ばかりで帰国日が近いことを感じさせられます。
実際二つめの質問に答えるのは難しいです。日本の友達や家族には会いたいけれど、アメリカの気候も生活も友達も好きだなぁって。アメリカに来たばかりの頃を思い出すと懐かしいです。長いと思っていた留学生活も、もうすぐそこに終わりが見えているなんて。
まぁ、一ヶ月はあっという間と言っても結構いろんなことがありますよね笑
でもまだ帰国する実感が全く湧かないので、帰国のことはそんな深く考えなくていいかなと思っています!
最後までめいっぱい楽しみます!!

(UNCCの寮)
さて、今回は春休みのこととラクロス部のことを書こうと思います。
まず、春休み。
3月の初旬に一週間ほどの休みがあり、オーランドのディズニーランドに行ってきました!
世界一のディズニーランドということでとてもワクワクしていました。エプコットという世界各国のパビリオンと近未来がテーマになっているパーク、マジックキングダムという所謂ディズニーランド、アニマルキングダムという動物がテーマのパーク、そしてハリウッドスタジオという映画やミュージカルをテーマにしたパークの四つを三日間かけてまわりました!さすがアメリカと言わんばかりの広大な敷地面積です。

(マジックキングダム)
でも日本のディズニーランドも負けていません!マジックキングダムと東京ディズニーランドを比べると明らかに東京の方が大きいし、乗り物やお土産も凝っているように思います。
日本から見ていたアメリカは世界をリードする憧れの国というイメージでしたが、アメリカから見た日本もまた、素晴らしい国だなと実感させられることが多いです。
街は綺麗で公共交通機関が整っていて、店員さんは優しくコンビニの品揃えも豊富!笑
自分の国だからという贔屓抜きで、私はアメリカにいて日本という国の良い面にたくさん気づくことができました。
そして、私の所属するラクロス部。
今学期からコーチが来てくれるようになり、練習の質がだいぶ上がりました。とても気さくでみんなに平等に接してくださる方で、私たちはコーチのおかげで練習の雰囲気もよくなり、試合の士気もとても上がりました。
先日はEast Carolina Universityで行われたトーナメントに参加してきました。私たちのチームはまだ新しいチームで結果は振るいませんでしたが、全員にとってとてもいい経験になりました。何年後かにはこのチームがナショナルリーグに出られるような強いチームになってくれているといいなと思います。

(Senior Day)
写真はSenior Dayの日のもので、最後のホームゲームの日に今学期卒業する選手たちの卒業祝いをしました。私は卒業ではありませんが、日本に帰るからといってチームメートたちが一緒にお祝いしてくれました。留学生の私を快くチームに迎え入れてくれて、いつも優しく接してくれるみんなには本当に感謝しています。とってもいい思い出でした!
こんな遊びや課外活動のことばかり書いていますが、5月初旬には期末試験があります。日本にいる時よりも自由な時間がたくさんあるので、継続的に勉強に取り組むという良い習慣を得ているように思います。これが日本に帰っても続くといいのですが…笑
残り一ヶ月も今まで以上に濃い毎日が過ごせるように頑張ります!
|
|
この記事の先頭へ戻る
◇ 2016年4月 【アメリカ・サウスカロライナ大学 菊池直輝】大学2年生で交換留学するメリット・デメリット(前半)
この記事を折りたたむ
|
◇ 2016年4月 【アメリカ・サウスカロライナ大学 菊池直輝】大学2年生で交換留学するメリット・デメリット(前半)
こんにちは!
University of South Carolina, Darla Moore School of Business留学中の慶應義塾大学経済学部2年の菊池直輝です。
留学生活7ヶ月半が経ち、残すところあと1ヶ月となりました。
前回のブログでは取り上げませんでしたが、大学陸上部への入部が許可されなかったのち、高校生の陸上競技チームにしつこくお願いして、特別に入部を許可してもらうことができました!
そのおかげでトレーニング漬け、勉強漬けの留学生活です。


さて今回は、自分が交換留学を考えていた時期に知りたいなと思っていた、
2年生で交換留学するメリットとデメリットをまとめようと思います。
慶應で2年生から交換留学するためには(2014年の時点では)、1年生の夏にTOEFL IBTのスコアと願書を提出し、その後の二次選考で内定をもらう必要があり、早めに準備しなければなりません。加えて、出願者が多い場合、1年生よりも上級生が優先されることもあるようです。
実際に2年生から交換留学する人は少なく、留学先でも留学生の友人たちはみな3年生か4年生です。自分はまだ2年生だというと、Oh, You are a baby!と言われます笑
留学前は、学年を落とさず、且つ就職活動にも間に合うということで、2年生で留学するのがベスト!と考えていましたが、
実際に留学してみて気づいたことも含めて自分なりに、2年生で交換留学する長所と短所をまとめてみたいと思います。
まずはデメリットから書きます。
1.専門分野が決まってないうちに留学することになるかもしれない
1・2年生の間に一般教養、3・4年生で専門科目を勉強する大学が多いと思います。また、少人数のゼミ・研究会の活動は3年生以降という大学が多いのではないでしょうか。
もし自分が3年生、4年生で留学していたら、研究会やより専門的な分野の研究を通して得た知識や考え方を使って、留学先での授業に貢献できたかもしれないと感じることがあります。
例えば、今学期受講中の環境経済学は、500番台の授業で、大学院生と一緒に授業を受けます。ディスカッションや発言の際、ミクロ経済学の基礎に関しては慶應で学んだことを生かせたと実感していますが、
発展した内容の議論になると(最近では環境政策の提言など)、議論で貢献することは未だに難しいです。
その他の授業でも、何かひとつでも深く学んだ分野があれば、もっと違った形で授業にコミットできたかもしれません。
とにかく幅広く学ぶ!というのが留学の目的のひとつではありましたが、
留学先ではたくさん悔しい思いをしたし、
何よりも経済学の面白さに気づくことができたので、帰国後はもっともっと勉強します。
2.留学先で取りたい授業が履修できないかもしれない
発展系の科目になるとPre-requisiteといって、指定の科目を履修済みでないと履修が許可されない場合があります。
例えば、僕は最初の学期にIntroduction to Financeという科目の履修を希望していました。しかし、そのPre-requisiteであるFinancial Accountingの単位が未取得であるという理由で、履修が許可されませんでした。
特に2年生で留学すると、日本で取得済みの科目はどうしても少なくなるので、Pre-requisiteを満たせない可能性が大きいです。
しかし、Pre-requisiteに関しては交渉次第だと思います。後半の学期の履修のときには、教授や学生部に直接お願いして、希望の科目すべて履修させてもらうことができました。
3.出願が1年生の夏なので、準備できる期間が限られている。
TOEFLのスコア、志望動機書、留学計画書などが必要ですが、
2、3年生と比べると準備できる期間は限られます。
4.1年生で選考を受けても上級生が優先される場合がある。
僕の大学では、出願が多い場合上級生が優先されることがあるそうです。
5.留学前にたくさん授業をとることになり忙しい
学年を落とさずに留学するためには、2年生から3年生への進級条件をあらかじめ留学前に満たしておく必要があるかもしれません。
僕の場合は、マクロ経済学・ミクロ経済学・経済史のどれか一つでも欠けてしまうと、(留学先で似た科目を取得し帰国後に単位認定されない限り)進級できないという条件があったため、結構プレッシャーでした笑
また、そういった条件がなくても、留学後のことも考えて早めに必要な単位を取っておくことをお勧めします。
6.留学後に2年生の必修科目を受け直さなければいけないかもしれない
2年生で留学すると、2年生のうちに履修しなければいけない必修科目を残したまま留学することになるかもしれません。
僕は帰国後、3つの2年生の必修科目を受ける必要があり、それらの必修科目を受講するために2つのキャンパス間を移動することになります(1・2年生と3・4年生のキャンパスが異なるため)。キャンパスの移動があると異なるキャンパスの授業を連続で取ることができないので、時間割も組みにくくなります。
また、科目の性質上2年生の春に受講した科目が無効になるものがありました。(これが一番ショックでした)
留学前に履修案内などできちんと条件など確認して理解しておくことが大事です!
7.ゼミ・研究会の説明会や選考に参加できないかもしれない
留学中の3月にゼミの選考があり、僕の希望するゼミは決められた受験日に会場で直接受験しなければならなかったので、急遽飛行機を取って5日間だけ日本に帰って受験しました。
また、ゼミの説明会や模擬授業が留学中に開かれた場合、直接見て回ることができません。
僕は、先輩方に協力していただいて、興味のあるすべての研究会に所属する方々の連絡先をいただき相談にのってもらった上で決めました。
ゼミ・研究会に関しては、留学することを決めたら早めに選択肢を絞って、留学中でも受験が可能か確認するといいと思います。
8.20歳だといろいろ年齢制限にひっかかる
サウスカロライナ州でお酒が飲めるのは21歳以上なので、バーには入れませんし、部屋にお酒を置いておくことも禁止されています。
また、マイアミでは、レンタカーができるのも確か21歳以上でした。
以上、考えつく限りのデメリットをあげてみました。
次にメリットを書きますが、長くなったので次のブログで掲載します。
デメリットだけ書いたのでかなりネガティブな内容になりましたが、
2年生で留学するメリットはおおいにあるので、
是非後半のブログにも目を通していただけると幸いです。
失礼いたします。
|
|
この記事の先頭へ戻る
◇ 2016年4月 【アメリカ・ノートルダム大学 前田陽介】番外編:ウユニマチュピチュ一人旅
◇ 2016年3月 【アメリカ・ノートルダム大学 前田陽介】カッコ悪くても良いじゃないか
◇ 2016年1月 【アメリカ・ピッツバーグのアレゲニー大学 餅原圭吾】今まで一番の授業に巡り会う
この記事を折りたたむ
|
◇ 2016年1月 【アメリカ・ピッツバーグのアレゲニー大学 餅原圭吾】今まで一番の授業に巡り会う
もう既に新学期が始まってしまったのですが、秋学期に自分の人生の中で一番面白いと感じる授業に出会うことができました。以前のブログでも紹介したのですが「The third world countries」という授業です。どんな授業だったか、今回は英語で紹介しようと思います。(文法間違いはごめんなさい)

"The third world countries" was the best class that I have ever taken in my university life. It was a class of learning the situation in developing countries from perspectives of poverty, development, foreign aid, international institutions and so on. I learned basic theories about development and how to solve poverty in the class, but I could also see the real problem and the situation in developing countries, because the professor had an experience of working in developing countries before. I think this class includes attraction of liberal arts college. The distance between professor and students was really close, and I had a lot of opportunities to speak out.(I really struggled though) I'll take same professor's class in next semester!
上に書いたように、この授業は教授との距離も近く、受講生徒も少なく、リベラルアーツの良さが詰まっていて(交換留学生が偉そうなこと言えないですけど)、自分の成長に大きく繋がりました。それだけに、課題の量は半端ではなかったです。笑この授業で一番初めに発言したときは今でも忘れません。
どうしても発言したくて、やっとの思いで発言できたときは本当に嬉しかったです。
教授も嬉しそうな顔をしてくれました(笑)
それから以降も、いい感じに発言し続けることができました。この授業の教授が本当に素敵な方だったので、来期も同じ教授の授業を取る予定です!
新学期にどんな勉強をする予定かはまた次のブログで紹介します!
それでは、失礼します!
|
|
この記事の先頭へ戻る
◇ 2016年1月 【アメリカ・イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校 前田貴之】秋学期を終えてみて
この記事を折りたたむ
|
◇ 2016年1月 【アメリカ・イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校 前田貴之】秋学期を終えてみて
お久しぶりです。なかなか更新できず大変申し訳ございません。慶應義塾大学総合政策学部3年の前田貴之です。
さて、12月にイリノイ大学アーバナ・シャンペーン校での秋学期を終了しました。8月の中旬から学校が始まってみて、怒涛の4ヶ月でした。私自身あっという間に感じてしまい、グループワークでのディスカッションや課外活動で仲良くなった友人と色々話しているうちに自分を見つめなおす機会が多々ありました。
私の専攻であるスポーツマネジメントの授業で日本のスポーツの強みを紹介するときに、相撲や最近のラグビーの躍進など日本のスポーツマネジメントを紹介し、私以外全員アメリカ人(スポーツマネジメントメジャーor 体育会の学生ばかり)を前にディスカッションしたところ、2020年の東京オリンピックまでにアメリカ人から見た視点が色々と私にとって印象的でした。
日本大好きなアメリカ人の学生の意見として、「日本は少子高齢化が進むけど高齢者は何かオリンピックに何か活かすの?」これは私にとって予想外な質問でその質問に対して上手い答えが出せませんでした。
イリノイ大学はアジア人の中でも日本人は少なく、中国、韓国、台湾人が圧倒的に多い事でも有名な学校で、日本の知名度は低い事がわかります。私自身、交換留学をアプライする際に田舎の学校を限定して出願しました。
そもそも私はずっと0~3歳までアメリカ(ニューヨーク)で住み、4歳~現在まで東京に住んでいた為アメリカの田舎のキャンパスに憧れていたのでそこで私は田舎の学校でかつ、スポーツマネジメントを学べる学校を選択しました。(都会がいいのか、田舎がいいのかは最終的にはみなさんの好みです)
こうして合計5つの授業を終え、怒涛の課題やテストを終え、無事単位も取得し、冬休みはイリノイ大学に通っている友人とカナダやアメリカの大学に交換留学をしている友達とメキシコシティー→キューバ(ハバナ)→カンクン(メキシコ)に行ってきました。
日本から旅行していくと距離もある分、更に旅費も更にかかります。当初アメリカ人の友人や他国からの交換留学生の友人を旅行に誘ったところ、皆自分の国に帰省や、地元(シカゴ)に帰らなきゃいけないと言われてしまい、結局日本で同じ大学で交換留学をしている友達と旅行をしてきました。
メキシコは物価が安く、特にホテル近辺のレストランに行かなければ屋台などで大きいメキシカン料理を頼んでも200~300円で食べる事が出来ます。そして、驚いたのがキューバはお金が二種類あり、人民ペソと兌換ペソがあって私たちは主に兌換ペソを使わなければなりません。人民ペソと比較して非常にお金がかかります。
社会主義国恐るべしです。でもキューバは日本と比較して貧困層が多かったり、街が汚いなど多々ありますが、キューバ人の人柄に感動しました。キューバに滞在中、民宿(カサ)に滞在しホームステイ先のおばさんには優しくしてもらい、中南米の旅行で初めて旅行してキューバは好きになりました。スポーツだと野球が国技なので、スポーツが好きなキューバ人は日本人と伝えると野球、野球!って声をかけてくる人もいます。
 
(メキシコシティー ティオティワカン遺跡) (ハバナのダウンタウン)

(カンクンのビーチ)
イリノイの寒さとは逆に、Tシャツ、短パン、サンダルで過ごせて過ごしやすい冬休みでした。数日前にイリノイのシャンペーンに戻ってきて、気温マイナスが続いてもう冬が怖いです。後期の履修もほぼ決まり、19日から大学が始まりますが気を引き締めて勉学や課外活動に励んで悔いのない留学生活を送りたいと思います。
最後に
留学の過ごし方は人それぞれです。パーティーばかりのイベントに参加する人、自分の専攻の勉強に集中する人、課外活動頑張る人など楽しみ方は色々あります。なので、一日一日無駄にせず、私の場合は友人とかにイベントに誘われたら基本的に断らず全部行こうって自分の中で決めています。
実際にそこで自分の同じ専攻の人と出会ったり、そこで今でも仲良くなったりと不思議な出会いが多々あるものです。
留学をして自分は留学先の学校で何をしたいのか、よく考えるのも重要だと思います。
|
|
この記事の先頭へ戻る
◇ 2016年1月 【アメリカ・ノースカロライナ州立大学シャーロット校 今井瑠美】2016年!!
◇ 2015年12月 【アメリカ・ノースイースタン大学 前期振り返り 余語憲太】
この記事を折りたたむ
|
◇ 2015年12月 【アメリカ・ノースイースタン大学 前期振り返り 余語憲太】
お久しぶりです。
留学の半分が終了しました。今は落ち着いているので少々長い文章をこの4ヶ月の振り返りも兼ねて執筆しました。振り返りに移る前に、今年の冬は以前から計画していた通り、初めてのヨーロッパに1人滞在することにしています。2つ理由があり、日本に帰る飛行機の値段とヨーロッパへの値段が一緒だからという理由と、今まであった(ここ1,2年)で会った友人を訪ねようという理由です。
アゴス, YFJで出会った友人に会いにイギリスに、大学の先輩に会いにスペインへ。現ルームメイト・大学1年次に仲良くなったフランス人に会いにフランスへ。そして、カナダのプログラムで同じチームにいた28歳のドイツ人に会いにドイツへ。
というのも単に観光ということではなく、自分にとって1回会った友人と2回目に会うまでの数ヶ月、ないし1年が非常に重要な期間だと思っているからです。
その期間で自分がどう変化したかなど、自分で気づかないところを指摘してくれる友人に出会えたことは人生の財産だと思います。感受性が豊かな時に、初めて訪れる国々の季節感、風景、空気を自分の肌で感じてみたいなと思っています。
さて、この4ヶ月間としっかり向き合ってみようと思います。
1. 前期受講授業
a. Global Social Enterprises
b. Principles of Organizational Communication
(German 1 + First Year Writing)
2. 「Global Social Enterprises」での出来事
3. 来期受講授業の予定
1、前期受講授業
今学期は4つの授業を履修しました。
Global Social Enterprises, Principles of Organizational Communication, German 1, First Year Writing
確実に大学で単位換算ができ、かつ、専攻の経営学の理論、実践的な会社の経営事情に焦点を当て科目を選択しました。すべての授業で学術的なこと以外に非常に多くのことを学んだのですが、特にGlobal Social Enterprisesのクラスが1番印象に残るものだったため、掘り下げて説明したいと思います。その前に他3つの授業を簡単に、
a. Global Social Enterprises
世界中の社会問題の解決、また人々のニーズを満たすための活動を最重要課題とする社会的企業を様々な指針を基に分析・評価していく授業です。世界各国にある社会的企業の中で100社程度を1学期間で分野別、且つ評価基準別に査定していきました。分野別というのは、水・電気・小売業・医療・教育・マイクロファイナンスなどのことで、評価基準別というのは財政上の持続性・透明性・ビジネスモデル・影響力・規模・創設者の当事者意識などのことです。
このクラスでは、5つ以上の社会的起業の企業研究をする理由からオンライン資料がアップデートされ、毎回の授業の前に各自で定めた評価基準や要素を基に順位付けし、エクセルで資料を簡素化することが求められていました。また、1ヶ月に1冊(約400ページ)ほどの本を読破し、提出1週間前に発表される問題に答える形で7~9枚程度のペーパー(約2000 words)を提出しなければならないこと。
プレゼンのためのグループミーティング、パートナーと分割して15枚(約4000 words)ほどのペーパーを書いて提出するなどを同時並行ですることが求められました。他の留学生には簡単にできてしまうようなことでも、自分にとっては苦難を強いられました。時には、午前4時頃まで図書館に籠り、コンピューターとにらめっこをするわけですが、自分と同様ににらめっこしてるアメリカ人らしき人物が隣にいるわけです。
(アメリカ人でもこれだけ苦労してるんだから当たり前!と敢えて彼に理由を聞かずに続けるわけです)この環境だと「何としてでも彼より早く寮に帰ってやる」というどうでもいい動機で作業してる自分に気づき惨めな気持ちになることが多々あるのですが、、、笑
成績の話にいきましょう。
9月、初めての課題で、このように勉強をしてB+。
10月、この箇所を勘違いしてたのか、今度こそと望むもB+。
11月、教授、どこが悪かったのですか?なるほどそこなんですね。B+
12月、なんでA-が来ないんですか教授!TA!なるほど。B+
ファイナルプレゼンテーションB+ 共同ペーパーB+
クラスの友達A、隣の人A-、自分......
結局、クラスへの貢献度や出席点、クラス内に実施されたテスト以外で
1度もA-ですら頂けませんでした。
a. Principles of Organizational Communication
組織(会社、団体)で活動する人々にとって、どのような組織構造や理念の元に日々の任務を遂行しているかということを明らかにしていくために、理論や概念を理解していくという授業でした。
日本では、会社・団体の組織構造を調べ、構造ごとの利点や弱点を理論的に分析することを学んでいたのですが、この授業では教授がアメリカの典型的な大企業や近年できたスタートアップ会社までを複数取り上げ、それぞれ会社の組織体制がどの理論や概念に当てはまるかということを学習していました。
理論的な話がほとんどなので教材は重く固苦しく、一学期を通して一冊読破する計画に沿って毎授業40ページほどの予習がありました。
またそれ以外に、5セット1000字程度のペーパー(与えられた抽象的な問題に対する自分の考えを授業で学んだ内容を含めながら論理的・具体的に書くことが要求される宿題)。
さらに、ここ最近の時事問題や環境問題に対する企業や団体の取り組みを概念と絡めて説明する1時間強の質問型プレゼン(クラスに問題提起をし、意見を聞きながら自分たちで考えた結論に誘導していくプレゼン)。
授業中はほとんど教授は資料を使わず、会話形式に理論や概念を説明していくスタイルから、7人程度のグループをその場で作り、そこで予習した内容を元に即興でプレゼンをグループでするというものでした。総括すると、非常に厳しい時間を過ごしました。この授業の難しいところは授業の大半がアメリカ人で留学生が自分含めて3人し かいなかったこと(初回の授業で10人程度がドロップアウトしていました)、しかも残りの2人はアメリカの高校を出たという学生から、圧倒的に厳しい環境でありました。
さらに、参加点(20%)はクラスの学生によって決められるということで、意見を述べるだけではなく、印象に残る、また何か他の人の考え方に影響を与えるような内容の発言をしなければ誰も自分の名前を書いてくれないという事態が生じてしまうのではないかと常にアンテナを張って1番前のど真ん中の席で毎回授業を受けていたことを覚えています。
German 1, First-Year Writing この2つの授業にも「教授と授業中に口喧嘩をする」「優先順位1,子供 2,妻 3,博士の論文4, バンド 5, 学生のペーパーの評価 6, オフィスアワー(教授と1対1で会話ができる機会)という教授との戦い」などなどストーリーは山ほど記憶していますが、省略。
2、「Global Social Enterprises」での出来事
中間を折り返したら、恒例の「今まで学んだ内容全てを考慮して」の出番、クラスでは今まで学んだ社会的企業とアメリカでは普通の企業を授業中に平然と言われあたふた。スペルはわからないけれど、ノートの右端にカタカナで聞こえた通りに書いて、授業終了と同時にTAに聞く。時に隣の人にこれなんて言ってたのかと。
時に、堂々とTAの前で授業を録音した音声を再生してどういうことですか?なんて言ってるんですか?と聞く。そうこうしてるうちに予習があり、人付き合いもあり。生活リズムが酷くなりました。
食欲がわかず、運動をせず、コミュニケーションを取らずと。大学1年の春休みに体調を壊し、いろいろな人に多大な迷惑をかけ挫折したこともあっただけに、体調だけは崩さないようにとやっているのですが、寝たらクラスに置いていかれる。けど寝ないと体調を崩す可能性が高まるというジレンマと戦いつつ、常になんとかしていました。
10月下旬、図書館に籠った後に2日連続で宿泊しそうになった際、寮からわざわざ親しかったアメリカ人の友人が顔色を変えて自分のところにやってきました。彼も勉強しに来たのかと思いきや、「お前は自分の体調を考えなさすぎる。今は大丈夫でも絶対崩すぞ。お前の留学は間違ってる。荷物しまって寮に今すぐ帰れ。」反撃に「帰ったら自分が自分に満足できない。明日の授業で発言も内容も入ってこない。」「お前は悪くない、留学生を支援しないこの大学が悪いから、今すぐ日本語と英語が話せるやつを紹介するから力を借りろ」「俺はこの生活がしたくて日本からお金をかけてきた。」「その生活は間違ってる。お前の留学は間違っている。」「・・・・・・」
と夜中3時スネル図書館3階、普段は話すことが禁じられている空間で罵声が飛んでいた。結局、彼は怒ったまんま帰り、自分は残った。
そこから、自分は何のためにここまでしてるのか?果たしてこの生活は間違っているのか?このような生活を繰り返すことが自分のためになるのか?と、もう一度深く考えることができ、彼とは今では連絡を頻繁に取る仲となりました。
以前、読んでいたブログで
「果たして時間がないのか、あるいはどこかで時間を浪費しているのか」という問いに対して詳しく述べており、直接彼から話を聞いたことがあります。その時はあまり気づかなかったけれど、自分の持っている1日24時間の使い方から考え直す必要性が留学生活には必要なのではないかということに気づきました。
どれだけ日本では普通にやっていれば1日が回っていたのか、果たして日本で勉学や課外活動をしていた際にどれだけ計画を立てることが容易だったかということを改めて感じました。
この出来事以降、自分の24時間の使い方から考え改めることができ、1つ1つ歯車が噛み合っていきました。
それから月日が経って12月中旬、15分のグループプレゼンで大切な箇所を飛ばし、学生の質問に頷かせるような回答ができず、チームメイトに多大なる迷惑をかけ40人の学生の前で唇を噛むという経験をしました。授業終了後、即座に寮に帰り、床に倒れこんでいる自分に自分が気づいたことは今でも印象的です。「Global Social Enterprises」このクラスにはドラマしかないと思っています。
9月始めに教授、TA(Teaching Assistantの略=授業中に理解できなかった箇所などを時間をとって個別に説明してくれる学生)しか信じられなくなり、そこから少しずつ考えてきたのだけれど、結局最後まで納得のいかない形で終わりました。Dennis shaughnessy教授との出会いからこれだけの経験ができるとは夢にも思わなかったです。
ちなみに彼と人生についての話をしていた際に、「One’s path in life is the result of the many experiences」ということを強調して言っていました。ありきたりなことだけれど、間違いないなと言うのが率直な感想です。終わってしまったのはしょうがないけれども、幸運な事に来学期彼が新しく授業を開講するらしいので、もちろんリベンジしに履修します。(正直なことを言うと、社会的企業の分析などをする授業内容や授業スタイルにどハマりしました。)
3、来期受講授業の予定
授業の題名と取るきっかけだけ簡単に紹介します。内容は開始次第書いていこうと思っています。
(もちろん最初の週で変える可能性は十分にありますが、)
1, Experiential Entrepreneurship
2, Social Responsibility of Business in an Age of Inequality
・ Dennis shaughnessy 教授の授業
3, International Business and Global Social Responsibility
・ この授業を開講しているLuis Dau 教授とは留学の書類を提出前の段階(2014年9月)からメールで連絡を取っていました。
8月にカナダへ初めて留学していた時に、たまたま受講していた授業の教授が以前にボストンに住んでいたという理由から、大学で現在所属しているD’Amore-McKim School of Businessの教授を数名紹介していただきました。
その際に、授業を取るにあたり日本でできる最大限の準備として何冊か本を推薦していただき読んでいました。正直、今の段階でほとんど内容は頭に残っていませんが、当時、その内容から展開される授業に非常に興味を持っていた事を覚えています。記憶が正しければ、留学計画書に彼の名前と受ける授業を細かく書いていたと思います。
今回は9月~12月に経験したことのごく一部を紹介しました。言葉で説明することが難しいことをなんとか言語化したせいか、伝わりにくい箇所があると思います。
しかしながら、交換留学生の一人として「リアル」で「正直」な体験として執筆させていただきました。
今後、留学を考える高校生や大学生の方で、あまり海外経験が豊富ではないという方には是非読んで頂きたい内容です。
次回は、来学期のクラスの内容や春休みについて執筆していきたいと思っています。
|





|
この記事の先頭へ戻る
◇ 2015年12月 【アメリカ・ノートルダム大学 秋学期振り返り・後編 前田陽介】Play Like a Champion Today
◇ 2015年12月 【アメリカ・ノートルダム大学 秋学期振り返り・前編 前田陽介】「没頭する」とは何か
◇ 2015年11月 【アメリカ・サウスカロライナ大学ダーラムアスクールオブビジネス 菊池直輝】今学期の授業を通して感じたこと
この記事を折りたたむ
|
◇ 2015年11月 【アメリカ・サウスカロライナ大学ダーラムアスクールオブビジネス 菊池直輝】今学期の授業を通して感じたこと
こんにちは!
University of South Carolina Darla Moore School of Businessに留学中の慶應義塾大学経済学部2年の菊池直輝です。
アメリカに来てから3ヶ月半が経ちました。
早いものでもう12月になりますが、12月1日のサウスカロライナの最高気温は23度。師走とは思えないほど穏やかな気候でとても心地が良いです。まだサンダルで過ごせます!

PaperやMid-termも一息ついて授業はあと一週間を残すのみとなり、最近は今学期を振り返ってみたり、来学期や帰国後の予定を考えてみたりしています。
そこで今回は、今学期を振り返って、特に授業を通して感じたことを書いてみたいと思います。
今学期受講したのはマネジメント、マーケティング、管理会計といったビジネス科目であるのに対し、慶應での専攻は経済学であるという学問の性質上の問題かもしれませんが、
こちらの授業は慶應のものと比べてより実践的で、将来ビジネスの場で直接役立つような内容が多かった印象があります。アメリカでは就職活動で専攻が重視されると言われる所以がわかったような気がします。
同時に、今学期アメリカで履修した科目は、慶應での授業と比べるとアカデミックさに欠けるのではないかと感じています。今学期の授業を通して、組織におけるリーダーシップの成功例、企業におけるマーケティング戦略、節税対策など…、確かに実践的なアメリカのビジネスを学ぶのはとても興味深かったです。
しかし、帰国後はもっと学生のうちだからこそ学べる「理論」を勉強したいと考えるようになりました。
幸い帰国後は三田キャンパスで経済学をより専門的に学べる環境が待っています。日吉キャンパスで取り残した必修科目たちも待っていますが笑(2年生の途中から留学したので取りこぼしがあるんです…)

ともかく、僕の留学の目的のひとつである「留学先で幅広くビジネス科目を受講し、帰国後より深く学びたいことを決めていく」ことは何となく達成できてきたのかなと感じます。
来学期は全米No.1と言われているInternational Businessの授業をはじめ、もっとChallengingな科目を受講していく予定なので、自分がそこから何を学び、どう考え方が変わっていくのか楽しみです。そしてまたこのブログで報告したいと思います。
以上、今学期の授業を通して感じたことを簡単に書かせていただきました。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
何かの参考になれば幸いです。
それでは失礼いたします!!
|
|
この記事の先頭へ戻る
◇ 2015年11月 【アメリカ・ピッツバーグのアレゲニー大学 餅原圭吾】ボストンキャリアフォーラム
この記事を折りたたむ
|
◇ 2015年11月 【アメリカ・ピッツバーグのアレゲニー大学 餅原圭吾】ボストンキャリアフォーラム
こちらに来てから2ヶ月が経ちましたが、前回ブログ書いた時と違って苦労していることが1つあります。
それは「ボストンキャリアフォーラム」です。
僕は留学が決定してからこのイベントを知ったのですが、ボストンキャリアフォーラム(通称ボスキャリ)はバイリンガルを対象とした就活イベントで、毎年多くの留学生が一同にしてボストンに集まるのです。
なんでも「3日間で内定も決まる可能性あり!」と、逆に不安になってしまうぐらいのイベントなのですが、就活を早い時期から経験した方がいいだろうという判断から、今年はボスキャリに参加します。
ちなみにあと2週間後(笑)
この準備が非常に大変なんです。各企業に対して志望理由を書いたり、履歴書を作成したり、
「SPI(学力測定テスト)の勉強したり」
何でアメリカ来てまで、国語とか数学の勉強しないといけないんだろうって率直に思います笑
でも、やるしかないですね!2週間後のボスキャリに向けて、突っ走ります!
 
P.S.)ハロウィーンはキリンの仮装をしました。いろんなハウスパーティーに参加して、皆が笑ってくれました笑
ハロウィーン関係ないけど、とりあえず目立ちたかったんです(笑)
|
|
この記事の先頭へ戻る
◇ 2015年10月 【アメリカ・イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校 前田貴之】
◇ 2015年10月 【アメリカ・ピッツバーグのアレゲニー大学 餅原圭吾】
この記事を折りたたむ
|
◇ 2015年10月 【アメリカ・ピッツバーグのアレゲニー大学 餅原圭吾】
はじめまして。
慶應義塾大学3年の餅原圭吾と申します。
現在はアメリカはピッツバーグのアレゲニー大学(日本で知ってる人ほぼいない
w)という場所に交換留学生として滞在しています。
今回は簡単に近況と、交換留学を目指すにあたっての内容を書きたいと思います。
それでは近況ですが、
「基本的に勉強以外することがありません笑」
話には聞いていたので想像はしていたのですが、アレゲニー大学は本当にど田舎
にあって、周りに何もありません。その代わりに、各授業から出される 課題が
大量にあります笑笑
元々田舎育ちの僕は、この環境に慣れているのでとても満足しているのですが、
勉強に関しては本当に苦労しています。というのも、今まで長い海外滞 在経験
がなかったので、英語の本を読むのにもどうしても時間がかかってしまうからです。
それでも、授業自体はとても面白いです。
お気に入りの授業は「The third world politics」という授業で、アフリカや東
南アジアの貧困をどう解決するか、どのような視点で見れるのか、というような
内容を学ぶものです。リベラル アーツカレッジというだけあって、生徒の数は
15人ほどで、教授との距離が近いです。ただ、この授業では発言を強く求めら
れます。私自身、日本の 大学では積極的に発言する方だったのですが、どうし
ても初めは英語で発言することに苦手意識を感じてしまいました。それでも、3
回目ぐらいの授業 の時に、思い切って発言してみたら、教授が驚いてくれて、
すごい喜んでくれました。それからは、1回の授業に1回発言を目標にしています。
私が交換留学を本格的に目指し始めたのは、1年生の10月頃からです。
今回、同じくブログを書いている前田君にAGOSを紹介してもらい、準備を始めま
した。
他の人も書いていましたが、
「とにかく早く準備するべき」
というのはその通りだと思います。私の場合、出願までに約1年あったわけです
が、その期間を全てトフルに使えたわけではありませんでした。という のも、
トフルの点数が上がり始めた冬に、第二外国語の韓国語の研修で1ヶ月英語から
離れてしまった時期があったからです。結果的にトフルの点数が 下がってしま
い、非常に焦った覚えがあります。
なので、いついつまでに何点を取れれば大丈夫というように考えるよりかは、少
しでも早く高得点を取れるように考えるべきだと思います。予定という のは、
上手くいかないものなので。
第1回目はこの辺で。
ブログを書くのは好きなので、今後も積極的に投稿していきたいと思います。
それでは!勉強頑張ります
|



|
この記事の先頭へ戻る
◇ 2015年10月 【アメリカ・ライス大学 小松夏実】
◇ 2015年9月 【アメリカ・ノースイースタン大学 余語憲太】
◇ 2015年9月 【アメリカ・サウスカロライナ大学ダーラムアスクールオブビジネス 菊池直輝】
◇ 2015年9月 【アメリカ・ノースカロライナ州立大学シャーロット校 今井瑠美】はじめまして(^^)
この記事を折りたたむ
|
◇ 2015年9月 【アメリカ・ノースカロライナ州立大学シャーロット校 今井瑠美】はじめまして(^^)
皆さんはじめまして!
学習院大学法学部政治学科2年の今井瑠美と申します。
私はこの8月から、アメリカのノースカロライナ州にあります、ノースカロライナ州立大学シャーロット校に約10ヶ月間の交換留学に来ています!
この度、AGOSの2015年出発の交換留学生と共に、このブログを約一年間にわたり執筆させて頂くこととなりました。さまざまな大学に留学に来ている学生たちの生の声が聞けると思うので、更新を楽しみにして頂ければと思います。
○自己紹介
まず、最初のブログですので簡単な自己紹介と留学に至った経緯を話したいと思います!
私は小学校から学習院の付属校に通っており、海外留学経験も高校2年生の時に行った2週間のイギリスでのサマープログラムだけなので、今まで外の世界をほとんど知らずに安全地帯で生きてきてしまいました笑
そんな私は高校の時に同年代とは思えないほど社会貢献への意識が高く、幼いころから英語に触れて世界的な視野を持っている高校生たちに出会い、自分の考えの未熟さや英語を操れない怖さを知りました。そこで、最後の学生期間である大学生活では絶対に留学を経験しようと思い大学1年の春から本格的に留学準備を始めました。AGOSではIELTSの講座を受講していて、IELTSのスコア取得までのサポートに限らず、出願書類の添削などでも大変お世話になりました。
○ノースカロライナ州立大学シャーロット校について
この大学を知らない方がほとんどではないでしょうか。1946年創立の比較的新しい大学で、光電子工学、精密工学、情報技術の応用研究分野が強い大学と言われており、ダウンタウンからは少し離れたところにあるため広大な敷地と緑に囲まれて周囲には何もないです(;_;)
とにかく敷地が広くキャンパス内にはなんでも揃っています。しかし、一度キャンパスを出るとなると公共交通機関が発達していないので、車がないとどこに行くにも不便です。
統計的には白人学生がほとんどを占めるとありますが、南部ということもあってか黒人学生、ヒスパニックの学生も多く見られます。人種差別も激しいと聞きますが、キャンパス内では黒人だからアジア人だからといって差別をされる光景は未だ経験していません。アメリカ人は日本人と比べて誰に対してもフレンドリーで新入りに対してあたたかいと思います。少なくとも私はそのような友達に恵まれているのでありがたいです。
留学生に関しては日本人学生が予想以上に多いこと、そしてインド人学生が圧倒数を占めることに驚きました。
○留学生活の所感
とにかく初めてのアメリカ、初めての寮生活ということで最初の数日間は食料も何もなく英語も聞き取れず話せずで、虚無感にかられることもありました。しかし、2週間ほどして生活にも慣れてきて、今は毎日を無駄にしないように生きるのに必死です笑
海外留学を経て英語を道具として使えるようになることと、自分の学びたい都市計画の分野を受講すること、世界の先頭をいくアメリカという国の文化、人々、街並を肌で感じたいという考えがありました。しかし、残念ながら今学期では都市計画の授業は定員漏れにより受講することができませんでした。その代わり、今学期はアメリカ政治、比較政治、中国語を受講しています。
たしかに、こちらでの生活は今まで安心安全なコミュニティで生きてきた分、言語の壁をはじめ日本が恋しくなることもあります。しかし、まだこちらに来て一ヶ月も経っていませんが、留学にて経験したいと日本で思っていたことよりもはるかに多くのことを経験し、考えることができています。例えば、人種間での職業の違い、日本人の友達にはいないようなアメリカ人のラフな性格、留学生の中で特に英語が話せないことが目立つ日本人などなどです。日本では小学生から英語教育がされているのに、なぜこんなに英語を使えない人が多いのだろうと日本の英語教育に憤りすら感じます。笑
それから、先進国の中でアメリカ人ほど他の世界を知らない人種はいないのではないかとも思いました。 アメリカにいれば欲しいものはなんでも揃うし、山にも海にも行けるし、四季も感じることができる。海外からの移民も多いので、“異文化交流”もできる。ほとんどのアメリカ人たちはアジアのことなんて気にかけることもなく日々を過ごしているのだろうな、などと考えました。
まだ始まったばかりの留学生活ですが、予想以上に毎日さまざまなことを考えさせられています。
それと、早い英語を聞き取りネイティブたちの会話に入っていくことはとても大変です。
沢山英語に触れて早く話せるようになりたいです!
言語の壁、文化の違いがあるばかりに日本人、アメリカ人といった国民的アイデンティティーについとらわれてしまいがちですが、このような環境にいるからこそ、一人の人間として自分に関わってくれる人を大切に、その人と大切な時間が過ごせるようにすることを忘れないでいたいです(^^)
それでは、次回のブログも楽しみにしていてください!
|



|
この記事の先頭へ戻る
◇ 2015年8月 【アメリカ・ノートルダム大学 前田陽介】初めまして!