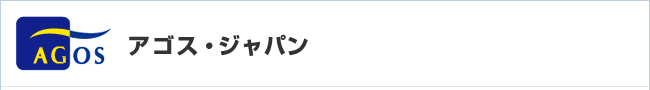◇ 番外編 近況報告と、Kindleへの移行について!
この記事を折りたたむ
|
◇ 番外編 近況報告と、Kindleへの移行について!
みなさんお久しぶりです!ブログが完結してからもう半年経ちました。みなさんはいかがお過ごしでしょうか?
ハチャメチャな大学時代を送ったと思ってきた自分でしたが、ここ半年間は大学時代以上に波乱万丈でした(笑)。以下がここ半年間に起きたことです。
●2016年11月号の記事に書いていた通り、最初の職場に選んだのは日系の総合商社でした。昨年の記事にある通り、元々はこの会社へ入ることにすごくワクワクしていたのですが、非常に日本的かつ上下関係が強い文化が自分に合わず、3ヶ月で退職しました。
●総合商社に勤めていたのは今年の7月から9月のみ。その間に転職活動を進めていました。自分は決してエンジニアではないですが、2017年2月号の記事に書いた通り、テクノロジー業界に憧れを抱いていました。そのため、大学時代に見た企業以外では、テック系を中心に見ていました。これは日系総合商社の文化とは正反対の場所を求める深層心理があった気もします。
●その中でも、環境・インフラ分野において世界的に大きな変革をもたらしているスタートアップからオファーを頂き、10月から働き始めました。
●今はこの会社に、以下の理由で惚れ込んでいます。
・日系企業はもとより、新卒の友人が入社している外資系企業らを遥かに上回る職場環境を備えていること(カリフォルニア発のテック企業は、ほんとココが素晴らしいです)。
・さすが急成長している会社だと言うべきか、徹底的にデータを用いるなどビジネスのやり方が本当に合理的で、日系総合商社と違い、会社にいる事で多くの勉強ができること。
・日本法人は未だ小さな組織で、一人一人に大きな裁量があること。
最初に入った職場が余りにも自分に合わなかったのは残念でしたけど、その後の短い転職活動で、現状で間違いなく最善の選択を出来たのは、今の自分の誇りです。実際はこの記事でもウチの企業を全力でプロモーションしたい所ですけど(笑)、最近メディアに取り上げられる事が多く社会へ発信するイメージに凄く敏感な会社なので、ちょっと名前は控えさせて頂きます(笑)。ご興味のある方は個別に聞いて下さい。
さてそんなハチャメチャな半年でしたが、もう一つ大きな報告があります。前職の日系総合商社を辞めて現在の会社に移るまで、前職の有給休暇を消化していたため、暫く間がありました。その間にふと思い立ち、無秩序に物事を書き付けてきたこのブログを改訂する意味、そして(働くことに対する意見など笑)ブログを書いていた頃と今で考えの変化があった事を書き付けておく意味を込めて、アマゾンのKindle(電子書籍出版プラットフォーム)で簡単な電子書籍を出版しました!以下のリンクからどうぞ。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0773V7JTR
一冊はたったの30分もあれば読み切れるほどの長さですが、シリーズものにしようと思っており、第5弾くらいまでは続けようと考えております。さらにKindleでは、アメリカの大学に関する話に留めず、ゆくゆくは仕事、外資系企業と日系企業の違い、カリフォルニア発テック企業の文化など、社会人としての新たな発見についても話を広げて行こうと思ってます。前のブログ記事で社会人になってからもブログを続けると書きましたけど、Kindleがまさしくそのプラットフォームとなりそうです。今後はKindleを、どうぞよろしくお願いします!
|
|
この記事の先頭へ戻る
◇ 2017年6月 留学論
◇ 2017年5月 卒業論文と、大学論
◇ 2017年4月 BSAJと、教育論
この記事を折りたたむ
|
◇ 2017年4月 BSAJと、教育論
様々な人に学校教育の話を聞くと、皆、様々な意見を持っています。それもそのはず。義務教育が普及している日本のような先進国において、学校教育というのは、全ての人が経験する道。政治哲学のような己の身から離れたトピックではなく、己の経験と実感に基づいて多くを語れるのが、学校教育。自分自身も、2015年10月号を始めとした様々な記事で、学校教育を取り上げてきました。さらに昨年春から、教育にまつわる新しい法人、BSAJ(Boarding Schools Alumni of Japan)(http://bsaj.jp/)を立ち上げさせて頂き、現在に至るまで代表を務めています。学校教育というのは、自分自身も多様な経験をしてきたため、常に関心を持っています。
大学生活を終えようとしている自分が、今、ここにいます。大学院に行く事は検討していますが、大学院では研究をするわけで、教育という場に身を置くのはこれが人生で最後になるはず。自分にとっての教育とは何だったのか、今、振り返る時期にあります。アゴスで書くブログ記事だって、あと3回分。今回の記事は、4年間の海外大学生活を総括する記事の、第一章にしたいと思います。
1. 一度きりの学校教育
1-1. 教育価値観の再生産
1-2. 他の価値観との出会い
1-3. 自分の経験を振り返って
2. 今までの経歴と、それから見えてくるもの
2-1. 幸福度と成長度
2-2. 青年教育の経験から
3. 教育の質
3-1. 青年時代の欲求
3-2. レールを敷くという行為
3-3. 二つの欲求が満たされる学校教育
3-4. 二つの欲求が満たされない学校教育
3-5. お金について
4. ボーディングスクールとBSAJ
4-1. ボーディングスクールとは?
4-2. 教育の質という世界の頂点
4-3. 社会階層の違い
4-4. BSAJ
1. 一度きりの学校教育
学校教育と言っても、その道は多様です。公立や私立、文系や理系、教育と言っても道は本当に多様。反対に、人生を経験するのは一度きり。人々は、人生のある期間において、ある一つの学校に通う事しかできません。また、文系を選んだ人が理系も選ぶケースはありませんし、国立大学に進学した人が私大にも同時に進学するケースはありません。
先月述べた教育心理学の研究に関わっていて思うのは、大部分の人が、自分が一回きりしか経験していない教育バックグラウンドに対して、何かしら後悔をしていない限り、なんだかんだポジティブな印象を持っているということ。多くの人は、人生で一つの小学校、一つの中高、一つの大学にしか通わないですし、他の学校と経験を通じて比較する事はできません。言い方が悪いですが、日本以外の国を全く知らなかったら、日本が世界で最高の国だと考えるのと同じこと。結果、自分の教育経験に悔いがない限り、多くの人は自分の教育経験が良かったのではないかと捉えていますし、その教育スタイルが本人の中でのデフォルト設定になっています。
1-1. 教育価値観の再生産
一見して自分の専門分野から離れているこの研究。2年生の秋、ブラウン日本クラブ(Japanese Cultural Association)のメーリスでリこのような状況で起きるのが、教育価値観の再生産。色々な人に、「子どもにあなたが通っていた学校に入れたいですか?」という質問をすると、母校に対して特別に悪い印象でも持っていない限り、多くの人が、「なんだかんだ楽しかったので、ぜひ」と答える気がします。学校単位ではなく、学校の種別に話を広げると、もっと分かりやすいはず。例えば、ずっと公立の学校に通って親になった人がいたとしたら、子どもに対しても、学校は公立の学校に通わせるのがデフォルト設定。反対に、中高が私立の中高一貫校であった人であれば、子どもを私立の中高一貫校に入れようとする。公立に通った人は私立を経験していないですし、私立の中高一貫校に通った人は、公立の中高を経験していません。公立と私立のどちらがいいという話ではなく、こういった現象は必然的に起きるのだと思います。
この話は、教育期待にも関わってきます。先月号で述べた研究の対象には、両親が大卒ではない家庭が半分含まれます。両親が大卒でない家庭には、後悔をしていない限りは、子どもに大学進学を求めないお母さんが多い。己の道さえ見つけてくれれば大学に行く必要なんてないと、多くのお母さんが言います。反対に両親が大卒の家庭においては、大学進学を望んでいるお母さんが多い。大学進学と就職、どちらが正しいなんて決められません。自分の経験と照らし合わせて、どちらがデフォルトの価値観になっているかの違いでしかありません。以上のような価値観の再生産は、ジェンダーに関する価値観など、様々なものに当てはまると思います。
1-2. 他の価値観との出会い
再生産が行われないケースは、自分が経験したもの以外の学校教育について知ったとき。それこそ、大学での友達関係は、いい例です。東大のような大学には、公立高校から来た人もいれば、私立中高一貫校から来た人もいます。ブラウン大学でも同様です。公立高校(Public School)出身の学生がいれば、私立高校(Private School)出身の学生もいて、ボーディングスクール出身の学生もいれば、インターナショナルスクール出身の学生もいます。自分のいるコミュニティ・社会から飛び出し、他のコミュティ・社会を知って、そこに所属する人と何かしらのプラットフォームで交流した時、初めて自分が経験したもの以外の学校教育について知ります。2015年10月号の文脈を借りれば、自分が所属する社会階層を飛び越えた時に、初めて見えてくるものがあるということ。その際には、「自分は通えなかったけど、子どもが出来たらボーディングスクールに入れたい!」など、教育価値観が変化する可能性もあるでしょう。自分もこのような価値観の変化を味わった人の一人です。
「知らないって怖い」なんて表現を頻繁に用いますが、同時に「知らぬが仏」なんていうことわざもあります。知る事が幸せなのか不幸なのかは分かりませんが、少なくとも、視野を広げて考える事はできます。
1-3. 自分の経験を振り返って
様々な人が様々な意見を持っている学校教育ですが、一度きりしか経験できない性質上、学校教育に関する視野は狭まりがち。そのような学校教育において、僕は特殊な経験をしました。父親が転勤族であった事や、留学経験を繰り返した事で、普通の人には経験しえない数の学校に通いました。幼稚園ですら転校しましたし、小学校は最初の一学期だけ通ったのちに、父の仕事でノルウェーへ。中学受験を経て私立の中高一貫校に入るものの、中学二年からロンドンへ。ロンドンでも二つの学校を経験しました。大学に入った後は、このブログにこれまで書いてきた通り、正規学生として東京大学・ポモナ大学・ブラウン大学に在籍しました。それ以外に、留学生として在籍した北京師範大学やカンタベリー大学を含めると、合計で五つの大学を経験しました。このような僕の経験は、自分で言うのもおかしなことですが、本当にユニークです。
普通の人は、教育というものにおいて、一つの道しか経験できません。人生は一度ですし、ほとんどの人は一つの学校に通います。だけど自分は、幸か不幸か、国境や階層を超えて様々な学校に触れられる機会を得られた、世界中見渡しても類を見ない人だと感じます。自分だからこそ書ける教育論が存在するのではないかと、最近強く思い始めました。今回の記事は、そのような発想から執筆に至っています。

(ノルウェーの住んでいた地域で行われるクロスカントリースキー大会。オスロインターナショナルスクールでは、クロスカントリースキーが必修でした)
2. 今までの経歴と、それから見えてくるもの
僕は今まで、何校もの学校を経験してきました。以下が、学校別にまとめた僕の経歴です。
| 期間 |
在籍校 |
種別 |
| 幼稚園:年少 |
翠幼稚園 |
私立 |
| 幼稚園:年中・年長 |
千葉大学教育学部附属幼稚園 |
国立 |
| 小学1年(~7月) |
千葉大学教育学部附属小学校 |
国立 |
| 小学1年(9月)~4年(3月) |
オスロインターナショナルスクール |
私立 |
| 小学5・6年 |
千葉大学教育学部附属小学校 |
国立 |
| 中学1・2年(~7月) |
麻布中学校 |
私立 |
| 中学2年(9月~翌1月) |
インターナショナルスクールオブロンドン |
私立 |
| 中学2年(1月)~高校1年(6月) |
アメリカンスクールインロンドン |
私立 |
| 高校1年(9月)~高校3年 |
麻布高等学校 |
私立 |
| 大学1年(~7月) |
東京大学 |
国立 |
| 大学1年(9月~翌6月) |
ポモナ大学 |
私立 |
| 大学2~4年 |
ブラウン大学 |
私立 |
|
以下、留学先
|
|
|
| 大学1年(6月~8月) |
北京師範大学 |
国立 |
| 大学3年(2月~6月) |
カンタベリー大学 |
私立 |
2-1. 幸福度と成長度
これらの学校のうち、記憶があやふやな幼稚園と、一学期未満在籍した北京師範大学を除き、自分が幸せだった学校と、自分が成長した学校を、それぞれランキング形式でまとめました。
幸福度ランキング
| 順位 |
学校名 |
| 1 |
ポモナ大学 |
| 2 |
オスロインターナショナルスクール |
| 3 |
東京大学 |
| 4 |
ブラウン大学 |
| 5 |
カンタベリー大学 |
| 6 |
麻布学園 |
| 7 |
千葉大学附属小学校 |
| 8 |
アメリカンスクールインロンドン |
| 9 |
インターナショナルスクールオブロンドン |
成長度ランキング
| 順位 |
学校名 |
| 1 |
ブラウン大学 |
| 2 |
オスロインターナショナルスクール |
| 3 |
アメリカンスクールインロンドン |
| 4 |
ポモナ大学 |
| 5 |
東京大学 |
| 6 |
千葉大学附属小学校 |
| 7 |
カンタベリー大学 |
| 8 |
麻布学園 |
| 9 |
インターナショナルスクールオブロンドン |
学校によって在籍期間も異なる上、在籍時期も異なるため、基準はバラバラです。一年生から進学したのではなく、途中から転校してきた学校には、イマイチ好きになれなかった学校もあります。インターナショナルスクールオブロンドンは、アメリカンスクールに入るための繋ぎとして入った学校で、あまり教育がしっかりしている学校ではありませんでした。カンタベリー大学に関しては、大学の外でたくさん成長しましたけど、それが大学から与えてもらったものかというとちょっと違う気がします。学校が多くのものを提供してくれて充実していた場合は、幸福度も成長度も、自然と上の方に順位が来ます。また、一日の大部分を過ごす学校というのは、一つのコミュニティ・社会でもあります。優秀で刺激的な人に囲まれていた場合も、ランキングで上位に入る気がします。

(日本の小学校で必修だった組体操。すごく苦手で、慣れるのに長い時間がかかりました)
2-2. 青年教育の経験から
僕の経験からは、様々な考えを導く事ができます。例えば、日本のドメスティックな小学校とインターナショナルスクールを往復した経験は、非常に独特でした。2015年1月号の記事において、印象に残っている『ハーフ』というドキュメンタリー映画について述べさせて頂きました。このドキュメンタリーでクローズアップされている登場人物の一人も、同様の経験をしている小学生です。小学校というのは、勉強能力以上に、文化と価値観を叩き込まれる場所。その時期に、叩き込まれる価値観が全く異なる世界を往復すると、自分がうまく実力を発揮できない葛藤や、それぞれの世界に馴染めない悩みが生まれます。それは、Transnationalな経験をしている子どもや、アジア系アメリカ人など家庭と学校の文化が異なる子どもの葛藤とも、共通しています。
上の話は別に一記事くらい書けるような内容だと思うので、今回は割愛させて頂きます。ここから先クローズアップしたいのは、日本の学校教育システムにおける中学校~大学の学校教育、すなわち、青年教育です。生活習慣やマナーなど文化や価値観から、よりアカデミックな部分に教育がシフトしてくると同時に、学生自身の心理に迫ってみても、自我形成期を迎えて、教育に対して求めるものが少しずつ変化してくる時期にあたります。この時期の僕は、国や学費も異なる三つの中高、三つの大学に通い、教育の質に応じて、スランプから覚醒まで味わってきました。ここからは、自分自身の経験を振り返り、教育の質(青年期)の根底にあるのは何なのか、考えてみたいと思います。

(ポモナ大学の卒業式。すごく温かみがあります)
3. 教育の質
特に私立の学校において、教育というのは学生に対して売っているサービスに他なりません。そのサービスに充実感があれば、子どもは幸せで成長も出来るでしょうし、親もサービスの対価を喜んで支払います。そのサービスに不足があれば、子どもは葛藤し、親も対価の出費を渋ります。子どもが幸せで成長できる教育が良好なサービスであるという前提に立つならば、サービスはどのようにして改善できるのでしょうか?
3-1. 青年時代の欲求
僕は心理学に精通しているわけではないので、引用とかを交えてこのテーマを語ることは出来ないのですが、一般論として、自我形成期の青年には、「自己実現」と「他者承認」に対する欲求が強くあると言われます。どちらも、欲求を五段階に階層化した心理学者マズローによる『欲求段階説』に出てきます。自己実現とは、自分の持つ可能性・能力を発揮して、具体的な何かを成し遂げる事を指します(15年3月号でも詳しく述べています)。また他者承認とは、他の人から価値のあるものと認められ敬われる事を指します。
自己実現と他者承認。二つのキーワードに落とし込むのならば、学生が幸せで、なおかつ成長できる青年教育というのは、この二つの欲求を漏れなく満たしてくれるものであると言えるでしょう。良い学校は、学生の自己実現を後押しして、学生を温かく承認します。
3-2. レールを敷くという行為
自己実現や他者承認と言っても、そのスケールは大きなものから小さなものまであります。学級委員になる事だって一つの自己実現ですし、学級委員になる事によって他の学生からリスペクトされたのであれば、それは一つの他者承認にあたります。
自己実現と他者承認の機会を一つ一つ提供すること、すなわち、学生が乗っかれるレールを敷いてあげるのが、学校の役割です。教室に放置されていても、学生は何も見出せませんし、何かに挑戦する事もありません。だけど、学生が自然に乗っかれるレールがあれば、レールを用いて誘導してあげる事ができる。あとは、学校が持っているリソースによりますが、学生に対してどのような種類・質のレールを敷いてあげられるかにかかってきます。
日本では最近、自由でのびのびという教育方針がトレンドになっています。だけど、このような考え方は放任主義と結びつきがち。例えば、僕が教育関係のインターンをしていた香港において、そのような考え方はありません。ある学生が何を好きになって、どんな道を選ぶかと言うのも、何を与えられているか、何を知らされているかによって決まるのだから、ある程度レールを敷いて誘導する必要がある。のびのびばかりを重視する放任主義の教育に、僕は少なからず反感があります(若々しい記事ですが、13年12月号で話しています)。
3-3. 二つの欲求が満たされる学校教育
自分の人生を振り返ってみても、ポモナ大学、ブラウン大学、アメリカンスクールインロンドン、それこそ2月号で述べたTECH::CAMPなど、自分を育ててくれるレールを敷いてくれた場所において、心理的に穏やかで、最も輝いていた気がします。
例えば、ポモナ大学での生活は、毎日が本当にポジティブでした。学校側が提供する様々なレールに乗っかるだけで、様々な自己実現機会を与えられます。中国語、Princeton in Beijing、環境学、震災被災地のフィールドワーク、WWOOF、これらは全て、ポモナが与えてくれた自己実現機会。それだけでなく、優しくて世話好きな教授たちや、大学側がセットアップした様々なコミュニティ(寮のコミュニティ、アジア系学生コミュニティ、中国語学習者のコミュニティなど)のおかげで、他者承認の機会も豊富でした。ブラウンでは、スランプの時期(16年12月号参照)もありましたが、文化人類学、Honors Thesis、教育心理学の研究、中国語、香港でのインターンシップ、Frontiers Abroad、全ては学校が提供してくれた自己実現機会でした。ブラウンの敷いてくれるレールは、学生全体の能力が高いのと、リソースに恵まれた名門校である事から、スケールが大きいものが多い。卒論にしても教育心理学の研究にしても、自己満足にとどまらず、今後の人生全体に影響を与えるものを成し遂げることができました。
ポモナにしてもブラウンにしても、学生に無数のレールを敷いてくれます。例えばどちらの大学でも、毎朝、その日に学内で行われるイベントをまとめたメールが、全生徒に配信されます。毎朝のようにそのメールを見て、その日もキャンパスでたくさん面白いイベントが起きていると知りつつ、「既に様々なイベント・活動に首を突っ込んでいて行けないなあ・・・」なんていう感覚、両大学では日常茶飯事。だけど、これらの学校にいられない人にとっては、突拍子も無く贅沢な世界です。
3-4. 二つの欲求が満たされない学校教育
自己実現も他者承認も、何かしらのレールが無いと実現されません。よく覚えているのが、高校から東大に入った瞬間。受験が終わった時期、僕は色々な活動に関わりたいと思って模索していました。だけど高校が提供するレールもなければ、学校の外に、高校生が関われるものもありません。4月に東大に入った瞬間に何が変わったかと言うと、レールの豊富さ。大学生になった途端に、学生団体やサークルなど、多くのレールを目の前に提示されます。この時期は、自分の中でも飛躍的に幸福度が上昇した瞬間だった覚えがあります。
自分自身に意欲があるのに、その意欲をどのように現実化すればいいのか分からないとき、人は最も葛藤する気がします。若々しい言い方になってしまうんですけど、そういう環境は、学生の能力を無駄遣いしてしまうと思うし、潰してしまうと思う。教育の質の根底にあるのは、二つの欲求を満たすために、学生に敷いてあげる様々なレール。これが、自分の教育に対する哲学です。
3-5. お金について
先ほど、「サービスに充実感があれば、子どもは幸せで成長も出来るでしょうし、親もサービスの対価を喜んで支払います」と述べました。これが私立の教育機関が成立する根源になっています。インターナショナルスクールやアメリカの大学を見ていると、素晴らしいレールを敷いてくれる反面、不当なまでに学費が高い。それもそのはず。アダムスミスの「神の見えざる手」ではないですが、素晴らしいサービスに需要が押し寄せ、学校のキャパシティで供給が制限されれば、当然のごとく価格はうなぎのぼりします。自分が素晴らしいと思う学校は、例外なく学費が高い。高額な学費を請求できる学校は、学費収入でカリキュラムやサービスをもっと充実させて、教育の質を更に上げていきます。これを見て、教育を要素分解して値札をつけようとする人は、教育価値が「インフレ」していると述べます。だけど、教育というのは人生に一度しか経験できないものだし、子どもに後悔をさせたくない。お金さえあるならば、最も人気で、最も質の高い教育を目指すべきではないか。そう僕は考えています。

(名門ボーディングスクールの一校である、セントポールズスクールのキャンパス)
4. ボーディングスクールとBSAJ
その中で、僕は残念ながら通うチャンスがありませんでしたが、僕の哲学に乗っ取った教育を実践している学校があります。それがアメリカの名門ボーディングスクール(寄宿学校、ここでは高校)です。
4-1. ボーディングスクールとは?
ボーディングスクールと言うと、学生全員、または大部分がキャンパス内の寮に住む寮制の学校を指します。学生は24時間キャンパスにいるため、24時間体制で指導を受け、寮の同僚や、共にキャンパスで暮らす先生と、密な関係を育むことができます。アメリカの名門ボーディングスクールは、「文武両道」「リーダーシップの育成」に重点を置いている学校が多く、少人数制授業を採用するだけでなく、アートやスポーツが必修になっています。寮や食堂、普段の生活を営むキャンパスは、学生が充実した生活を送れるよう徹底した配慮がなされています。ディスカッション授業は、ハークネスメソッドという手法を採用しています。先生の介入は最低限で、事前に準備をしてきた学生による主体的なディスカッションが行われます。
4-2. 教育の質という世界の頂点
ボーディングスクールといっても、本来は寮制学校を指すだけで、それ自体は学校の形態にすぎません。しかし資本主義国のアメリカでは、そもそも、私立学校(Private School)と公立学校(Public School)の間に大きな差があります(これに関しては、2015年10月号でも述べています)。例えば、僕がロンドンで通っていた二番目の学校は、アメリカ系の私立学校(Private School)です。スポーツ施設などは完璧に整い、徹底的な少人数制授業が行われ、しまいには小学5年生の学生全員にMacbookが無償配布される始末(日本の学校ではありえませんよね)。とはいえ、莫大な学費や、OBからの潤沢な寄附によって、十分に潤っています。これだけの学費を負担してくれた父の会社に感謝せねばなりません。このようなPrivate Schoolの中でも、寮を兼ね備えて24時間学生を指導し続けるボーディングスクールは、Private Schoolの教育の質を1日24時間に最大化させた学校です。学問、アート、スポーツ、ボランティアなど、徹底的に自己実現機会を与えられた学生は、毎日忙しくも充実した日々を送っています。それだけでなく、承認の機会だって豊富。ある名門ボーディングスクールでは、スポーツチームの試合があった際、どれだけ出場時間が短い学生であったとしても、その学生のプレーも他の学生と同じくらいの大きさのセクションを用いて、翌日の校内新聞で褒めたたえるそうです。このような学校の哲学って、本当に凄いなあと思います。
アメリカのボーディングスクールは、アメリカの大学と同じくらいの学費がかかります。だけど先ほど述べた通り、学費というのは提供しているサービスの質を反映しているに他なりません。学費が非常に高く、教育の質も非常に高いとは、資本主義の申し子のような学校ですよね(笑)。冗談はさておき、いわば教育の質という世界の頂点にあるのが、アメリカのボーディングスクールである気がしています。
ちなみにこの記事では、アメリカのボーディングスクールについて述べていますが、スイスやイギリスにも素晴らしいボーディングスクールがあります。
4-3. 社会階層の違い
ボーディングスクール出身の学生と話していて思うのが、非常に率直な感想なのですが、そもそも自分と社会階層が違うということ。2015年10月号の記事において、最近のTransnationalな(国境を超えた)教育では、己の社会階層と教育背景が直結しているお話をしました。そして該当記事において、ボーディングスクール出身生は、「大学や社会で飛躍する「準備」が普通の人以上に出来ている気がします」と述べました。日本の高校や、アメリカの公立高校から来た学生が、ブラウンの大量の宿題に押し潰されそうになっているのを脇目に、ボーディングスクール出身の学生は平然と課題をこなし、様々な活動に関わっていたりします。親のバックグラウンドも大きいのでしょうが、自分が知らないようなアメリカのお偉いさんや有力者と繋がっている学生も多い。これは香港にいた際に実感した事なのですが、そもそも頭がとてつもなくいいと感じる学生も多い。相手の頭の回転に自分の頭の回転が追い付かず、相手の話にやっと返答しようと思った時には、既に次の話題に移っているなんて感覚(笑)、香港ではよく味わいました。僕はボーディングスクールを経験していません。しかし、上記のような階層を飛び越える経験をしてきた事で、ボーディングスクール出身生に出会い、その教育について知る事ができました。
4-4. BSAJ
最近、そんなボーディングスクールに、活動を通して関わっています。昨年、ブラウンの同級生とともにBSAJ(Boarding Schools Alumni of Japan)という団体を立ち上げ、現在まで代表を務めています。詳しくはウェブサイト(http://bsaj.jp/)をご覧下さい。もともとこの活動をやり始めたのは、ブラウンの同級生から誘われた上、自分もボーディングスクールに少なからず興味を持っていたから。だけど、ここまで大きな活動になると、自分は思ってもいませんでした。BSAJは今春、一般社団法人になり、数々のメンバーや理事会を抱える一大組織に成長しつつあります。パートナーの会社とイベントを開催するだけでなく、日本におけるボーディングスクール出身生のネットワーク作りや、BSAJの活動を通じて現役ボーディングスクール生に自己実現機会を提供するのも、活動の大きな比重を占めています。BSAJメンバーは、アメリカ名門ボーディングスクールの卒業生と現役生。このように拡大できた理由も、ボーディングスクールで切磋琢磨されてきた、メンバーの能力や行動力の高さに他なりません。一人一人のメンバーが個性的で、一人一人の実力によってBSAJは支えられています。自分も活動を通して、ボーディングスクールに対する理解を深めると同時に、自分も経験してみたかったという気持ちをひしひしと味わっています。

(BSAJのウェブサイト:http://bsaj.jp/)
先ほど述べた通り、インターナショナルスクールと日本の学校を往復するなど、文化の違いに関して僕は苦労した経験があります。留学生としてのボーディングスクール生活だって、決して甘いものではありません。寮制学校であれば、逃げ場もありません。だけど文化というのは、幼少期や家庭のバックグラウンドに影響され何を自然に感じるかの問題であり、教育の質とは全く異なる場所にあります。教育の質は二つの欲求をどれだけ満たすかによって定義されるのであり、アメリカ的な文化によって教育の質が下がるという事はありません。教育の質が高い学校がアメリカ文化圏に存在するのであれば、子どもを最初からそのような文化に染めて、アメリカ文化に快適さを感じるように育て上げればいい。僕だったらそこまで考えてしまいます。
人は一つの学校しか経験できない、それゆえに学校教育に関して視野が狭まってしまう・・・そんな話を最初にしました。しかし、このような学校教育のネガティブな性質は、ポジティブに捉えることもできます。学校の選択肢によっては充実した経験を得られないまま人生を終える一方、ただ一つ、学校の選択肢さえ変えれば、非常に充実した人生を送るかもしれない。パラレルワールドではないですが、異なる選択肢を選んでいた場合の人生というのは、どうやっても同時に経験する事ができない。それゆえに、学校教育というのは面白いものですし、自分も将来ずっと意識して生活していくトピックだと思います。
今月はこれで締めさせて頂きます。来月は、大学の話に絞りながら、自分が経験した様々な大学が提供してくれたものと、それがどのように自分に影響を与えたか、話していきます。では5月号で。
|
|
この記事の先頭へ戻る
◇ 2017年3月 教育心理学の研究
◇ 2017年2月 TECH::CAMP
◇ 2017年1月 Honors Thesis(卒業論文)とIndigenous Knowledge
この記事を折りたたむ
|
◇ 2017年1月 Honors Thesis(卒業論文)とIndigenous Knowledge
あけましておめでとうございます!先月は先延ばしにしてしまいましたが、今月は、Honors Thesis(卒業論文)の話をしていきます。先月号で述べた通り、アカデミック面では、現在、Honors Thesis執筆が生活の中心になっています。まだ研究も途中で、研究成果などについては述べられませんが、今月はHonors Thesisについて、じっくり語っていきます。
1. Honors Thesis(卒業論文)
1-1. アメリカにおいて
1-2. ブラウン大学において
1-3. ニュージーランド時代の経験
1-4. 将来へ向けて
2. 研究内容
2-1. 考古学データベース
2-2. 津波研究と人類学の架け橋
2-3. 地理情報システム(GIS)
3. Indigenous Knowledge
3-1. Indigenous KnowledgeとWestern Scientific Knowledge
3-2. ニュージーランドや日本の事例
3-3. Indigenous Knowledgeの性質
3-4. Indigenous Knowledgeの面白さ
3-5. 環太平洋火山帯の口頭伝承を用いて
3-6. 伝承研究の面白さ
雑感:人生を変える経験について
1. Honors Thesis(卒業論文)
Honors Thesisと先程から格好つけて述べていますが、Honors Thesis自体は、日本の大学においても執筆する卒業論文の事です。
1-1. アメリカにおいて
それでも自分がHonors Thesisという名前に拘るのは、多くのアメリカの大学において、Honors Thesis執筆は卒業に必須ではないから。反対に、Honors Thesis執筆やそれに該当するプロジェクト(Capstone Projectと言います)をやって卒業すれば、普通の卒業生とは違う、Honors Academic Designation(特別な卒業生としての認定)を得る事ができます。Honors Thesisを執筆した学生は、学内シンポジウムにおいて15~20分のスロットを与えられ、研究成果を発表する事となります。
1-2. ブラウン大学において
また、Honors Thesis自体、希望すれば誰でも書けるものではありません。ブラウン大学では、専攻科目の授業(自分ならAnthropology)の成績の大部分がAである必要があります。すなわち、成績優秀でないとHonors Thesisを書く権利も与えられません。その後も、研究内容を提案する段階で落とされるケースもあれば、論文執筆後に、内容不十分でHonors Thesis不適格とされるケースもあります。ブラウン大学のAnthropology(人類学学科)においては、Honors Thesisに不適格とされた作品は、「Senior Thesis」という称号を得ます。Senior Thesisも直訳すれば「卒業論文」なのですが、ここまで読んできた方には、Honors Thesisとの違いが分かると思います。
1-3. ニュージーランド時代の経験
昨年春、僕はニュージーランドで過ごしていました。ニュージーランドでは、地球環境を愛する未来のサイエンティストに囲まれ、ハードコアなリサーチプロジェクトを行うなど、アカデミアを意識する生活をしていました。周りには、教授の下でリサーチを行い、論文を共同執筆する学生もいました。サイエンティストにとって、これは大学院に入る上で非常に大事な成果。リサーチ経験を示す事で評価も高まります。
1-4. 将来へ向けて
Honors Thesisを書くのは非常に大変なプロセス。それゆえに、大学院を受験する時など、アカデミアの世界からは高く評価されると聞きます。自分も来年から日本の会社で働くため、アカデミアでの生活はひとまず最終年。ならば最終年に、大学生活の集大成となるものを仕上げたいと考えました。これが理由で、コンピューターサイエンスとか取ってみたい授業はあったのですが、時間をHonors Thesisに割く事にしました(もちろん、ものすごくやる気があれば、同時進行も出来たかもしれませんけどね)。
先月号でも述べましたが、せっかく論文を執筆するのであれば、大学の中にとどまらせておくのは勿体ない。ニュージーランドでは、教授と論文を出版する人もいました。そこで僕は、卒業論文に手を加えたものを、学術誌に投稿しようと考えています。自分の名前をアカデミアに残してこそ、大学生活に有終の美を飾れるのではないか?そう考えています。また就職後にずれ込んでしまうかもしれませんが、カンファレンスで研究発表を行うオプションも検討しています。
2. 研究内容
ここからは、Honors Thesisの内容について書いていきたいと思います。Thesisのトピックに関しては、ニュージーランドでの研究プロジェクトについて述べた、2016年6月号の記事を参照して下さい。簡単に言うと、東日本大震災の際に多くの神社が津波遡上域外にあった事を踏まえ、先史時代の人々の津波防災知識について、研究しています。ニュージーランド時代、一つまとまりのあるものは出来上がったのですが、色々と穴がありました。Honors Thesisでは、自分が非常に意欲を感じているこの研究を、続けています。前提知識は、昨年6月号の記事じっくり書かれているので、そちらも合わせてご覧下さい。今月は、Honors Thesisを書く上で、新しく取り組んでいる事を中心に話します。
2-1. 考古学データベース
さて、ニュージーランド留学中は、軍事的性能を持つ村落「パ(pá)」の空間的配置と津波の遡上域の関係を、GIS(地理情報システム:後述)を用いて研究しました。「パ」は、防衛を行うための砦を備えていて、周りの地形より盛り上がっている点が特徴。すなわち、今の時代であっても、リモートセンシングを用いて簡単に識別できます。しかし、「パ」は当時存在していた村落の全てではないですし、「パ」の建造自体、ニュージーランドに多くの津波が押し寄せた15世紀以降であるという調査結果も出ています。
僕の研究プロジェクトのアドバイザーは、考古学の教授。アメリカだと、考古学は人類学の学部内に含まれます。彼のアドバイスにより、考古学の発掘調査を利用して、「パ」以外の村落も調査対象に加える事にしました。発掘調査のデータは、ニュージーランドの考古学データベースから入手できます。考古学データベースの中から、自分の調査対象地域(ノースランド)の村落情報を抽出し、座標をGISに取り込んでいきます。発掘調査中、村落の使用年代推定が行われた場合、村落の使用年代が15世紀より前か後か調べる事もできます。このようにして、研究に使用するデータの一新を行っています。
2-2. 津波研究と人類学の架け橋
ニュージーランドにいた時は、マオリ文化に関する文献など、研究の理論的なベースをなす文献には手が回っていませんでした。Honors Thesisを執筆する上で、自分の研究プロジェクトのベースとなる理論を整理しないといけないため、たくさんの文献も読んでいます。そこで再認識したのが、今回の研究が、人類学のホットトピックと合致するという事。6月号の記事を読んで頂ければ分かるのですが、自分の研究テーマは、先史時代の人々が残した津波防災知識。文化人類学の世界では、文字情報に残されないような先史時代あるいは地域住民の知識を、Indigenous Knowledgeと呼び、主要な研究分野の一つに位置付けています。そのため自分の研究内容は、人類学で行われている様々なディスカッションへ、スムーズに入ってくる事ができます。
口頭伝承に残されたIndigenous Knowledgeの活用は、スマトラ島沖地震の際も注目されました。お年寄りなどから聞いた伝承を思い出して逃げた多くの人々が、津波被害を免れています。しかし津波防災知識に関する研究は、当然ですが、殆ど津波研究者によってなされています。そして津波研究者の殆どが、それこそ昨年僕がニュージーランドで囲まれていた地質学者など、サイエンティスト。文化人類学の立場からIndigenous Knowledgeという視点で津波防災知識を扱った研究は、あまりありません。

(既にブログでは取り扱っていますが、相馬市の津神社を訪問した際の写真です。「あそこ(津神社)まで逃げれば(津波から)助かるんだ」という伝承が、地域に存在していたようです。)
2-3. 地理情報システム(GIS)
昨年6月号の記事でも述べましたが、僕の研究ではGISを用います。GISはGeographic Information Systemの略で、日本語では地理情報システムと言います。GISとは、ありとあらゆる地図やそれに付随する地理情報を、コンピューターで管理するシステムの事。コンピューターで一括して管理する事で、異なる情報を別々のレイヤーに乗せて地図上で重ね合わせる事ができ、空間的分析が容易にできるようになります。また、膨大な地理情報をコンピューターが管理する事で、検索・表示を簡単に行う事ができるようになります(これに関しては、本が電子書籍になる事のメリットを考えると、想像しやすいと思います)。
僕は高校地理でGISという概念に触れて、興味を持ち始めました。その後、ブラウンに在籍していた大学二年次に、GISを用いるリサーチアシスタントのアルバイトをしていました。仕事内容は、1940年のアメリカ市街地図を、デジタル化するというもの。例えば僕はカンザスシティを取り扱ったのですが、スキャンした紙媒体の地図を下層のレイヤーに表示し、その上を線でなぞり、道路や区域を再現していきます。単純作業ですが、紙媒体の地図では高度な分析ができないため、この作業は地理学の世界で非常に大事。当時は単純作業しか出来なかったのですが、ニュージーランド留学時に、再びGISを使う事になり、GISのソフトウェアの使い方を学びました。GISのソフトウェアは扱いが難しく、本当に高度で専門的。Honors Thesis向けの研究を仕上げるため、来学期にブラウンのGISの授業を履修して、さらに技術を磨く予定です。

(GISの主流ソフトウェア、ArcGISの使用シーン。様々な地理情報をレイヤー毎に整理し、同じ画面に表示する事ができます。)
3. Indigenous Knowledge
最後の章では、自分のHonors Thesisの理論的なベースとなっている、Indigenous Knowledgeの話をしていきます。どうやらIndigenous Knowledgeは日本語訳が存在しないようなので、今後もIndigenous Knowledgeという言葉を使っていきます。
3-1. Indigenous KnowledgeとWestern Scientific Knowledge
Indigenousという言葉は、「土着の」という意味合いが含まれる、差別的な用語です。それはIndigenous Knowledgeが、Western Scientific Knowledge(西洋科学に基づく知識)の対義語として発展したため。世界中に広まっている西洋科学をベースとした知識ではなく、特定地域の社会・文化に根差している伝統的な知識が、Indigenous Knowledge。
もともとIndigenous Knowledgeは非科学的なものとして扱われていましたが、最近は多くの学問分野で、Indigenous Knowledgeの合理性が注目されています。Indigenous Knowledgeは、環境学・人類学・開発学など、様々な方面から注目を集めています。エスノグラフィーという手法を用いて、ある特定の集団で長期間過ごし、集団の文化・社会の質的研究を行う文化人類学は、まさしく世界中のIndigenous Knowledgeを「発見」する役割を持っている学問です。
3-2. ニュージーランドや日本の事例
例えばニュージーランドのIndigenous Knowledgeと言うならば、それは先住民マオリ族の知識を指します。マオリ族の環境に関する知識が注目されているのは、過去にも述べた通り(2016年3月号、6月号)。カワカワという薬草(5月号で少し述べました)が歯痛に良いという知識や、外洋航行中に特定の雲が見えたら下に陸地があるという知識、これらは全てIndigenous Knowledgeです。
Indigenous Knowledgeは世界中の様々な地域に存在します。日本でも、富士山に笠雲がかかった翌日は、東京で雨が降ると言いますよね。お米には7人の神様が宿っているという言い伝えがありますが、これだってIndigenous Knowledge。7人の神様という考え方、西洋科学の世界では説明できない概念ですが、昔の日本人にとっては何かしら合理性を感じさせるものだったに違いません。

(富士山の笠雲)
3-3. Indigenous Knowledgeの性質
そんなIndigenous Knowledgeですが、いくつかの性質があります。第一に、Indigenous Knowledgeは、ある特定地域の住民の間で伝統的に共有されてきた性質を持ちます。多くの場合、その地域の文化に深く根付いているのが特徴です。また、地域内でのみ共有されてきた場合や、文字を持たない先住民族の間で共有されていた場合、Indigenous Knowledgeは文字媒体に残されていません。口頭伝承という形や、実演によって後世に伝えられています(工芸品の作り方などは、まさしく実演で伝えられる世界でしょう)。そして6月号で指摘した通り、モニュメントに知識を託すなんてこともできます。神社が過去の津波被害を示すモニュメントではないかという考えは、6月号で述べた通りです。
3-4. Indigenous Knowledgeの面白さ
6月号の記事を読んで頂いた方には、既にIndigenous Knowledgeの面白さが伝わっているかもしれません。Indigenous Knowledgeが侮れないのは、現代科学の知識では知りえない情報が含まれているケースがあるから。
たとえば、地域住民しか知らない自然環境・農業・天候に関する知識はたくさんありますが、これらに着目せずして、その地域の開発を行う事は難しい。例えばある地域で伝統的に農業をやってきた現地住民は、土壌の質を維持するために、何種類かの作物を交互に栽培してきたかもしれない。このような知識が無い外部の人が、強制的に農業方式を変更させると、その地域の農業が持続不可能になってしまいます。
同様に、長らく被災地域で過ごしてきた人々は、現代科学に頼らずとも災害に対処する手段を持っている事が多い。日本における神社の活用は、その一環と考えられています。これゆえに、Indigenous Knowledgeの研究は面白いわけです。
3-5. 環太平洋火山帯の口頭伝承を用いて
自分がHonors Thesisのためにやっている事の一つは、津波に関するIndigenous Knowledgeを、口頭伝承から抜粋するというもの。Honors Thesisにおいて、GISを用いた分析のフォーカスはニュージーランドですが、日本とニュージーランドを関連付けて、環太平洋火山帯を調査対象地域と位置付けています。環太平洋火山帯は、地震や津波が昔から頻発してきた地域。そのような地域に、地元社会に根差す、伝統的な津波防災手段があるのではないか?これが、自分のリサーチの投げかける大きな質問です。
事実、環太平洋地域には、様々な津波にまつわる伝承があります。日本にはもちろん、アイヌ神話にもありますし、東南アジア地域にもあります。アラスカのトリンギット・インディアンに伝わる津波伝承があれば、アメリカワシントン州西部のホー・インディアンに伝わる津波伝承もあります。チリにも色々あると聞いているのですが、残念ながらスペイン語が読めないため、チリの文献はあたれませんでした。伝承というのは、昔話をイメージすればいいと思います。文化情報にまみれた昔話の中には、津波に関する知識がキラリと垣間見える事があります。これこそがIndigenous Knowledgeです。

(ワタリガラスを描いたトリンギット・インディアンのアート)
3-6. 伝承研究の面白さ
先月号では、自分が熱中している授業があるという話をしました。その名はAnthropology of Climate Change。気候変動を人類学的視点で捉えるという授業で、Indigenous Knowledgeに関しても、幾度となくディスカッションしました。
この授業ではファイナルペーパー提出が義務付けられています。出展を含めずに15ページなので、なかなか長い。このファイナルペーパーの題材として、自分は亜寒帯地域における口頭伝承の分析をしました。随所に現れるワタリガラスをモチーフとした伝承は、出身地が近く子どもの頃から憧れていた写真家、星野道夫が死の直前まで追求していたテーマ。小六の教科書に載っている『森へ』というエッセイで有名な彼は、伝承の起源を追い求めて行き着いたカムチャッカ半島で、ヒグマに襲われて亡くなりました。星野道夫を北へと誘った文化には、魅力がたくさん詰まっています。せっかくなので、アラスカの伝承から一本だけ抜粋して、記事を締めようと思います:
「During the winter, the mosquitoes and their parents live in one round room. Late in the spring, the young mosquitoes get tired of staying in the same place, but their parents say, “It is too cold yet, we will let you go in a little while.” Finally the parents open up the room; all the mosquitoes are very happy and they spread out over the whole country. But the weather soon turns cold again, and all the mosquitoes have to return to the room. When they all come home, the parents remark, “My! You all must have lost a great many people [i.e. mosquitoes],” but they reply, “Maybe four or five during the whole summer, but you never know.”(冬の間、蚊の家族は一つの大きな家に住む。晩春にもなると、若い蚊たちは家の中で退屈してくるが、親たちは「まだ外は寒いし、もう少ししてから外に出してあげるわよ」という。そしてやっと、親は家を開ける。蚊たちはみんな大喜びで、世界のそこら中に散らばっていく。しかしまた寒い季節がやって来て、蚊たちは家に戻らないといけなくなる。蚊たちがみんな家に帰ってきたら、親たちは言う。「あら、たくさんの子たちがいなくなっちゃったみたいじゃない。」それに対して子どもたちはこう答える。「夏の間全部で4、5匹かな、だけど実際のところどうか分からないよ。」)」
伝承って、不思議な魅力がありますよね。この物語を含めて多くの物語では、自然界を構成する動物などが擬人化されて、観察対象としての他者ではなく(西洋科学的な観点)、人々の生活に近いものとして描かれています。さらに上の物語、ちゃっかり、蚊が夏の間に大量発生する理由を説明しているんですよね。日本でもそうですが、蚊というのは夏に大量発生するものの、冬にはぱたりと姿を見せなくなります。これぞまさしく、Indigenous Knowledge。この伝承を伝えた人々は、蚊の生態について熟知していたということ。上の物語では、蚊がまるで人間のような大きな家族を構成すると述べられていて、夏にしか子どもを外で遊ばせないという説明がなされています。このようにして、蚊の生態を合理化しています。アラスカの冬では、人間の子どもだって遊ぶのはNG。子どもが外を出歩いたら、凍傷になるかもしれないですし、非常に危険。この地域に住んでいる人たちには、冬の間に子どもを外で遊ばせない習わしがあるのではないかと、推察できます。すなわち、蚊の生態に対して、人々の日常的な生活が投影されているんですよね。本当に面白いと思います。
今回の記事では、自分が取り組んでいるHonors Thesisの話に始まり、論文の内容にまで少々踏み込ませて頂きました。いかがだったでしょうか?少しでも僕の取り組んでいるトピックに対して関心が芽生えたら幸いです。ではまた2月号でお会いしましょう。

(夏のツンドラでは、虫よけネットを頭からかぶるのが常識)
雑感:人生を変える経験について
アメリカでは11月に、大統領選という大きなイベントがあり、アメリカの、特にリベラル世界の人にとって、今回の大統領選は本当に衝撃的でした。人生には、己に強烈なショックを与えるイベントが必ず存在する気がしますが、あるアメリカ人の友人は、今回の大統領選こそが、人生で最もショックを受けたイベントであると述べていました。この話を聞いた時、自分は不思議なほど納得しました。なぜかというと、日本人の自分にとっては、2011年の東日本大震災が全く同じようなイベントだったからです。目の前で起きている現実が信じられなかったのは、あの時が本当に初めて。今回の研究に取り組むモチベーションも、そんな自分自身の人生経験から生まれているのではないかと、いつも感じています。
|
|
この記事の先頭へ戻る
◇ 2016年12月 ブラウン大学最終年と、モチベーションサイクルについて
◇ 2016年11月 海外大生の就活事情③:自分自身の選択について
◇ 2016年10月 海外大生の就活事情②:学生にとっての様々な選択肢
◇ 2016年9月 海外大生の就活事情①:海外大生にとって有利な環境について
この記事を折りたたむ
|
◇ 2016年9月 海外大生の就活事情①:海外大生にとって有利な環境について
さて、前回宣言した通り、今月号からは就活について書いていきます。と言っても、何回か分けてのんびり話していければと思うので、最初の今月は、企業サイドから見た海外大生の就活事情について話していきます。
就活って、なんか一つの通過儀礼みたいな扱いなのが気持ち悪いですけど、日本の企業は新卒優遇なので、多くの人が通る道ですよね。日本で仕事をしたい海外大生だって就活を行います。日本に帰ってきて就活する場合は、国際経験豊かな海外大生にとって、なかなか有利な環境が整っています。
今月号では、企業サイドの観点から海外大生の就活について話します。なんでこんな話を知っているかというと、海外大生と日本の企業をマッチアップする人材系ベンチャーで昨年夏インターンしていたからです。今回の内容は、そこで経験した事が生かして執筆しています。
1.日本の企業が海外大生を求めている現状
さて、海外大生が日本で就活する場合、なぜ有利なのか?すごく単純に言えば、海外大生に限らず留学経験者は、国際経験豊富な人材を求めている多くの日本企業の意向にマッチしているからです。現在、日系企業の多くは、縮小傾向にある日本市場を飛び出し海外進出を目論んでいますが、海外進出のノウハウを全く持っていません。日系企業に限らず外資系企業も、国際色豊かな社風に合う学生を必要とするため、国際経験のある学生を欲しがります。政府が「グローバル人材」という言葉を多用し、交換留学生など留学経験者を増やそうとしているのも、日本社会でこのような人材が極度に不足しているから。そのため、海外大生のような国際経験がある学生は、引っ張りだこになります。
2.企業が海外大生と会う方法
人と人の出会いを表す「一期一会」という言葉がありますが、企業と学生の出会いも一期一会モノ。海外大生なんていうのは特にそうで、世界中にバラバラに散らばっているため、会う事すら難しい。そんな海外大生と接触機会を増やし、良い学生をスカウティングしつつ自社の魅力を紹介するため、日本の企業は莫大な資金と労力を投じています。以下は、日本の企業(日系企業+外資系企業の日本オフィス)が海外大生と接触する方法のほんの数例です。
2-1.キャリアフォーラム
こにおけるキャリアフォーラムとは、企業がブースを出展し、来場した学生をその場で面接して採用するイベントを指します。シドニー、ロンドンなど様々な場所で開催されていますが、なんて言ったって有名なのが「ボストンキャリアフォーラム」。150社ほどの企業が日本からわざわざやってきて、学生向けのブースを設営します。黒いスーツをまとった無数の学生が次から次へとやってきて、その場で面接を受け、その場で内定を獲得していく様は、圧巻です。この機械的でスピーディーなキャリアフォーラムは、接触機会の少ない海外大生を効率的にリクルーティングする、一つの方法です。

(ボストンキャリアフォーラムの様子。青いカーテンで仕切られているのは企業ブース、画面右端の白いカーテンで仕切られているのは面接室。)
2-2.キャンパスリクルーティング
日本での就活セミナーに顔を出せない海外大生と、堅苦しい面接会場以外で接触するには、海外大生が普段いる大学キャンパスまで出張するしかありません。アメリカの有名大学では、日本の企業による「キャンパスリクルーティング」が頻繁に行われています。企業の人事の人がわざわざ海外の大学まで渡って行って、大学のキャンパス内で学生向けの企業説明会を行い、一部の学生に対してはその場で面接を行います。ブラウンにいる日本人の学生(日系など含む)で日本での就職を考えている人は、学年あたり2人くらいでしょうか。それでもわざわざキャンパスまでやって来て頂けるあたりに、日本の企業の焦りのようなものを感じます。

(ブラウンに、某有名企業の方々が訪問した際のディナー会)
海外大生に会うためには海外まで行かないといけない事が多いですが、キャリアフォーラム参加やキャンパスリクルーティング実施には莫大なお金がかかります。海外大生の採用に積極的なのは大企業ばかりで、ベンチャー企業などは少ないですが、経済的要因が大きく働いています。
3.夏休み中に日本で開催されるイベント等
ボストンからは遠方すぎる上、キャンパスリクルーティングをやってメリットがあるほどたくさん日本人学生が通っていない大学の学生もいます。そういった学生にアプローチするチャンスが、学生が日本に帰国中である夏休み期間。この期間に海外大生向けの企業説明会や交流会、ワークショップを開催し、海外大生との接点を増やす事が出来ます。

(これは海外大生向けの合同企業説明会の写真。学生は、海外大学の雰囲気そのままに、カジュアルな外見で参加しています。ちなみに手前でこちらに背中を向けてリュックを背負っている方は、現在大躍進中のスタートアップの社長さんです)
時に、夏休み中に日本へ帰国している海外学生に対して個別面談を実施し、選考を行うなんていうケースもあります。忙しい人事の人がわざわざ個別面談してくれるほど、海外大生というのはVIP待遇な訳です。
以上の1~3、キャリアフォーラムは特にそうですが、企業が自ら実施する事は少なく、海外大生のネットワークを持っている人材会社を経由して行うケースが多い。自分が人材ベンチャーで働いていた際は、まさしく上の2や3のようなイベントのお手伝いをしていました。次月号は、自分の具体的な就活の話を踏まえながら、学生サイドで就活を考えて、海外大生がどのように仕事を見つけていくのか話していきます。
では次月号で。
|
|
この記事の先頭へ戻る
◇ 2016年8月 ニュージーランド留学体験の総括
◇ 2016年7月 中国系ニュージーランド人
◇ 2016年6月 東日本大震災と神社の空間的配置(NZでの研究プロジェクト)
◇ 2016年5月 エスニック料理(+ニュージーランド日常生活編)
◇ 2016年4月 ニュージーランドワイン
◇ 2016年3月 ニュージーランド編:大学生活と環境問題
◇ 2016年2月 ニュージーランドへ
◇ 2016年1月 異国へのロマンチシズム
◇ 2015年12月 生活協同組合とベジタリアン文化
◇ 2015年11月 教養教育の種類
この記事を折りたたむ
|
◇ 2015年11月 教養教育の種類
こんにちは。今回の記事は、普段の生活が非常に忙しいため短くサクッとしたものにしようと思います。テーマは教養教育。学際的な教育を重視する「リベラルアーツ教育」なんてものが謳われますが、日本とアメリカで少し捉え方が違う気がします。それについて軽く述べていきます。
1. アメリカのケース
1-1. 考え方を養うリベラルアーツ
1-2. リベラルアーツの起源?
2. 日本のケース
2-1. 教養人の定義
2-2. 洗練された人
2-3. 社会的ステータスを生み出す「教養」
3. 東大の教養課程から思うこと
3-1. 知識習得
3-2. マニアックさ
3-3. オタク的リベラルアーツ
4. いぶし銀な日本的教養人
1. アメリカのケース
アメリカのリベラルアーツ教育はどういうものか?これについては、ブログの2013年11月号「思考の軸」という記事で述べました。
1-1. 考え方を養うリベラルアーツ
東日本大震災以降、日本の災害研究の現場では工学専門家だけでなく人類学者、経済学者などを広く集めるようになったといいます。大きな問題を解決するのには、多角的なアイデアを持った人材が必ず必要になるからです。社会でリーダーとなる人は、ビジネスやエンジニアリングといった実践的知識だけでなく他の広範な知識を持っていなければならない。大学ではアートや歴史、哲学といった様々な学問を学びながら、それぞれの学問なりの「考え方」を身につけないといけない。三年次以降は気に入った学問を一つ専攻し、「思考の軸」を習得していきます。そうすることで多様な人材が含まれるグループを統括できるようになるだけでなく、究極的にはProblem Solving Skills(問題解決能力)を養うことが出来る。アメリカのリベラルアーツ教育には、こんなコンセプトが根本にあります。
アメリカのリベラルアーツ教育のポイントは、「考え方」を学ぶことが重視されている点だと思います。アメリカ人の学生は、小学生の頃から、常に、自分の意見を発信することを求められます。ディスカッションというのはまさしくいい例です。アメリカでは、ディスカッションを行うグループはバックグラウンドが多様なら多様なほどいいとされています。なぜかと言えば、他の人の考えを聞きながら自分の考えを成熟させていけるから。参加者が多様であればあるほど、多様な考えに触れる事が出来ます。様々な考えに触れ、己の思考能力・問題解決能力を磨き上げる事。それに力が注がれています。
1-2. リベラルアーツの起源?
リベラルアーツという概念は、中世ヨーロッパ生まれ。超大国アメリカの考え方が世界を支配するのは当然ですけど、上のような捉え方が絶対というわけではありません。中世ヨーロッパにおけるリベラルアーツの扱いは想像の域を出ませんけど、どちらかと言えば、それこそ下の日本のケースに似ていたのかもしれません。日本はどうなのか?

(中世ヨーロッパにおける、リベラルアーツの概念図)
2. 日本のケース
日本で、僕は運よく東京大学に在籍していました。東大は、日本の国立大学の中で、最も「リベラルアーツ」教育を謳っている学校です。文科1~3類、理科1~3類に入学時点で分けられるものの、一年生と二年生は全員同じ教養学部に所属し、三年次に学部へ進学します。一年生と二年生は、総合科目と言われる授業を履修しなければなりません。これら総合科目というのは、人文系、自然科学系など大きく5つの区分に分けられた授業群で、それぞれの区分から一定数以上の授業を取らなければなりません。まさしく、広範な教養を身に着けさせるための処置です。東大生活については、当ブログの最初の記事、2013年7月号の「駒場のリベラルアーツカレッジより」という記事にて詳しく綴っています。
2-1. 教養人の定義
日本では、「リベラルアーツの目的は教養を身につけること」と言われます。教養学部という言葉にもある通り、「教養」という言葉がリベラルアーツの対訳としてピックアップされたキーワードになっています。しかしこの「教養」という言葉は直訳に近い概念ではなく、日本特有の文化的な意味合いが含まれている気がします。
2-2. 洗練された人
日本社会で「教養」がある人って、どんな人を指すでしょう?一見仕事に役に立たないものの、広範な文化的知識を持っている人だと思います。例えば日本史や世界史の知識があったり、シェイクスピアや源氏物語など文学的知識があったり、諸子百家など哲学的知識があったりといった人です。教養があるという表現は好意的に用いられますが、文化的に優れた教養人は洗練されているとみなされ、社会の中でリスペクトされます。洗練されていると思われるにとどまらず、女性に顕著ですが、教養があることは家庭的バックグラウンドの良さを象徴すると言われることもあります。茶道や華道が「教養」の一種とされるのは、まさしくこういう文化の象徴だと思います。
2-3. 社会的ステータスを生み出す「教養」
アメリカのリベラルアーツ教育は「考え方」を養う教育なため、遠回しですが、社会に出てからの実践性を伴うと言えます。反対に日本における教養というのは、実践的でないだけでなく、実践的でない事を特長にしていると感じます。普通の人だと学ぶ機会・環境・時間がないため、教養というのは他の人と違いを生み出すことができます。例えば、お嬢様教育というのは、教養と結びつくケースが多い気がします。他の人との違いを作る教養というものには、お嬢様教育のように、社会的ステータスを生み出す力があります。

(茶道)
3. 東大の教養課程から思うこと
先ほどの段落で教養人がどんな人か説明しましたが、文学的知識や哲学的知識など「知識」という言葉がクローズアップされていました。実践性を伴うアメリカのリベラルアーツが「考え方」にフォーカスするのであれば、日本の教養教育は、実践性を伴わないものの他者との違いを作り出す事ができる、「知識」というものにフォーカスする気がします。
3-1. 知識習得
日本で高校受験や大学受験の勉強をすると、知識の習得が中心である事が分かります。知識って、持っているか持っていないかで簡単に人を判別できますし、人と人との間に違いを作る非常に簡単な手段。教養というのは人と人に違いを生み出すと先ほど話しましたが、その教養の軸になっているのが、この「知識」である気がします。
自分も東大時代、いくつか面白い総合科目の授業を取らせて頂きましたが、アメリカのリベラルアーツとは雰囲気が異なります。東大の総合科目は一年生や二年生が取る授業で、大講義室でやるレクチャーが多い。ディスカッションのように考え方をぶつけ合うスタイルというよりかは、教授の話に耳を傾け、知識の習得に力を注ぎます。
3-2. マニアックさ
こういった教養教育で習得する知識ですが、実践からかけ離れているどころか、非常にマニアックなものも含みます。アメリカでは一年生や二年生が専門分野外の授業を取る場合、多くの人が「~学入門」のような授業を取ります。経済学入門、環境学入門といった感じです。ある学問の「考え方」を学びたいのなら、そういった包括的な授業の方が一番いいでしょう。
反対に東大の総合科目において、大きな学問体系の入門授業はありません。総合科目以外に「準必修」と呼ばれる授業があるのですが、「法I」「経済I」「心理I」のような授業はそちらで提供されます。総合科目は、例えば「適応行動論」「社会行動論」「レジリエンス工学」のような、より細かい学問体系の授業であったりします。例えば「適応行動論」は、自然人類学、生物学、心理学なんかを巻き込んだ発展的な学問です。さらには、「イスラーム古典」「魯迅を中心とする現代日中両国の比較文学史」といった名前の授業もあります。一・二年生向けの授業なのに、教授が自らの研究テーマをレクチャーするものも多いです。熱く自分の研究内容を語る教授から学べるのは、学生のニッチな知的欲求を満たすマニアックな知識。それに尽きます。
こういった一風変わったマニアックな知識を習得する機会は、普通の人には与えられないPrivilege、特権です。このようなマニアックな知識が、ある人を他の人と区別する、教養というものを生み出すのだと思います。

(東大の総合科目リストから抜粋。リストは21ページにも及びます。)
3-3. オタク的リベラルアーツ
マニアックな知識を学生に与える教育、これを自分は「オタク的リベラルアーツ」と呼んでいます。誤解を招きたくないのですが、この場合のオタクという言葉に否定的な意味合いは一切ありません。オタクという言葉ほどビシッと言い表せる言葉がないから用いています。
オタクというのは日本生まれの言葉です。日本的な概念ですし、オタクは日本の都市部に不思議なほどたくさん存在する、日本文化の産物です。オタクというのは、例えばアニメや鉄道、地歴、ミリタリーなど、社会において実践的役割を持たない特定方面の「知識」を豊富に持っている人を指します。自らの知的欲求が導く方面に没入し、普通の人が持ちえないほど豊富な知識の習得を行うことで、他の人とは異なるステータスを自ら作り上げてしまいます。
オタクという概念が日本的であればあるほど、日本的教養教育に合致する側面を感じ始めます。日本でオタクという概念が生まれたのだとしたら、日本がこういう深い知識の習得を良しとする文化があるのかもしれません。ディープな知識を身につけることで他の人と異なる引き出しを会得し、洗練された文化人としての社会的ステータスを生み出す教育。これこそが、日本的教養教育であり、オタク的リベラルアーツの真髄だと思います。
4. いぶし銀な日本的教養人
日本で教養人とされる人の多くは、こういうオタク的側面を持っていると感じます。自分自身も結構オタクですし、お互いの気持ちはよく分かります。日本の教養人は、話をしていても知識の引っ張りどころが秀逸でとても面白い。アメリカの大学に行くような人ほど、自分の考えを自由に言えたり、ディスカッションでお互いの考えをぶつけ合ったりなど「考え方」を養う教育を重んじる人が多い気がします。いぶし銀な日本的教養人の魅力は伝わらないかもしれません。だけど、こんな渋き良き日本の文化が失われて欲しくないと、自分はなんとなく思っています。
では次は12月号で。トピックは「生活協同組合とベジタリアン文化」。今学期、僕は植物性の食事のみが許されるシェアハウスに住んでいるので、その話をしていきます。
|
|
この記事の先頭へ戻る
◇ 2015年10月 教育と社会階層
この記事を折りたたむ
|
◇ 2015年10月 教育と社会階層
こんにちは。もう10月ですね。いかがお過ごしでしょうか?
今回は、前から予告していた通り、教育と社会階層に関して述べていきたいと思います。香港で見聞きした内容に基づいて、世界中の富裕層を巻き込んで成長している「グローバル階級」、広がる格差に飲まれ戸惑う中産階級、そんな方面へ話を広げていきたいと思います。
前回の流れを引き継いで、今回も目次を掲載します。
1. 教育世界の三階級
1-1. 香港での経験から
1-2. 運命付けられたトラック
1-3. 良い学校に入る事と「privileged」
1-4. 階級の再生産
2. グローバル階級
2-1. 再生産のメカニズム
2-2. 海外大の役割
2-3. 「狭い」世界
2-4. ブラックカラー階級
3. 「最も損をする」中産階級
3-1. アメリカや香港で言われること
3-2. 生き残りをかけた競争社会
3-3. DGS
3-4. 高まる教育熱・高騰する学費
3-5. 格差が広がる中で
おまけ:愛国主義的人材育成?
1. 教育世界の三階級
今年の夏、香港のNoah's Arkでインターンしている時に(詳細は8月号)、興味深い話を聞きました。香港では教育世界を中心に三つの階級が生じているという話です。
この階級は、その人が通う(通った)高校の種類によって大まかに分けられます。
1. 公立高校に通う人たち。中産階級の人々です。
2. 香港政府によって支援された特別高校に通う人たち。これらの高校は名門校として香港政府から認定され、歴史的に政府から補助金を受け続けてきました。補助金が与えられるゆえ、教育の質の割に学費は安く、中産階級の優秀な学生は選抜試験を乗り越えて入学します。日本政府から補助金を受けているわけではありませんが、日本の名門進学校(開成や灘、麻布など)と立場は似ています。中産階級の親にとっては夢の舞台です。
3. インターナショナルスクール、ボーディングスクール(全寮制寄宿学校)、IB(国際バカロレア)認定校に通う国際的かつ富裕な人たち。
三階級と聞いたところで、ぴんと来ない人も多いかもしれません。香港に限定された話なのではないか?と。しかしこの三階級は皆が思っている以上に世界中へ広がっていると思います。日本も国際化が進み上のような社会がジワリジワリと広がってきているので、日本にも当てはまるという前提で読み進めていただければ幸いです。
1-1. 香港での経験から
この話を聞いたのは、Brown Connect(ブラウン大学の就活支援プログラム)を通じて発見した、香港でのインターンシップにまでさかのぼります。香港ではNoah's Arkというテーマパークで働かせていただきました(8月号参照)。Brown Connectというプログラムは、名前の示す通り、インターンプログラムを提供するだけでなく、キャリアに生かせるようなコネクション作りのお手伝いをします。コネクションは就職活動に大事なので、広義に解釈すると、大学発の就活支援プログラムと言えます。
事実、Noah's Arkのジェネラルマネジャーの方は、香港中の様々な有力者にインターン生を引き合わせてくれました。Noah's Arkを実質的に運営している香港随一の大企業Sun Hung Kaiの重役たち、ブラウンOBの世界的投資銀行で働いている人たち、世界中のNGOを支援する会社を立ち上げた人、こういった方々と交流する機会がありました。しかし何より感じたのが、ここNoah's Arkでの経験がいかに現実離れしたものであるかということ。ミシュラン星印の高級レストランで会食したり、Noah's Ark内でVIP待遇されたり、専属ドライバー付き黒塗り車で移動したり、ふんだんにお金をばら撒いて高級バーに侵入したり。そして、このような生活が日常である有力者と接触するうちに、彼らにどこか共通の背景や価値観、ライフスタイルがあるような気がしてきたわけです。一つの独立したユニット、あるいは階層として扱うことができるのでは?と。
そんな中ジェネラルマネジャーの方が、教育世界の三階級の話をしつつ、我々が接しているのは教育段階から厳選された社会のほんの一部を形成する人々なのだと教えてくれました。勝手な造語で恐縮ですが、1-1で述べた三番目の階級を「グローバル階級」と名付けようと思います。国際系のエリート学校で教育を受け、大学はイギリスまたはアメリカに出て、香港で忙しくも優雅な生活をしている人たち。このグローバル階級こそが、このブログ記事のテーマです。
1-2. 階級ごとに与えられたトラック
香港において、三つの異なる階級は、三つの異なる人生を歩むと言います。
公立高校というのは最も多くの人が通う一般的な高校です。多くの人はここを経験し、社会に出ていきます。
特別公立高校は日本でいう進学校のようなものですが、香港のそれはとてつもなくレベルが高いです。Noah's Arkでのインターン中、香港ナンバーワンの女子高DGS(Diocesan Girls' School)の女の子達と一緒に子ども向けキャンプ(DREAM Camp)を手伝いました。DGSは植民地時代の教会に端を発する超名門校で、政府支援校の代表格です。卒業生は、香港大学など国内名門大学、あるいは海外大にも散らばっていき、香港社会のあらゆる方面で活躍しています。
インターナショナルスクールなど国際系私立校からは、海外大学に進学するのが規定ルートです。よりドメスティックな上2つの選択肢に対し、こういった恵まれたバックグラウンド出身の人々は、自然とグローバルな生活を享受することになります。大学卒業後はグローバル企業に就職し、世界を股にかけて仕事する人が多くいます。
1-3. 良い学校に入る事と「privileged」
ポモナ大学にいた頃、ポモナの入学審査部長(Dean of Admission)とお話する機会がありました。その際に僕は、「応募書類に目を通す際に、名門校出身である事は考慮しますか?」という質問をしました。アメリカの大学受験では学内順位が重要なのですが、学内のレベルが高ければ自分の順位も下がります。それが不利に影響しているのであれば不当だろうという意味を込めた、質問でした。その質問に対する答えはあっさりしていました。「名門校に行っていたところで考慮しないよ」と。当時はこの答えが癪に障ったので色々と質問したところ、「良い中高に入っていた事は、それはあなたがよりprivilegedな(恵まれた)バックグラウンド出身であることを証明するだけだよ」と言われました。「良い中学校や高校に入るのはあなたの実力に依るものではなく、親の教育熱・バックグラウンド・資金力に依るものが大きい」と。中学受験を乗り越えた人間として、鼻をへし折られた気分でした。
アメリカの大学受験の際、Private School(私立高校)出身であるかPublic School(公立高校)出身であるか、必ず聞かれます。学生同士の会話でも、私立高校出身か公立高校出身か、話題になります。アメリカの私立高校の学費は高いですが、教育の質は桁違い。私立高校に入れさせてもらえる家庭の子どもは、それだけPrivilegedであるということ。
自分の場合、中産階級よりの家庭だと思いますが、母親が特別に教育熱心でした。それだけでなく、父の仕事で海外駐在を経験し、父の会社が学費を負担してくれたため、海外でインターナショナルスクールに通う事ができました。こういった恵まれたバックグラウンドをもらえたことが、都内進学校、ひいてはアメリカの大学に進学できた、唯一の理由でしょう。
1-4. 階級の再生産
自分自身がどのようなバックグラウンドで教育を受けたかは、後の進路や収入、所属コミュニティに影響を与えていきます。バイリンガルな教育環境や、アメリカの名門大学に行くだけの環境が整っている人は、それだけで大きなアドバンテージがあります。自分自身がprivilegedであったかどうかは、自分の子どもに投影されていきます。親が貧しければ子どもも貧しいという貧困のサイクルへ陥るように、親がprivilegedであれば子どももprivilegedになり、階級は再生産されていきます。階級という、明確に分離された社会ユニットが存在すると考えるのは、あながち間違っていません。
Noah's Arkには、子どもがどれだけprivilegedであるかがその子の人生の70%近くを左右すると言っている教育関係者がいました。いくら才能があっても成功できない人がいる反面、子どもの頃から恵まれた環境に置かれていて成功する人もいる。才能がある人は世の中にいくらでもいますが、グローバル階級に属している人をエリートとでも言うのなら、エリートと優秀な人は異なります。才能は成功の一助にはなるでしょうが、資金力や家庭環境、親の価値観も教育に大きな影響を与えます。
第3章でもう少し述べますが、現在、中産階級はかつてない流動性を持っています。中産階級間の格差が拡大しているためです。そのため、中産階級からグローバル階級に加わる人だってたくさんいます。この拡大の部分に大事な役割を担うのがDGSのような特別進学校でしょう。そのため、正確にいうとグローバル階級はただの「再生産」でなく、「拡大再生産」と呼ぶのがいいのかもしれません。固定化された階級でないことは一筋の希望ですが、格差が広がる将来には暗雲が立ち込めています。

(香港のフィナンシャル・ディストリクト)
2. グローバル階級
では先ほどから述べているグローバル階級、自分もアメリカの大学に来るまでこのような人々と接する機会が与えられていなかった気がします。彼らはどういう人たちなのでしょうか、どういう生態なのでしょうか。
2-1. 再生産のメカニズム
先ほど、階級は再生産されると言いました。人生の70%近くがprivileged度合いによって決すると言われるように、グローバル階級が新たなグローバル階級を再生産するなら、親が子どもをグローバル階級へスムーズに入れるメカニズムが存在するはず。今はさんざんグローバルが叫ばれている時代ですが、バイリンガル教育を受けただけで名門海外大に入り、名門海外大に入れば一流企業に入れるというのは、ご都合主義過ぎます。高額の国際系高校や海外大学に子どもを入れる資金力は当然ですが、香港に来て、他にも色々な要因があることに気がつきました。
一つ目は、こういった国際系の学校は莫大な学費を請求するものの、教育の質が非常に高いから。バイリンガル教育や子どもへの面倒見(サービス業としての教育)が徹底されています。海外名門大へ進学したいとなったら、高い読解力や論理力を鍛えてくれるし、ボランティアなど課外活動のチャンスを多く提供します。何より、学生に多くの機会を提供し忙しくさせることで、大学生活や仕事のプレッシャーに慣らせる役割も持っている気がします。アメリカでボーディングスクール出身の学生に会う度に思うのですが、こういった人は大学や社会で飛躍する「準備」が普通の人以上に出来ている気がします。
二つ目は、親の社会的地位や、ハイレベルの教育を受ける事を当然とする親の教育価値観、そのレベルに到達させるために子どもをお膳立てすることを当然とする教育文化があるから。親が作り出すこういった教育環境を生かすことによって、子どもは親と同じレベルへ到達できます。良い例があります。Noah's Arkでのインターン中、「バスケットボールキャンプ」という学生キャンプを手伝いました。これはなんと主催者が高校生で、インターナショナルスクールに所属するグローバル階級の子息です。母親は子どもの経歴作りとしてバスケットボールキャンプ主催を命じました。母親は自分が今まで培っていたビジネスコネクションと資金力を最大限に生かし、Noah's Arkとの共催を取り付け、我々ブラウンの学生をゲストとして呼び込み、専属カメラマンと新聞記者を呼んでイベントのお膳立てをします。こういった行為も全て、子どもに機会を提供する行為なのです。親が自分たちの資金力を生かして最大限にサポートし子供たちに機会を創出してあげる、チャンスをつかませてあげる。このようなレベルの課外活動は、アメリカの大学を受験する場合、合否を左右するレベルの経歴です。親は子どもが大学生になってもサポートし続けるのでしょう。香港出身のブラウン生は、大学一年生を終えたばかりでも、世界的投資銀行でインターンをしています。親のコネクションで入れさせてもらったのは間違いありません。
2-2. 海外大の役割
香港にいた時ブラウンのOB会に参加したのですが、このイベントでインド人のOBにお会いし、話に花を咲かせました。彼は幼少期からオマーンに在住し、オマーンのインド人コミュニティ出身でした。幼少期から国際経験に恵まれていた彼ですが、オマーンのインド人コミュニティからアメリカの大学を受験した人はそれまでいなかったと言います。しかし彼はアメリカの大学へ進学することの価値を見出し、アメリカの大学へ行くことがいかに将来に対する投資かというのを親に力説しました。「インド人はCommercial(商業的)な民族だから、投資とさえ言えば納得してくれるんだ」と、ニヤけ顔で話していたのを覚えています。アメリカの大学へ行くことは、グローバル階級に仲間入りすること、いわば階級を一つ飛び越えるためのチャンスをつかむために必要な手段だったと彼は言います。事実、このOB会だって、植民地時代に植民地政府の貴族が愛用したオシャレなカフェで開催されています。これぞグローバル階級という生活です。
インターナショナルスクールのような学校は教育の質も高く、学生がグローバル階級に到達するのを手助けするのではという話をしました。海外大の役割も似ています。第1章で述べたBrown Connectのようなプログラムが良い例です。大学側は学生にたくさんのサービスを提供し、就活支援においてグローバル階級の人々とマッチアップしてくれます。ブラウン大学に来られる時点で恵まれたバックグラウンドの人ばかりですが、Brown Connectのようなサポートプログラムがあるおかげで、学生は世界中に広がるOBや有力者の方々と繋がることができます。大学にはその他の就活サポートプログラムがあるし、先輩や同輩など周りのコネクションを生かすこともできます。そういう意味で、アメリカのトップ大学も、インターナショナルスクールやボーディングスクール同様、グローバル階級再生産のお膳立てをしてくれます(日本の大学などと比べて学費が高い点も、インターナショナルスクールやボーディングスクールの特徴と似ています)。
2-3. 「狭い」世界
再生産されるグローバル階級の仲間入りを果たすと、それが非常に小さい世界である事が分かります。僕はロンドンにいた頃、父の会社のおかげで、グローバル階級が子息を入れる学校に通えました。恐ろしい額の学費を請求するものの、高校のクセに完璧な設備を誇り、ロンドン随一のアカデミックレベルを維持している学校です。学費を払ってくれた父親の会社に感謝せねばなりません。びっくりするのが、この学校の同級生にアメリカ中どこいっても遭遇すること。ポモナ時代は隣のピッツァー大学に通っている元同級生がいましたし、友達が通っているコルビー大学へ遊びに行った時も元同級生に遭遇しました。さらに、現在ブラウンで住んでいるシェアハウスにも、元同級生がいます。
グローバル階級の人々はこんな状況に遭遇するたび、お決まりのように「世界って狭いんだね」と言います。本当にそうなのでしょうか?ロンドンからアメリカ、そして日本、こんなに世界中を飛び回れるだけの資本力を持っている人自体、世界人口の10%未満。さらに行った先で仕事や学業を行うグローバル階級の人なんて、世界人口の1%にも満たないでしょう。世界人口の1%弱と言えば7000万人弱、フランス共和国の総人口くらいでしょう。いわばフランス国内に全ての人が集まっていると考えれば、同じパリ住民に顔見知りも多いはず。世界が狭い訳ではなく、世界中を自由に飛び回れるほど恵まれているグローバル階級、これがとてつもなく少ない人口規模で回されているということなのだと思います。「狭い世界」という言葉はアメリカの大学で頻繁に使われるのですが、自分の中では使うのに抵抗のある言葉の一つです。「狭い世界」という言葉には皮肉が込められていると僕は感じています。
2-4. ブラックカラー階級
ホワイトカラーというのは労働者階級のブルーカラーとは対照的に、デスクワークに従事するなど中産階級を示す言葉として発展しました。中国ではまさしくホワイトカラーが増加しているのですが、中国人の造語で、ホワイトカラーの上の階級としてブラックカラーという階級が存在します。
このブラックカラー階級が指すのは、グローバル階級のことだと思います。彼らは服が黒く車も黒く、彼らの人生は中産階級からかけ離れているせいで想像つかず、それどころか収入や人生、仕事もどのような雰囲気なのか隠されています。政治的コネクションを持ち、税金をしっかり満額納めているのかも怪しいと言われ、これらを全てひっくるめてブラックという色に例えられています。最近の中国では中産階級間の格差が広がり、このブラックカラー階級が急速に成長していると言います。
もちろん税金滞納なんて表現には妬みが含まれていますが、グローバル階級という存在を一般人が見た時、こういう印象を抱くのも分かる気がします。普通の人生とはかけ離れ過ぎていて、何を幸せと感じ何を目標に生きているのか正直わからない。彼らの子息も普通の子どもたちとは隔離されて別の学校へ行っているため、子どもたちすらどんな生活を送っているのかも想像しづらい。そんな一般認識が伝わってくる造語だと思います。

(アメリカの名門ボーディングスクール、セント・ポールズ・スクール)
3. 「最も損をする」中産階級
意外に思うかもしれませんが、香港は人口の15%が貧困レベルを下回ると言われます。パキスタンやフィリピンからやってきて働いているドメスティックワーカーたちや、彼らに代表されるマイノリティグループの人たちがいるからです。香港人夫婦が朝から晩まで働き尽くめのところで、こういった方々が子どもの送り迎えや食事の提供、家の掃除などを行っています。彼らの権利は法律によって守られていて、休みを貰う週末には各所でコミュニティを形成し、のんびりお喋りに興じています。
香港には当然のごとくグローバル階級の人々もいます。しかしせいぜい、人口の5%でしょう。残りの80%は?といえば中産階級です。ここからは立場が変わりつつあると言われる中産階級の話をしていきたいと思います。
3-1. アメリカや香港で言われること
8月号で、香港のNGOに関する話をし、人口の5%未満にあたる人が人口の15%にあたる人々に支援を行なっている様子を報告しました。そんな香港では以下のようなことが言われます。「グローバル階級の子どもは資金とコネクションがあるから苦労しないし、貧しい子どもたちは政府やNGOの支援を受けることができる。教育において最も消耗するのは中産階級だ」、と。「最も損をする」のは中産階級だというのは、大学の学費高騰が進んでいるアメリカでも言われます。グローバル階級の子どもはグローバル階級に入ります。反対に貧しい生まれの子どもは貧しくとも支援を受け続け一定の幸福を得る事が保証され、大学に合格する才能があれば、莫大な奨学金が授与されます。逆に言うと唯一流動的なのが中産階級で、上に動くとも下に動くともつかない恐怖があるわけです。
3-2. 生き残りをかけた競争社会
上に動くとも下に動くともつかない恐怖は、中産階級の教育界に競争社会をもたらします。どんな学校へ行けるかで、中産階級の格差というのは大きく開いていきます。彼らの選択肢にはDGSのようなトップ教育機関もあれば、専門学校だってあります。
高校後も問題です。日本の東大ポジションにあたる香港大学は、中産階級にとって夢の舞台です。しかしアメリカやイギリスの名門私立大学に行きたいのなら、資金力を奨学金で乗り越え、英語教育の欠如(香港の一般人は広東語しか話しません)を勉強で乗り越え、不慣れな入試を乗り越えて進学します。ドメスティックな世界から突然グローバル階級に入れば、カルチャーショックだってあります。日本の一般高校から海外大を受験した人たちの苦労を見ればよく分かります。グローバル階級に属していない限り、何重にも備え付けられた壁を一つ一つ乗り越えなければ上り詰めることはできません。
3-3. DGS
以上のような文脈を踏まえると、DGSのような特別高校にいる人たち(2番目の階級)はどのような人たちなのでしょうか?
DGSに所属する学生は、恐ろしいほど勉強をします。自分の母校も日本の進学校で、御三家と命名された名門校だったはず。しかしDGS生は中1の頃から毎日5時間睡眠で、一日中宿題とお稽古事に明け暮れます。その上で中3や高1あたりはボランティア活動など課外活動に参加することが義務付けられ、高2あたりは自分が得意とする分野の大会に出場して高みを目指し、高3は当然のごとく受験勉強に追われます。DGS選抜入試では、学業優秀が前提条件で、水泳大会やダンス大会での受賞歴など、明確なアピールポイント持っている人のみがチャンスを得ます。
そもそもインターナショナルスクールに行けるだけの資金力やコネクションがあれば、子どもをDGSに入れる競争を回避できます。しかし香港において、インターナショナルスクールに子どもを通わせられる人は「世界を股にかける企業経営者」と比喩されます。DGSに子どもを通わせる人はと言えば、「香港を股にかける企業経営者」と比喩されます。教育熱心であっても、グローバル階級に上り詰めるほどの資金やコネクションが無いからこそ、激しい競争社会の餌食となるわけです。
DGSというのはまさしく、中産階級の夢を具現化した学校である気がします。人というのは、周りに異なる階層に属す人がいるのを知ることによって、階層意識を強く持つようになります。自分もアメリカや香港での経験が、階層意識を植え付けました。香港は日本以上に、華やかな生活をしている人々が目立つ社会です。そんな華やかな生活に上り詰めるために、流動的な中産階級の人々は負けじと教育を課し、熾烈な競争の結果DGSに子どもを入学させます。才女たちはDGSの教育を用いて、グローバル階級に仲間入りするためのキッカケを掴み取りにいくのでしょう。

(DREAM Camp中の写真。ブラウンのインターン生らと子どもたちを除いた8人の女の子はDGS生。DGS生は殆どが中学三年生なのですが、みんな雰囲気が大人びています笑。高校に入ると忙しくなりすぎるので、中三のうちにこのようなボランティア活動に関わるのだとか。)
3-4. 高まる教育熱・高騰する学費
このような競争社会が存在する以上、子どもの成功を祈る親の間で教育熱が高まっていきます。教育に関する熱が高まれば、インターナショナルスクールのような学校は経営に困らなくなり、学費を引き上げるため、学費はさらに高騰します。アメリカの大学学費がインフレ状態なのは、周知の通りです。学費だけでなく、塾やお稽古事の費用も高騰します。
グローバル階級に収まるには、それ相応の学費を払わないといけないので大きな負担を伴います。極端な例は中国(大陸)に住む外国人家庭です。詳しくは僕も理解できていないのですが、戸籍をその地域に置いていない外国人は、インターナショナルスクールに子どもを通わせる事しかできないと聞いたことがあります。外国人が中国でビジネスをやる時、子どもの高い学費を強制的に払わせるというのは、恐ろしい制度です。しかし仮に現地公立校に通えたとしても、別の問題が生じるケースがあります。フィリピン系など外国人の増加に伴い、最近は日本の公立小中校でインターナショナルスクールからあぶれた外国人の子どもが増加していますが、いじめが頻発しているのも耳にします。画一的な地元校だと、外国の人は馴染みづらいでしょう。公立学校にもインターナショナルスクールにも子どもを入れられないとなると、その国に残ってビジネスをすることが不可能になる人も出てきます。ゆえに地域内で裕福な家庭の選別が進みます。
3-5. 格差が広がる中で
台湾の農園生活(9月号参照)で実感したのですが、青年期というのは現代社会が創出したものです。人々が一次産業に従事していた時代、子どもは全て労働力でした。思春期を迎えたならば大人の仲間入りをし、労働します。現代社会において、子どもは一種の重荷です。一定期間の教育を受けないと労働市場にも入れないため、親への経済負担は重くなり子どもの数も減っていきます。子どもは子どもで学業に従事するという宿命が課せられます。先述の通り青年期の学業が将来へ直結する社会なため、中産階級の家庭は血眼になって子どもの教育を行います。
子どもの成功を祈る感情、それは純粋な親子愛そのものです。しかしこの純粋な親子愛、時には他の家庭の親子愛と衝突してしまうこともあるでしょう。世の中全ての親子愛が叶うわけでないのは、競争社会の真理です。ある家庭では、子どもが失敗し、親から子への信頼が崩れ束縛を強くし、反動として子どもは離反し「グレ」ていきます。家庭崩壊そのものです。現代社会が教育に付加価値を生み出さず、教育に対するプレッシャーが子どもへの圧力を生み出さなければ良いのに・・・そう夢見る人も多いはず。議論に上ることも多いこういった数々の現代的な家庭内問題、これらだって現代社会の異常さ、すなわち現代社会が青年教育に付与したインフレ状の価値ゆえに、生じたのかもしれません。
今月号も重厚なトピックだったので非常に長くなりましたが、学期も忙しくなってきたので来月号からは手抜きの記事に戻ると思います。では11月号で。
おまけ:愛国主義的人材育成?
以下、本文に入れることが出来なかったのですが、台湾や香港にいてもう一つ思ったことをコラムとして載せます。
日本でゆとり教育の改革が進んでいますが、それは教育に関するアジア内での相対的地位が下降し、政府が焦ったからでしょう。日本がライバル視している人材育成国家といえば、香港・シンガポール・台湾・韓国が挙げられます。しかし教育にまつわる三階級というものに直面すると、優秀な人材という言葉で一括りするのはおかしくて、「優秀な人材」にも異なる種類がいるのではないかと、そんな発想に導かれます。
香港は香港内に集まる富裕なグローバル階級を中心とした人材がたくさん輩出される気がします。アジアではありませんが、人材国家の一つであるアメリカもそうでしょう。シンガポールの詳しい事情は分からないのですが、香港と似ているのかもしれません。エンジニアなど国家を支える人材を育成するというよりかは、国家とは独立した私立学校においてリベラルアーツ教育を受けた、世界的リーダーを育てる印象を受けます。反対に台湾は、行ってみてわかったのですが、国内にたくさんの国立大学が設置されています。こういった国立大学で排出される人材というのは、輸出産業を発展させるために育成される人材で、中産階級出自の理系人材が多い気がします。韓国も似ているのではないかと想像できます。
台湾や韓国は、政治的対立から愛国主義的な理念を常に掲げます。現在も明確な敵対国(中華人民共和国、北朝鮮)が存在し、どちらの国にも兵役が存在します。小さな国を守るため国が力を注いで人材育成に勤しむのが台湾や韓国。それが中産階級の強化(三階級のうち1と2の強化)、理系の強化という施策につながっている気がします。
最近日本でも、理系を増やし文系を減らすという案が実行に移されつつあります。海外の新聞では途上国的な退歩であると批判されていますが、自分がふと思うのは、日本で強まる保守的な愛国主義的理想との関係です。台湾や韓国のような愛国主義的な理念によってこの施策が進められていたらどうだろう。アメリカのメディアには、政治批判を行う反動分子を排除するために文系が減らされているのでは、とすら言われています。今後の動向も注視していきたいと思います。
|
|
この記事の先頭へ戻る
◇ 2015年9月 台湾の有機農園と地域共同体
◇ 2015年8月 NGO大国香港
◇ 2015年7月 奨学金と日米併願
◇ 2015年6月 留学とGDPとアメリカンドリーム
◇ 2015年5月 人類学的なものの考え方
◇ 2015年4月 アメリカと日本の人種問題
◇ 2015年3月 没頭する学生
この記事を折りたたむ
|
◇ 2015年3月 没頭する学生
こんにちは。学期が始まって一ヶ月ほどが過ぎました。ブラウンは春学期、二回も長期の休みがあります。一つは一週間もの長さがある春休み。しかしこれ以外に、アメリカの祝日であるPresident's Day(ワシントン大統領の誕生日)と平日1日を含む四連休が、2月中にあります。せっかく東海岸に住んでいるので、今回は友達がいる他の大学に遊びに行ってみようと思い、イェール大学に遊びに行ってきました。今回は、そのイェールでいろいろな友達と話して考えた内容です。
アメリカの優秀な大学に行った日本人の大学生は、とにかく勉強をしている人が多いです。しかし彼らは元から勉強が好きな学者肌の人たちに限らないし、アメリカの大学の授業が日本の大学の授業と違ってすごく面白いかというと、そうとは限らないと思います(昨年ポモナにいた時ならそう言っていたかもしれませんけど、ブラウンに来て、東大のような大人数の講義もたくさんあることに気づきました)。アメリカの大学の授業の方が実用的かと言われても、そうとは限らないと思います。じゃあなぜここまで勉強に没頭する学生がいるのか?アメリカの大学の過酷な勉強というのは、学生あるいは若者の強い自己実現欲求を満たす、精神的に学生たちを満たす部分があるのではないかと自分は思います。自己実現をしたいのにそれを行えない日本の大学と、いわば学生たちが「没頭できるほどの環境を提供する」アメリカの大学があるのではないか。今回はそんな留学トークをしたいと思います。
1. アクティブな高校時代、非アクティブな大学時代
1-1. 課外活動で評価される日本の大学生
1-2. アメリカの学生像
1-3. 日本での経験
1-4. 日本に残ってたら...
1-5. 大学側が機会を提供してくれること
2. 自己実現
2-1. 自己実現とは
2-2. 若者の自己実現
2-3. 日本の大学における自己実現
2-4. アメリカの大学における自己実現
3. 自己実現を行うのに最適な場所
3-1. 無理をする必要の無さ
3-2. 没頭できる環境を提供してくれること
3-3. 大学生が最も大学生らしくいられる場所
3-4. 大学改革などに関して
1. アクティブな高校時代、非アクティブな大学時代
アメリカの大学を受験するには、高校時代の課外活動というものが大事になります。日本の大学に行った友達なんかから見ると、結構アクティブな人がアメリカの大学に行く印象があります。
しかし最近不思議に思うのは、大学生としてアメリカの大学に渡った後は、高校生の時ほど課外活動に関わる人が少ない事。自分の周りの日本人学生は、日本の時より部屋に引きこもって、勉強をしている人が多いです。アメリカ人の学生もこういう人が多く、ブラウンなんかでは、イヤホンをぶっさしたまま食堂やトイレに行き、ずっと一人で引きこもって勉強をしている人もかなりいます。自分は都内の進学校出身ですが、思ってみれば高校二年の夏、皆が受験モードに入るときに、イヤホン購入が妙に流行しました。なんかこんなのを見ていると、まさか受験時代に逆戻りしたのではないかと思ってしまいます。
実際のところ東大生からは、「まるで受験生みたいな生活してるね」って言葉を投げかけられます。もちろん受験時代とは異なる充実感を覚えているのは事実だけど、それが何なのかをうまく口に出来ない。そんな経験が今回の話のルーツになってます。
1-1. 課外活動で評価される日本の大学生
日本の大学で流行っている「意識高い系」という言葉があります。日本の大学生の間では、どれだけ様々な学生団体、インターン、学生大会に関わったかが、ステータスとなることが多いです。世界一周旅行をしたり、大きなイベントを企画したり、こういったいわば「凄いこと」をやることが学生の評価に繋がってきます。こういった「凄いこと」をやる学生を、「意識高い系」と総称する文化が、東大や慶応など様々な大学にあります。
こういった「意識高い系」は、課外活動を行うことを第一の目的とします。そのため、授業を欠席するなど、授業が犠牲になってしまうこともよくあります。しかし授業がつまらないのは事実なので、「授業よりもっと生産的なことをやっているのだからむしろ良いのではないか」、そんな文化が存在します。外野の大人は「日本の大学生はもっと勉強しろ」と言いますが、講義がつまらないままなら、課外活動の序列の方が高いのはやむを得ないことなのです。部屋に引きこもって勉強ばかりしていた受験生時代の過去に無意味さを感じ、反動が来ている大学生も多い。授業はサボりながらテストで最低限の点数を取り、活動でメキメキと力を発揮する要領が良いタイプの人こそ、「意識高い系」の中の花形です。
面白いことに、「意識高い系」という言葉はやや軽蔑的な意味合いも含みます。一番の理由は、活動で成功している人間への嫉妬のようなものでしょう。しかし思ってみれば、大学生というのは授業に出て講義を聞いていることが本職です。別に学校の外に飛び出す必要なぞ、本来はない。意識高い系に対して、「本来やらなくてもいい余計な事をやっている奴ら」という滑稽な印象を持つ人もいるのだと思います。英語には「Overachiever」という非常に良い表現がありますが、まさしくコレでしょう。軽蔑的とまではいかなくとも、「なんでそんなにムキになってるの」という印象を持つのは、やむをえないことだと思います。最近の日本が競争社会から協調社会に移行して、野心的な人が理解されづらい環境にあることも、このような文化が生まれる要因になっていると思います。
こんな日本の大学文化ですが、アメリカと比較する上でのキーポイントは三つあると思います。
A.日本の大学生が課外活動に関わることでステータスを保つこと。
B.勉強の序列が低いこと。
C.課外活動に関わることは大学生に定められた本職でもなんでもなく、大学生としての枠組みから飛び出してやっている活動であるということ。
この3点を踏まえた上で、今度は自分の思うアメリカの学生像と比較してみます。
1-2. アメリカの学生像
アメリカの大学生は非常にアクティブだと思われがちです。しかし東大の学生が課外活動で東京中あるいは日本中を行き来している姿を見ると、こちらの大学生の学生生活は、キャンパスという狭い範囲に収まっていると言わざるをえません。
大学のキャンパスには、寮、映画館やスーパー、郵便局が入っていて、生活がキャンパスの中で収まります。それどころか、キャンパスコミュニティに収まっていることを良しとする価値観もあります。現在のルームメイトは、マサチューセッツ州出身のため、自宅がブラウンから車で30分以内の距離です。日本の価値観を知っている自分は彼に対して、「実家から大学まで通学したらどうだ?」と勧めました。大学の寮費もバカ高いですもんね。ルームメイトは悩んで親と相談していたのですが、親から拒否されたそうです。「大学生は出来るだけキャンパスコミュニティの近くにいないといけない。」キャンパス内の寮に住み、大学の他の学生と常に交流を保っている状態が最も「健康的」な学生生活であると、そう親から述べられたそうです。日本の大学では、多くの学生が実家から通い、他の学生はアパートの部屋に一人で下宿しています。それだけ考えても、キャンパスとの物理的な距離感が全然違います。
じゃあアメリカの大学生はどのような課外活動をするのか?正直言うと、日本の大学生ほど活動をしないと思います。勉強で多くの時間を取られるし、課外活動をするとなっても、週に一回くらい大学のクラブ活動に顔を出すなど、日本の価値観からするとスケールが小さいものが多いです。
1-3. 日本での経験
アメリカの大学に入学する際には課外活動というものが非常に重要なため、アメリカに行った学生も課外活動の面白さや意義については重々承知しています。なので自分が東大生(その中のいわゆる「意識高い系」)と接していると、単純に「すげぇなあ」という感想を抱きます。頑張っている学生は大学を飛び出して色々なものに関わっているため、本当にこういう感想を抱きます。
彼らの話を聞いていれば、もちろん、自分の話も聞かれます。「最近なにやってるの?」と。日本の大学における文化では(いわゆる「意識高い系」の中でですが)、この質問は、最近やっている課外活動を主に指します。「勉強してるよ」という答えより、「どこどこの会社でインターンしてるよ」という答えの方が、もちろんステータスも高くなります。
しかし不思議なことに、アメリカの大学生がこの質問を聞かれると、「勉強してるよ」と答えざるをえないことが非常に多いです。そりゃ、勉強量も多いですし、勉強以外に活動に関わるというのも中々ハードルが高いです。やっているとしても、「ちょっとクラブ活動やってる」とか「バイトやってる」程度のもので、これもインターンや学生団体、学生大会と比べるとスケールが小さい。最近の自分のケースを考えると、バイトをやっている以外では、料理をたくさんやっているくらいです。そんなこともあって最近の自分は、「俺の課外活動は自炊さ」などと言うこともあったのですけど、なんか腑に落ちない。アメリカまではるばるやってきたのに何やっているんだろうという感覚に至ります。
結局は、二つの大学にそれぞれの文化があり、それぞれの価値観があるからこそ、一方を相手方に当てはめた時、価値が突如低くなってしまうことがあるんだと思います。
1-4. 日本に残ってたら...
さらに不安を煽るのは、もし自分がアメリカの大学に行くことを決めず日本に残っていたとしたら、その「意識高い系」のような活動を自分も出来ていたのか、自問自答してしまいます。今は、大学から与えられた勉強をこなしている自分ですが、そんな自分が突如東大のような環境に放り込まれた場合、自分の人生はどうなってしまうのか。
自分でなんとか活路を見出すために、様々な人にメッセージを送って会ってお話をし、積極的にコネクションを作っていくのは、アメリカの大学の受験時代にも経験しました。高校時代、課外活動に関わったり先輩に話を聞いたりするために、こういったことをやったのですが、こういったアクションを起こすのにはそれ相応のバイタリティが必要なものです。「意識高い系」は、そのようなバイタリティに溢れている人ばかり。
1-5. 大学側が機会を提供してくれること
じゃあアメリカの大学の価値は何なのでしょうか?アメリカの大学の価値を端的にいうと、大学そのものが様々な機会を学生に提供してくれること、それに尽きると思います。
アルバイトとインターンの例が分かりやすいのであげてみたいと思います。東大生ならば大学の外に出て塾講師や家庭教師をやるのが普通ですが、アメリカの大学でアルバイトをする場合、大学側が募集しているキャンパス内の仕事に応募します。大学は、生徒がアルバイト経験を積めるために、キャンパス内の仕事を列挙したウェブサイトを作ります。生徒はそんな与えられた機会からアルバイトを見つけ、仕事に就くことができます。アルバイトの中でも、リサーチアシスタントやTAの仕事は、履歴書に書く事もできる経験です。
インターンも同様。アメリカの大学生、学期中は時間がないためインターンをすることはないものの、夏休みが三ヶ月以上と非常に長いため、夏はインターンをすることが結構あります。これに関しても、ポモナのように面倒見がいい学校だと、大学側がOB経由で世界中のインターン募集情報をかき集めてきて、大学のウェブサイトに掲載します。それどころか、ポモナではCareer Development Office、ブラウンではCareer LABと言われる大学内の機関が、何人もの就職カウンセラー(Mastersを持っている優秀な人がいる事も)を雇って、学生の世話をします。これもまた、大学側が色々と提供してくれる一例だと思います。日本の大学だと、インターンなどというのは限られた行動的な学生しかやっていませんが、それもそのはず。日本でインターンを探すとなると、必死でコネクションを作って、頭を下げて様々な社会人にお願いしてまわらないといけませんから、そうならざるをえないと思います。
勉強だって、まさしく大学が提供するコンテンツの代表例だと思います。生徒が勉強内容に関して自由に質問ができるように、オフィスアワーが提供されています。勉強場所の確保に困らないように、図書館は24時間開放されています。このような環境、「そこまで大学がものを提供するからこそ、勉強以外に何もやらなくていいんだね」と、日本の大学生に羨ましがられることもあります。ここまで多くの学費を払って通う私立大学なのだから当然とも言えますが、学生に対するこんなサービスの厚さが、アメリカの大学生としての日々を充実させています。

(試験期間前後は24時間開放されているブラウンの図書館。)
2. 自己実現
しかし、それでも湧いてくる疑問があります。正直、アメリカの大学生は「勉強している」どころではありません。英語だと「Driven」なんていう言葉を使うのですが、彼らはまるで何かに取り憑かれたかのように、ものすごく勉強をします。勉強に対する姿勢も、「I'm passionate about Biology(俺は生物学に対して情熱的なんだ)」なんていう言い回しがよく聞かれますが、みんな、好きでそれぞれの勉強に没頭しています。そうでもないとアメリカの大学でよく聞く、「朝3時まで勉強」なんていうライフスタイルは貫けないはず。
勉強があまりにも好きなんなら彼らは学者肌なのかというと、そんなわけでもありません。高校時代は積極的に課外活動に関わっていた人たちです。別に勉強の内容自体は日本と大きく変わりません。将来仕事で役立つから勉強をするというわけでもないはず。どこからそんな勉強に対するバイタリティが湧いてくるのか。
今回イェール大学を訪問し、まさしく経済学の勉強に没頭している一人の友人と話をしてきました。そんな中でひらめいたのが、こんなアメリカの大学文化を紐解くキーワード、「自己実現」です。
2-1. 自己実現とは
自己実現というのは、自己の潜在能力を最大に発揮して生きること。人間の欲求を五段階に階層化した心理学者マズローによる『欲求段階説』で、最上位に位置する欲求です。
欲求と言えば聞こえが悪いですが、もっと簡単に言えば、「人の成長に不可欠なもの」と考えればいいと思います。人が成長し成功するためには、初歩的な欲求が満たされるだけではうまくいかない。周りの人に認められ尊敬されることによって自信をつけ、己の潜在能力に対する認識を改め、さらなる成功への野心を持ち、野心が実現して得られる達成感に酔うこと。自己実現は人にさらなる自信を与え、人の成長を大きく増幅、加速させます。
抽象的で分かりづらいかもしれないので、上に述べたコンセプトの一つである「自信をつける」を、自分が好きなサッカーに当てはめてみたいと思います。僕はロンドンのアーセナルというサッカーチームの熱狂的なファンなのですが、アーセナルの監督を務めるベンゲルという監督は、自己実現というコンセプトを非常によく理解している監督だと思います。彼はとにかく、若い選手を覚醒させるのが大得意な監督です。彼は若い選手を、とにかく試合で使い続け、悪い時期もずっと守り続けて起用し続けます。このように使われ続けた若手は、ちょっとずつ自信が芽生え、どこかで本当にメキメキと力を発揮し始めて覚醒します。それも、若手選手の本来の実力ではありえないはずのプレイを見せることもしばしばあります。いわばこの監督は、選手を「Overachieve」させるプロなわけです。ベンゲル監督はたびたび、「本当に実力がある選手というのは、(長期に渡る地道なトレーニングなどではなく)ほんのちょっと自信を得ることによって一気に覚醒するものなのだ」と述べています。こんなふうに人を一気に成長させる糧が、まさしく自己実現なのです。マズローのいうとおり、自己実現を行うことが野心家の欲求だというのも、こんなに大きな心理的な効果を生み出すものなのだから、間違ってはいないと思います。
2-2. 若者の自己実現
自己実現が誰にとって最も大事かというと、それは間違いなく「若者」です。成長段階にある人こそが、成長を加速させるような自己実現を欲しているのは間違いないはず。うまく自己実現を行えず燻っているよりかは、自己実現を行って最大限の能力を発揮している方が間違いなく健康的です。だからこそ、自己実現を行おうとします。
そんな若者ですが、じゃあどんな場所で自己実現をすればいいのか?もちろん、自己実現そのものは、様々な舞台で行うことが可能です。しかし、その人が所属する環境によって、自己実現を行いやすい舞台が大きく異なると思います。そんな自己実現手段の違いが、先述した日本とアメリカの大学の差に現れているのだと思います。
2-3. 日本の大学における自己実現
じゃあ日本の大学における自己実現手段は何なのか?日本の大学では、課外活動を行うことこそが自己実現手段なのだと思います。勉強というのは自己実現手段に入らない。なぜかというと、大学側が提供するものに限度があり、授業や勉強というものに価値を見出せないからです。結果として、人々は自己実現をする場所を外に求める。自分はそう考えています。
2-4. アメリカの大学における自己実現
じゃあアメリカの大学における自己実現の手段は何なのか?
僕のイェール大学の友人が、いい例です。彼も高校時代は様々な哲学に関する課外活動に関わっていたのですが、今の彼は経済学というものの「没頭」しています。経済学の考え方が本当に気に入っていて、自分にすごく合っているのだとか。それだけでなく彼が繰り返し述べるのが、僕も「まだまだだ」だという言葉。経済学をマスターしないといけないし、それだけじゃなく、自分自身が経済学の勉強を通して「もっと成長しなければいけない」。このような言葉を、何回も繰り返していました。自分が泊まったその日も、そんなことを言いながら、朝4時まで図書館で勉強していました。日本の大学生にとっては不思議な話だと思います。勉強することが、自分自身が成長することと非常に強く結びついているわけですね。
上のような発言は、アメリカの大学において、中国人の学生など他の留学生、しまいにはアメリカ人学生からもよく聞きます。アメリカの大学というのは、過酷な勉強を生徒に課すもの。だけど、勉強というものが、学生の自己実現と強く結びついています。大量のリーディングや何ページにも及ぶエッセイをこなすことによって、学生は自信をつけ、自己実現を行っているのではないか。そんな気がします。

(勉強に没頭する学生)
3. 自己実現を行うのに最適な場所
ここまでは日本の大学とアメリカの大学を平等に比較し、それぞれの文化はどんなものなのかを考えてきましたけど、ここからはよりバイアスをかけて、アメリカの大学の良さについて考えてみたいと思います。
3-1. 無理をする必要の無さ
課外活動を行うのは格好いいことです。しかし、キャンパスの外に飛び出すというのは、本職から逸脱し無理をしてまで行う行為です。野心的な人たちは、学校という枠組みから飛び出して自己実現を行うこととなりますが、それには多大なバイタリティが伴います。アメリカの大学ではどうかというと、その自己実現手段が、勉強だったりする。アメリカの大学の良さは、自己実現手段が大学から提供されているため、無理して学校の外に飛び出す必要がないことだと思います。
アメリカの大学の中にはもちろん、「宿題が多すぎる」と半べそをかきながら勉強をやっている人も多いですが、勉強というのはすべての学生に課されるものであるため、すべての生徒が必然的にこの自己実現の世界に巻き込まれています。勉強が多いのは大変ですが、間違いなくすべての生徒が全力を注いでいる環境にあります。そして半べそをかいている学生に、「じゃあ来学期は履修する授業を減らしてみれば?」と聞けば、「それはいやだ」と言われます。嫌よ嫌よも好きのうちみたいな感じで、「来学期も取りたい授業がたくさんあるから授業を5個取るんだ」といった答えが返ってきます。
日本の大学においては、自己実現を行っている人たちは、「意識高い系」と、軽蔑的な意味合いを込めて呼ばれることがあります。学校の中に、頑張って自己実現している人の足を引っ張る文化があったら、それはすごく不健康な世界であると思います。アメリカの大学には、学生が頑張って勉強をする事を奨励し、自己実現を促す健康的なムードがあります。

(「意識高い系」を軽蔑するイラスト)
3-2. 没頭できる環境を提供してくれること
アメリカの大学の学生は、何回でも言いますが、本当に勉強をします。日本の大学生であれば、「この勉強に何の意味があるんだ」ってなって投げ出してしまいそうなところを、アメリカの大学生は、イェールの友達が本当にいい例ですが、夢中になって没頭しています。さっきまで述べたとおりですが、学生がここまで夢中になれるのは、勉強が将来役立つものとして意味付けられているのではなく、今、自己実現するための手段として意味付けられているから。変な言い方ですが、アメリカの大学生は冷静さを欠いている状態、いわば取り憑かれた状態になっているのかもしれない。あるいは、目の前の勉強に執着している状態に陥っているのかもしれません。
だけど、頭が良く要領が良いはずのトップ大学生を、こんなにも狂わせてくれる環境、精神的に麻痺させる環境を提供してくれることは、本当にすごいことです。そのためには、学生の勉強を徹底的にサポートする各種設備、学生を常に挑戦させ続けるためのサポート体制、教員の質の徹底的に底上げするための厳しい監視体制なんかが必須。こんな環境こそが、アメリカの大学の魅力なのだと最近思っています。
目の前にあるものに没頭し、自己実現を繰り返すことで、最後には究極の成功を得ること。それを良しとする学校文化は、アメリカ全体の資本主義文化である、アメリカンドリームと結びついている気すらしてきます。先ほど話したイェールの友達ですが、先学期、なかなかイェールという大学が好きになれなくて悩んでいたようです。その彼に向って、自分がとっさに言った言葉が、すごくよく印象に残っています。「ここまで没頭できる環境を提供してくれること、それこそがイェールの最大の魅力なのではないか」。
3-3. 大学生が最も大学生らしくいられる場所
昨年の秋、ある新聞社さんからのお願いで留学に関する記事を書くことがありました。そこで自分がアメリカの大学に関して端的に述べたのが、アメリカの大学とは、大学生にとっての「natural habitat」であるということです。日本語に言い換えれば、大学生の自然生息地、すなわち、最も健康に生活出来る居場所とでもいいましょうか。無理をしてキャンパスの外に出て自己実現をしないといけない環境、あるいは頑張っている学生を軽蔑する風潮、こういったものに無縁なのがアメリカのトップ大学である気がします。斜に構えて「意識高い系」を批判している人より、与えられたものに夢中になって自己実現している人の方が、何倍も健康的なのは明らかなはず。言い換えれば、大学生あるいは思春期の学生が、最も学生らしくいられる場所、最ものびのびと能力を発揮できる場所。そんな場所がアメリカの大学なのかな、と考えています。
3-4. 大学改革などに関して
もしこの記事を読んでいただいている大人の方がいらっしゃったら、この話をどんなふうに実用的に活用するか、考えるかもしれない。そんな中で思いつくのが、自分が在籍していた東京大学が率先して行っている、日本の大学改革です。
大学を外から眺めている大人はとにかく、「日本の大学生は勉強しない」と言います。第一に理解すべきなのは、自分が東大時代にすごく実感したのですが、勉強しないというのは一種の悪循環によって生まれた「学生文化」であるということ。
A. 教授の講義が面白くないから、学生は勉強したくなくなる。
B. 学生にやる気が見られないから、教授もやる気を失い、独り言を呟いているかのようなつまらない講義だらけになる。
(以下AとBの繰り返し)
大学サイドから見ると、「生徒が勉強しないこと」が問題であっても、学生サイドからすると、「授業がつまらないこと」が問題となっている。そして、どうせすべての授業がつまらないのなら、授業を真面目に受けるより、良い成績を収めやすい授業を履修したくなる。生徒全員に良い点数を与えるような、「優しい」教授の授業を取りたくなる。一部の人しか知らないかもしれませんが、こういった学生文化が集積して誕生したのが、東大を象徴する各種の学生文化です。
1. シケプリ(試験プリント):短期間の勉強で試験を乗り切るために生徒間で流通する、まとめノート
2. シケ対(試験対策委員):クラスの中で特定の一人を試験対策委員として授業に出席させ、他の人は授業に出ない文化
3. 『逆評定』(本の名称):単位をくれやすい「優しい」教授をまとめた評定本。生徒はこの本を読み、教授が「優しい」かどうかを確認した上で、履修を決める。
もう一つ大人が理解する必要があるとしたら、大学生も若者であるということ。すなわちは、もっと認められたい、褒められたい、頑張りたい、そんな自己実現の精神で動くものだということ。上のような学生文化は、勉強というものが自己実現と全く結びつかず、勉強というものの序列が低下する結果を招いています。仮に学生に勉強させたいのならば、勉強が自己実現と結びつくような環境を作り上げないといけない。
しかし、政治的に作り出せる環境だけでは足りないのもまた事実。生徒に勉強をさせようということで、授業時間の延長や、一限授業開始時間の前倒しが行われようとしています。その改革に対して周りの大人は理解を示しても、当の東大生からは非難の嵐。東大秋入学などについてメディアで騒がれた時期もありましたが、当の東大生や東大教授などから反発を招き、計画は破綻しました。
人類学を専攻している人らしい発言かもしれませんが、政治的に作り出せる環境には限界があります。究極的には、大学の環境や学生の価値観、これら全てを内包した「文化」そのものにメスを入れていかねばならない。「文化」そのものを変革していって、学生の自己実現の中心に勉強が来るようにしなければいけない。そんな気がします。
今回の話はずいぶんと長くなりましたが、このあたりで締めさせていただきます。アメリカの大学生が、異常なバイタリティによって突き動かされている姿は、昨年2月の記事でも述べた通り。一年間もこちらに暮らして、ポモナとブラウンという二つの名門校を知るようになった今、アメリカの大学に対する理解がずいぶんと深まったかと思います。今回の記事、最近の他の記事と比べて随分と長文になりましたが、それだけアメリカの学生文化が不思議で、自分も頻繁に考えているテーマだということが、ちょっとでも伝わってくれれば幸いです。
|
|
この記事の先頭へ戻る
◇ 2015年2月 人類学と近況報告
◇ 2015年1月 ハーフ
この記事を折りたたむ
|
◇ 2015年1月 ハーフ
昨年ポモナで視聴した、ICUの交換留学生に紹介されたドキュメンタリー映画が印象に残っています。映画の名前は『ハーフ』。今回は、日本人の外国人に対する意識について話してみたいと思います。映画『ハーフ』の中でも垣間見える、日本社会の未熟さについても、考えられればと思います。
1. ドキュメンタリー映画
1-1. 『ハーフ』
1-2. 日本のハーフの潜在的な多さ
2. 見下す風潮
2-1. 見下す風潮のメカニズム
2-2. 周辺国を下等国家に仕立てるやり方
3. 過剰反応
3-1. 温泉で
3-2. 日本語がカタコト喋れただけで
4. 結局は母国人じゃなければ難しい国
おわりに
1. ドキュメンタリー映画
アメリカに来てから、ドキュメンタリー映画を見る機会が増えました。昨年ポモナで履修していた環境学の授業二つにおいて、合計5本くらいドキュメンタリー映画を見た覚えがあります。アメリカの大学では、社会問題を伝えるメディアとしてドキュメンタリー映画の重要性が語られていて、ドキュメンタリーの話術(narrative)について実践的に学ぶ、ドキュメンタリー映画制作クラスも提供されています。それだけでなく、僕がポモナでアルバイトしていたアジアのドキュメンタリー映画を保管するPacific Basin Instituteというアーカイブセンターでも、ドキュメンタリー映画制作を奨励していました。このアーカイブセンターでは、毎年5人、ドキュメンタリー映画を制作する生徒に奨学金を支給し、ビデオカメラを初めとしたあらゆる機材を貸してくれます。アジアの諸地域でインターンしながらドキュメンタリー映画を制作するといった感じで、気軽にドキュメンタリー映画を作る事ができます。
最近はこのようにドキュメンタリー映画を見ることが増えたのですが、その中でも印象に残っているのが、『ハーフ』という日本映画です。
1-1. 『ハーフ』
内容と同じ上記の題名を冠するこの映画は、ハーフの女性映画監督二人によって作られた作品です。背景や年齢、性別がバラバラのハーフ5人の人生に迫り、1年以上にわたって取材し続け、エスノグラフィックな手法でハーフの人生を描いた映画です。以下はこの映画に出てきた内容とともに、外国人が日本に行った時に何を感じるのか、聞いたことを中心に書いていきます。

(ドキュメンタリー映画『ハーフ』)
1-2. 日本のハーフの潜在的な多さ
自分が小学校にいた時は、いた小学校のせいもあったのかもしれませんが、ハーフや外国の生徒はほとんど見かけませんでした。唯一あるとすれば、中国系の友達が何人かいたことです。そのうち一人は、いつも嫌がらせを受けていました。しかし高校時代の友人によると、彼は小学校時代、周りをフィリピンや南米系とのハーフに囲まれていたそうです。事実、映画で示されたデータによると、現在、新生児の49人中1人が日本人と外国人の間に生まれているそうです。移民をより多く受け入れようという政策の下、恐らくは今の小学生の間だと、ハーフや外国人の学生がいるのはもっと普通なのではないでしょうか。
2. 見下す風潮
同時に多いと思うのは、こういったハーフの人に対して、排他的ではないのですが、見下すような光景。小学生ならば、肌の色が違ったり言葉が喋れなかったりでイジメられることもあるでしょう。ただそれ以上に思うのが、日本社会(小学生なら親社会)の中に存在する、外国人を見下すような風潮の存在。韓国、中国はもちろんのこと、フィリピンなどの東南アジアや、ベネズエラなど南米から来た人であっても、日本の中には、日本より発展が遅れている地域から来た人たちだという、見下す風潮があると思います。逆にアメリカやヨーロッパの白人でこれが起こらない矛盾は、中国にいる最中に書いた2014号8月号の記事の通りです。
2-1. 見下す風潮のメカニズム
上のような差別的な発想は、日本が世界随一の先進国を自負しているから生じる考えなのだと思います。社会や文化がどれだけ発展してるかは全く未知数ですが、少なくとも経済的な指標は、日本が世界随一の先進国であることを示している。日本の教科書では、日本のGDPが世界第三位である事を強調しますよね。日本に出稼ぎに来る人は、日本より劣った国から金を稼ぎに来ているんだ!というロジックに至る人も多いと思います。日本が世界随一の先進国なのだと信じることで、特に東南アジアや中国、韓国といった他のアジア諸国を見下す人も多いのだと思います。
2-2. 周辺国を下等国家に仕立てるやり方
自分は最近、日本の義務教育期間中にあそこまで世界のGDPランキングを見せられるのは、もはや愛国教育な気がしています。GDPは国を計る手段の一つですが、それが全てではない。まあこのような教育も、日本という国に誇りを持たせる手段なのかもしれません。日本を敵国に祭り上げることによって自国のナショナリズムを保とうとしている韓国や中国の愛国教育を批判するのならば、間接的に日本以外のすべての国を下等国家にしたてている日本のやり方も、仮に社会的軋轢を生み出す要因になっているのならば、批判されるべきであるような気がします。

(GDPという指標を用いて愛国心を煽るのは、中国も一緒。上のグラフは、中国が日本のGDPを抜いた事を祝福しています。)
3. 過剰反応
このように外国人に対する日本の姿勢について語るときに、差別について語るのは誰でもできると思います。ではここでしたいと思うのが、留学生だからこそ気づく、過剰反応という現象についてです。話は簡単で、日本人は外国人に対して過剰反応をしがちなわけです。自分はアメリカの大学での立場上、日本語クラスのTAなどを務め、日本に興味を持っている外国人の友達がすごく多いです。以下にあげるのはそういった人の多くが日本で経験した、不快or不可解な出来事です。
3-1. 温泉で
中国人の友達が白人の友達と一緒に日本の温泉へ行った時があったとのことです。その時、白人の友人が一人温泉をうろちょろしているだけで、他の日本人客の視線は白人に釘付けになります。日本人としてはそうなるのは分かりますが、日本へ来た外国人にとっては、話しかけてくれるなら良いものの、話しかけもしないのに視線を感じるのは薄気味悪いもの。この後は当人の思い込みの可能性もありますが、なんと同じ温泉に浸かっていた日本人客が一人また一人と湯を上がって、最後にはその二人だけが取り残されたそうです。「ガイジン」が入ってきて緊張感が高まり、過剰に反応して逃げて行ったのではないかと彼らは言っていました。
ここで外国人が何よりも思うのは、外国人をなぜそんなに特別扱いしなければならないのかということ。日本文化への憧れがある場合は特にそうですが、普通の日本人として扱ってもらうことが外国人の願い。このエピソードにおいて、日本人客が誰も中国系の友人に注目していないことも、また皮肉な話です。気づかなかったといえばそれまでですが、人種によって外国人同士を差別している点も、外国から来る人をさらに苛立たせることが多いようです。例えば、肌の色が濃い人にとって、日本はなかなか住みにくいと思います。

3-2. 日本語がカタコト喋れただけで
これは日本人が全く理解していない、日本訪問者の悩みの種です。この類のエピソードは、結構多くの日本訪問者から聞いています。
日本においては、外国人(肌の色が違うなど、明確な外国人)が「こんにちは」など片言の日本語を喋っただけで、びっくりする仕草をして「日本語上手ですねぇ!」と返す人が多くいます。これは日本を訪問している人が不快に思うことが非常に多い。何年か大学で日本語を学んでいた人にとっては、「こんにちは」と言えただけで日本語が上手いと言われたら、相手がそれだけ自分が日本語出来ないだろうと見下していたと捉えかねません。日本人からすれば一種の礼儀として言っているのですが、余計なお世話。差別ではないものの、こういった過剰反応は、外国人に対する社会の意識を示すとともに、外国人にとって日本の居心地の悪さも表していると思います。
そしてこの現象も、仮に中国系の友人が上手い日本語を話したとしても、日本人だと勘違いするだけで、誰も反応しませんよね。あるいは、日本に長く住んでいる中国系や韓国系の人はそもそも多いので、中国系だと分かったところで新鮮味もない。ここにも差別が見られます。
4 結局は母国人じゃなければ難しい国
悲しいことですが、日本への訪問者が最終的につぶやく言葉で、以下のような言葉を聞くことが結構あります。「日本はサービスもいいし飯も上手い。"But I never felt it was my home"(居心地の良い場所=家と思えたことは一度も無い)」。日本において、訪問者は、余所者というアイデンティティを築くことしかできないということですね。日本人は英語をしゃべれませんし、そもそも日本語を喋れないと生活できない国。昨年冬、ポモナの環境学の教授と日本を旅行した時、引退後は日本に住みたいかと僕が聞いでみたのですが、「素晴らしい場所だけど、自分が住める場所ではないと思う」と言っていました。この返答には、まさしく上に述べた感情がこもっていた気がします。
おわりに
今回は、日本人の外国人に対する意識に関してお話をしました。そもそもなんでこんな話をしたいのか?それもなぜ、日本の問題点だと語りたいのか?それは日本という社会が、外国人を受け入れる包容力を持ち合わせていないから。ドイツやフランスは様々な移民問題を抱えていると言いますが、ここまで外国人の流入が進んでいなかった日本は、移民問題というたいそうな問題を持つ段階にすら至っていないのではないか?言葉を変えれば、日本がこういう問題に直面するのは、これからなんじゃないかと思っています。
かっこいい言い方をすれば日本批判みたいな話を、二月連続でしました。その中には、伝えたいメッセージがもう一つあります。「ぶっちゃけ、日本はそんなにすごい国じゃないよ」というメッセージです。外国に旅立った日本人留学生だと、これと真逆の印象を持つ人も多いですしし、留学ブログにはあんまり見られない考え方かもしれません。最近はCOOL JAPANといった言葉も人気で、メディアや浅はかな研究者が様々なことを取り上げています。そんな中であえて対立するような情報を出して、日本はあくまで世界中の一つの国に過ぎないと人へ伝えたい・・・。最近の自分はそんなことを思っています。他国が発展し人口も増加するのなら、日本は相対的に小国となり、広大なグローバル世界の一つのプレーヤーに成り下がっていきます。しかし北欧諸国のように、そんな立場においても輝きを誇っている国はたくさんある。なんか日本のちょっと保守的でナショナリズムチックに推移している様子は、それが微かなものであっても、中国へ留学しアメリカへも留学している自分にとっては、どこか薄気味悪いものにしか映りません。
|
|
この記事の先頭へ戻る
◇ 2014年12月 アメリカの男女平等について
◇ 2014年11月 アメリカの大学と健康問題
◇ 2014年10月 Independent Concentration?
◇ 2014年9月 総合大学とリベラルアーツ
◇ 2014年8月 ガイジン
この記事を折りたたむ
|
◇ 2014年8月 ガイジン
こんにちは。中国での生活もずいぶんと慣れて、最近は毎日、本当に楽しんでいます。自分が参加しているPrinceton in Beijingは非常に大変なので、休む間もなく自分を苦しめている人もいますが、成績以上に初めての中国を満喫する方が大事だろう!という気分で、出来るだけ外出するような日々を送っています。
さて、そんな中国での生活ですが、未だにどうしても気にかかることがあります。それは中国の現地の人、例えばタクシードライバーや道端の人と話すとき、自分という外国人をどう紹介すれば良いのか、という問題です。中国人と雰囲気が似通っている日本人が、ガイジンとしてどんな風に自分を紹介するべきか、なかなか難しい部分があります。今回はそんな話から始め、ガイジンという歪んだ概念について考えていきたいと思います。
1. 中国で生活する日本人として
1-1. アジア人のみの時
1-2. 白人と一緒にいるとき
1-3. 日本人だと述べたとき
2. ガイジン
2-1. 自分にとって初めての第三国
2-2. 「ガイジン=白人」という偏見
2-3. 「ガイジン=英語を話せる」という偏見
3. 社会の発展
雑感:日中関係について
1. 中国で生活する日本人として
問題は単純です。自分は東アジア人である上、Princeton in Beijingでの規定上中国語しか話せないため、ぱっと見、中国人だと誤解されます。そのため、商店でものを買う時も、町中で道を聞く時も、人々は自分のことを中国人だと思って接してきます。
1-1. アジア人のみの時
さて、自分が独りで歩き回っている場合、あるいはアジア系アメリカ人や韓国人の友人らと歩いている場合、当然、中国人だと思って人々は接してきます。もの凄い勢いで中国語をまくしかけてきますし、聞き取れずにもじもじしていると、(これは中国の雰囲気ならではですが)怒ったような態度で接してきます。
1-2. 白人と一緒にいるとき
しかし、自分が白人の友達と一緒に歩いていると、現地の人の接し方は当然のごとく変わります。白人と一緒に歩いているとなると、道端でも、興味深く覗き込んでくる人が多くなります。明らかに外国人である白人と一緒に歩いていると、自分の中国語のアクセントにも気づき、自分も留学生であることに気づく人が現れます。
このようにして自分が外国人だと分かるとどのように接してくるか?日本人が「ガイジン」に接するときほど丁重ではないと思いますが、中国の人も、なんだかんだ言いながら興味とリスペクトをもって接してくる気がします。
1-3. 日本人だと述べたとき
1-1のケースに戻り、あまりにも相手がまくしかけてきて聞き取れないので仕方なく、「自分は中国人ではなく留学生だ。ゆっくり話してくれ」と言ったとします。当然のごとく、相手方は「じゃあお前はどこの国から来たんだ?」と聞いてきます。この時、「日本人だ」と素直に答えると、あんまり良い思いはしません。政治的な対立が顕著ですし、特に老百姓(中国の一般人を指す名称)の反日感情は、強いことが多いです。
そこで「アメリカ人だ」と答えるとします。自分は英語が母語のようなものですし、アメリカの大学に通っているので、間違ってはいない気がします。しかしここがポイントなのですが、大抵の場合、信じてもらえません。相変わらず怒ったような態度で「どう見てもアメリカ人に見えないだろ」と一笑されます。いわば、「アメリカ人=白人」というステレオタイプが成立しているため、通用しないわけですね。
「韓国人だ」と答えるのは一つの手段です。朝鮮半島の人は国際的だなあといつも思うのですが、北京にもたくさんの韓国人あるいは朝鮮族(中国の少数民族)の人が暮らしています。しかし、韓国の人はあまりにも多いし、韓国文化は中国にあまりにも浸透しています。韓国映画や歌曲の話などを振られて、面倒くさいことが多いです。
こんな初歩的な例ですが、この中に垣間見えるのは、老外(日本でいう「ガイジン」のような、外国人をひとくくりにした言葉)という概念の歪みです。日本でも「ガイジン」という形で外国人をひとくくりにして呼ぶことは多いですが、ここには思わぬ差別的な意味合いや、思わぬ偏見・ステレオタイプが含まれていることが多いと感じています。

(中国の大都市、青島で見かけた釣具屋さん。「釣魚島」という釣具屋さんの名前は、尖閣諸島の中国語名です。お店の看板には中国の国旗のデザインがなされています。いくら冗談とは言え、日本だと許されない行為ですよね。)
2. ガイジン
中国に来て感じたことの一つは、この「ガイジン」という概念の不思議さです。ここからはこのガイジン(中国語では「老外」)という概念について探求していきたいと思います。
2-1. 自分にとって初めての第三国
自分自身がこの「ガイジン」という概念を理解し始めたのは、中国に来てからです。アメリカは移民大国で、外国人という存在を包容することには非常に慣れている気がします。以下に述べるような経験をアメリカでしたことはほとんどありませんでした。日本は自分の母国なので、そこで「ガイジン」としての経験をすることはありません。イギリスやノルウェーに住んでいた経験もありますが、これらは家族と一緒に暮らしていたので感じなかったのかもしれません。
2-2. 「ガイジン=白人」という偏見
まず間違いなく、中国と日本の双方で存在するのは、ガイジンと言えば白人の人であるというステレオタイプが存在することです。中国には多くの韓国人や東南アジア人、日本にも多くのアジア人がいるのに、彼らが「ガイジン」の枠に当てはまることは少ないですし、見た目がアジア人の彼らが外国人であることを理解出来ない人が多いと思います。
さらにひどいのは、このような形で、外国人の間に自然と階級が出来てしまっていることです。白人は「ガイジン」として最初から見られ、なんだかんだ言いながらリスペクトの対象となります。反面、肌の色が黒い人であると「銃を持っている危険な人」なんていうステレオタイプが中国に存在するらしいです。事実、黒人の友達と一緒に歩いている時の中国の人たちの反応は、また異なるものがあります。日本においても肌の色が黒ければ良い印象は持たれません。ポモナを卒業し、現在は北京で仕事をしている白人の友人がいるのですが、中国において「自分が白人でどれだけ得をしたか」について、彼は話していました。
東南アジア人などでも同じでしょう。日本にいる東南アジアの人は、「ガイジン」と見られないどころか、犯罪者や不法移民のような扱いをされると思います。Princeton in Beijingの親友は、インドネシア人とベトナム人の留学生なんですが、彼らが日本に来て彼女を探したいと自分に言ってきました。それに対して自分が率直に思ったのは、厳しいのではないかということです。彼らは本当に優秀でコミュニケーションも上手い奴らですが、日本だと間違いなく、国籍を聞いただけで少し腰が引けてしまう女の子が多いと思います。結婚するとなったら、両親が反対するでしょう。出身国だけで差別を受けるとは、冷静に考えれば恐ろしい社会ですが、日本は未だにそんな世界です。
2-3. 「ガイジン=英語を話せる」という偏見
「ガイジン=白人」と同頻度で見られるのが、「ガイジン=英語を話せる」という偏見です。こんなことを言ってしまったら、フランス人が黙っていないのは誰でも分かることだろうと思いますが、こんなステレオタイプは間違いなく存在します。
先ほど述べた友人ですが、彼は最近、中国の農村を理解したいからということで、農村地帯で就職活動をしていました。そんな彼が言ったのは、中国において、「肌の色さえ白ければ」、誰でも英語教師になれるという現状です。実際に英語が話せるかなど問題ではありません。「肌の色が白い=ガイジン」、「ガイジン=英語を話せる」、すなわち、「肌の色が白い=英語を話せる」という三段論法が、一般人の間ではまかり通っているようです。

(上に述べた話、中国だからあてはまるのだと考えるかもしれないですけど、この写真を見て下さい。上の白人の先生、実は英語を話せないというケースも考えてみて下さい。白人の先生の代わりに、アジア人の先生がいる場合も考えてみて下さい。写真は中国のものですが、肌の色さえ白ければ英語を教えられるだろうという感覚、日本にも存在するのではないでしょうか?)
3. 社会の発展
先述の友人ですが、中国に対して、以下のような印象を持っているそうです。「中国は文化も歴史も面白いし、本当に魅力的な国。しかし、経済だけでなく、社会も発展途上にある国だ。」社会の中には、未だに外国の人を受け入れるような土壌が整っていない上、「人種差別禁止」といった現代的な社会思想も、未だに社会には浸透していない。政治や経済と切り離された「社会」というものは、未だ発展途上であるという事ですね。
しかし自分が思うのは、中国のこんな例は全て日本にも当てはまるということ。先ほど述べた通り、日本にも「ガイジン」という用語に隠された差別が存在しますし、外国の人や文化を受け入れる土壌が全く整っていません。よりグローバルな社会を目指す日本の教育機関・市町村・国家の方針に、社会の改革が追いついていない状況にあります。
さらに思うのは、「社会」の発展度合いという視点から述べると、日本はそもそも先進国ではないのではないか?ということです。海外へ留学した人は気づくことが多いのですが、先進国の中で、ここまで男女不平等な国はなかなかありません。人種差別は「ガイジン」の例を見れば顕著に見られますし、身体に障害がある人が一般人と交じって生活するのは、未だに難しいでしょう。同性愛や性同一性障害に関する理解も、アメリカと比べるとまだまだだと感じることが多いです。
日本の欠点というのは、誰の目にも明らかな部分にはなかなか存在しません。しかし最近自分が思うのは、社会の未熟さなど、こういった陰に隠れた部分にこそ、日本の欠点が多くあるんじゃないかと最近の自分は感じています。
今回はこんな感じで締めておきます。9月はブラウン大学でのオリエンテーション期間なので、忙しくて更新できないか、8月末、ブラウンへ渡る前に更新することになるかもしれません。それはともかく、9月初頭にでもまたお会いしましょう。

(中国では、こんな最新鋭の新幹線が走っています。しかし社会の発展というのは、経済の発展とは切り離された場所で、少しずつ少しずつ進行していくものです。)
雑感:日中関係について
中国においては、先ほど述べた通り、政治的な対立から自分の事を「日本人」だと言いづらいと思います。中国に来てから日中関係について考えることが多くなり、8月号はそれについて述べようとも思いましたが、政治的でシビアな内容なので、やはりやめることにしました。一言で言うとしたら、日中関係というのは考えれば考えるほど難しい問題で、「何人死んだか」「日本軍は何を行ったのか」という事実関係が日中関係に与えている影響以上に、人々のちょっとした心理や社会環境が与えている影響の方が難解で深刻である気がします。政府のちょっとした声明や行動によって、人々の危機感が煽られ反発を招くなど、ちょっとした誤解の連鎖が問題の深刻化に一役かっています。そして、お互いの政府が、様々な政治的要因から、そのような心理を煽っているわけですね。
僕の知っている中国人は口を揃えて、「日中外交問題というのは政府と政府の問題であって、人と人の問題ではないよ」と言います。政治体制と人々を別物として考える、中国の人らしい考え方であると同時に、非常に的を射た捉え方だと思います。
|
|
この記事の先頭へ戻る
◇ 2014年7月 コミュニケーション文化
◇ 2014年6月 ポモナカレッジとは?
◇ 2014年5月 ポモナ休学の決断:奨学金との戦い
◇ 2014年4月 アメリカに対する畏敬の念
◇ 2014年3月 外から母国を眺める意義
◇ 2014年2月 ストレス
◇ 2014年1月 アメリカの教授たち
◇ 2013年12月 自由の意義
◇ 2013年11月 思考の軸
この記事を折りたたむ
|
◇ 2016年11月 思考の軸
なぜ勉強しないといけないのか?高校生の頃は、それが根本的に分からなかったと思います。僕以外の多くの高校生も分からなかったと思います。とりあえず受験の為に勉強をしますが、受験のための勉強がどのようにして将来の仕事に繋がるのかはよく分からない。考え過ぎてしまう人であれば、自分の人生に繋がらないからと言って、勉強をする気が起きなくなってしまったと思います。(校風もあると思うのですが、僕の母校は特にそういう人が多かったと思います。)
今回は、こんな話から始めていきたいと思います。アメリカに来て気づいた学問の意義、学問を通じて獲得する思考の軸などについて、述べていきます。記事の最後には、番外編として、Admission Officeの方と対話した時に気づいた内容に関しても書き留めておきます。
1. 学問の意義
1-1. World Scholar’s Cup
1-2. 考え方を学ぶこと
1-3. 本居宣長
1-4. 深みのある学問
2. 様々な学問と、様々な視点
2-1. 一例:都市計画において
2-2. ビジネス世界において
2-3. リベラルアーツで何を得るべきなのか?
2-4. 留学生を受け入れる理由
番外編:Admission Officeの裏事情
1. 高校のレベルというものの概念
2. 留学生向け奨学金の実情
3. 海外での大学プロモーション
1. 学問の意義
「俺のPassionはBiologyにある」。昨年アメリカの大学受験の準備をしていた時、ある東海岸の工科大学のウェブサイトに、こんな発言が載っていました。これはある生徒の言葉。このような発言は、アメリカではよく耳にします。実を言うと、昨年、こういった言葉を見る度に、「自分はアメリカの大学に向いていないのでは・・・?」と疑心暗鬼に陥っていました。自分のPassionがどこにあるかなど知る由も無かったし、それどころか、学問が好きという自覚が無かったからです。当時の自分にとって、勉強意欲に満ちた生徒がまるでプロパガンダのように襲いかかってくる大学ウェブサイトは、ホラーステージの一つでした。こんな「勉強大好き!」な生徒を見て、「そもそも大学なぞ行かずに、とっととビジネス社会に出たほうが良いのでは・・・」などと、自信を失っていました。
1-1. World Scholar’s Cup
2016年1月号のブログ記事に書いた通り、ポモナやブラウンでは、行きたいと思う国へ赴いて自由に仕事をするアメリカ人の学生に、たく上で述べた話についてもう少し書いても良いのですが、本題ではないので、割愛したいと思います。さて、上のような考え方が少しずつ変わってきたのは、高校三年生の頃、World Scholar’s Cupというリベラルアーツをテーマとする世界大会に関わった時から。「人はなぜ移住するのか」など、毎年、特定のテーマがあります。そのテーマに沿って、Science、Art、Music、Historyなど、10科目のテキストが作られ、それぞれのテキストがそれぞれの視点からそのテーマについて分析します。「人はなぜ移住するのか」というテーマであれば、Historyがユダヤ人の強制移住を取り上げ、Artがボスニア内戦により故郷を追われる人々の絵を題材とし、Scienceが気候の寒冷化に伴い人口が流出したグリーンランドを扱う、などといった感じです。
この大会に向けた勉強は非常に楽しかったです。なぜなら、今後の人生に繋がるような、様々な「考え方」を学ぶ事が出来るから。

(World Scholar’s Cupは、世界規模で開催されている、中高生向けのアカデミックな大会です。)
1-2. 考え方を学ぶこと
この大会が僕にとって、アメリカのリベラルアーツとの最初の接点でした。「考え方を学ぶ」という表現こそが、リベラルアーツを端的に示したものであると思います。リベラルアーツの意義は、社会を生きる中で直面する様々な問題を解決する能力、Problem Solving Skillを学生に植え付けさせる事。そして学問の意義は、様々な学問分野における「考え方」を学ぶことと、リベラルアーツ教育は捉えています。
1-3. 本居宣長
僕の麻布のある先輩は、「法学が、自分のあらゆる思考の根幹」と表現していました。彼は本当に面白い人で、東大の法学部にも所属していたOBでもあります。彼いわく、彼は社会の様々な事象を、「法学」というスケールにのせて判断すると言います。彼が強調したのは、自分の思考の軸となる、ある一つの学問を極めるのが重要であるという事。すなわち、「考え方」を熟知している学問を一つ持っている事こそが、非常に重要であるという事ですね。
ここで僕が思い出すのは、江戸時代の国学者、本居宣長の著書である『うひ山ぶみ』。本の中で繰り返し述べられていたのは、ある一つの学問を極める事によって、始めて、異なる学問に手を出す事が可能になるという意見。ある学問を極める事によって、その学問特有の「考え方」を学ぶ事が出来、以降の学問を探求する上でも、その「考え方」を頼りに辿って行けるからだと述べています。
1-4. 深みのある学問
僕の意見ですが、「考え方」が最も顕著に現れる学問と言えば、歴史学である気がします。歴史をしっかり学問として勉強すれば、あらゆる事象や問題を分析するとき、「歴史的にどのように変遷してきたか」「それらはどのような現象の影響を受けて生じたのか」などといった、歴史的思考力を応用する事が出来ます。これは非常に分かりやすい例だと思います。僕自身、高校時代、受験のために世界史を勉強していたため、歴史的な考え方に触れる事が出来ているのだと思います。
しかし、「考え方」をしっかり学ぶ事が出来る学問というのは、本居宣長が言うような、学問として極め甲斐のある、深みのある学問でないといけない気がします。最近僕が少しEnvironmental Analysis(環境学)に関して懐疑的なのは、環境学というのは歴史が浅く、どちらかというと実用的な学問であるという事。深みのある学問で、「考え方」を享受できる学問でない気がする訳ですね。事実、環境学を専攻する人にも様々な人がいます。10月号で述べた通り、彼らは自らの力で行動を起こせる凄い人たちが多いのですが、テレビで見たホッキョクグマが可哀想だったから、動物が可愛いからなどと、浅いモチベーションの人もいる。最近は、ポモナのまた別のInterdisciplinary(学際的)な専攻である、Linguistics & Cognitive Scienceという専攻を考慮に入れています。言語学・認知科学とでも訳せば良いでしょうか?言語学や心理学、哲学など、様々な歴史ある学問を横断する科目です。

(歴史教育の中では、歴史的思考力というものが、常に意識されています。)
2. 様々な学問と、様々な視点
さて、学問は様々な「考え方」を学ぶものであるなら、様々な学問に卓越した人々が集まったコミュニティはどうなるのか?様々な「考え方」が入り混じり、異なる視点から事象を見る事が出来るので、非常に生産的なグループが出来上がるのは間違いないでしょう。異なる視点をもたらせるとは、具体的にどういう事なのか?
2-1. 一例:都市計画において
「都市の意義」とは何か、多くの方面から議論がなされます。アートの世界では、多様な人が行き交う都市は、様々なアイデアが融合し、クリエイティブな発想を生み出す効果があると言われます。反対に、現在僕が履修しているEnvironmental Analysis(環境学)の都市に対する視点とは何か?環境学の視点で都市の意義を上げるとすれば、それはエコロジカル・フットプリントを下げる効果があるという事。エコロジカル・フットプリントというのは、人間活動が環境に与える負荷を、資源の再生産及び廃棄物の浄化に必要な面積で表した値。低ければ低いほど、環境負荷の低さを実現できるわけですね。都市において、人々は集住するため、熱エネルギーを共有します。職場に近接するため、交通にかかるエネルギーを抑える事もできます。エコロジカル・フットプリントを抑えるメリットこそが、環境学の視点から考えた、都市のもたらす大きな意義であるわけです。
町づくりというのは、様々な科目を横断するテーマです。アートのバックグラウンドを持っている人も、環境学のバックグラウンドを持っている人も、両方携わります。東北の被災地復興に向けて、工学の人は「防潮堤建設」、文化人類学の人は「防潮堤撤廃」を主張するのを見ると、様々な立場の人が異なる意見を発信する事で、議論が活発になっている様子が見て取れます。政治学、歴史学、環境学など他にも様々な視点が加わる中で、より生産的で住みやすい都市を作り上げる事が出来ます。
2-2. ビジネス世界において
さて、異なる視点・考え方をもたらすことが出来るというメリットは、ビジネスの世界において非常に重要です。ポモナには、3-2 Pre-engineering Programという、ポモナで3年間、カリフォルニア工科大学で2年間過ごすプログラムがあります。先日、このプログラムのOBが学校に訪問したので、ソファに座ってのんびり話をしてきました。このOBは、プログラム卒業後、ウォール街の有名な金融機関に3年間勤め、ハーバードのビジネススクールに通います。MBA取得後、カリフォルニアに帰還し、独立して金融機関を起ち上げました。
そんな、いかにもビジネス世界で活躍した彼は、3年間ポモナで学んだリベラルアーツの経験こそが非常に貴重だと述べていました。世の中には、大学の学部で4年間、ひたすらビジネスマネジメントを学んできた社会人が腐るほどいます。就職の際、そのような人の多くと差別化することが出来たと言います。それはなぜかというと、企業の側も、リベラルアーツ教育を通じてしっかりProblem Solving Skillsを学んできた生徒を重んじるから。ビジネスの世界が本当に必要としているのは、ただ椅子に座ってマネジメント作業を出来る人ではなく、日常に直面する様々な課題に対して、多様で柔軟に対応する事が出来る人。明確な「考え方」を持ち、思考の基準を持っている人。彼は最後に、印象的な言葉を残しました。「ビジネスの世界で活躍出来るのは、金融やマネジメントを学んできた人ではなく、人一倍意欲的で、人一倍協力的で、人一倍コミュニケーションに長け、人一倍問題解決能力がある人だ」。リベラルアーツ教育で得た「考え方」こそが、ビジネスは、非常に重要なわけですね。
2-3. リベラルアーツで何を得るべきなのか?
リベラルアーツ大学と言えば、将来、何をしたいか分からない人が集まると言うイメージがあると思います。それは一部、事実ではあるでしょう。しかしリベラルアーツ教育においては、様々な学問を探求し、それぞれの学問の「考え方」を学ぶことができます。探究の結果、自分が最も気に入る学問を見つけたならば、その学問を専攻してじっくり学ぶ事で、己の思考の軸にすることができます。このプロセスは、非常に充実したもの。現在、ポモナの学生は皆、来学期どの授業を取るかわくわくしながら考えていますが、そんな所にこの楽しみが表れていると思います。
2-4. 留学生を受け入れる理由
アメリカの大学が留学生を受け入れる一つの理由も、上のような理由です。留学生は異なる文化的バックグラウンドを持つため、「考え方」とは少し違うものの、異なる視点をコミュニティにもたらすことが出来ます。これがビジネスの向上に役立つように、学問の向上にも役立つという考えが、リベラルアーツカレッジにはあるわけですね。

(留学生同士で週末に合宿へ行ってきました。人種やアイデンティティに関するディスカッションをする中で、国籍の違う相手からは、びっくりするほど異なる思考が飛び出してきたのを、よく覚えています。)
番外編:Admission Officeの裏事情
さて、10月号で予告していた通り、Dean of Admissionとの対話内容に関して、今回の記事で述べたいと思います。きっかけは、今年のClass of 2017のInternational Students(留学生)が全員、ポモナで最も豪華な客室に招待されて、Admission Office(受験生の応募書を見て、大学への合否を決める部署)のトップと一緒に食事をした時の事。Admission Officerの人の話が非常に面白かったので、居残って1時間ほど、ずっと1対1で話を続けていました。
1. 高校のレベルというものの概念
日本の高校から受験する場合、日本人生徒は高校受験を経ているため、己の高校のレベルが高ければそれは評価されると信じている。しかし、Dean of Admissionの口から聞いた話なのですが、アメリカの大学のAdmission Officeは、中学や高校のレベルなどというものはほとんど考えないとの事です。すなわち、開成でも麻布でも、他の学校と一緒と同然に扱われる事が多いという事ですね。
なぜ?と日本人は思うかもしれない。開成や麻布にいる生徒は、それだけ優秀だと思うのが多くの日本人だと思います。しかし、アメリカでは違う。大学はともかく、中高で良い学校に行けるのは、親の教育意識や教育資金など、子どもの周りの環境に依存する事が大きいと言います。実際の所、僕も小5の始めにノルウェーから帰ってきて、よく分からないまま問答無用で受験勉強していました。麻布に入ったのは、母親がそうさせたかったという要素が非常に強いし、多くの生徒がそうだと思います。10歳の子どもが、良い学問を得る事の意義を見出せるとは、到底思えない。親が良い教育をさせたい部分が強い訳ですね。
麻布のような高校にいると、自分の高校以外には面白い・頭が良い人が存在しないかのように、生徒の間では話されます。しかし実際の所、課外活動などに関わってみると、他の学校にも素晴らしい奴らが一杯いることに気づく。とにかく、アメリカの受験プロセスにおいて、高校のレベルというものの価値は低いようです。
2. 留学生向け奨学金の実情
さてさて、もう一つ聞いて面白かった事があります。日本からアメリカの大学を受験する場合、大学の奨学金を申し込むと合格率が落ちると、大学側が宣言しています。このように、奨学金に応募した場合に合格率が下がるシステムを、Need Sensitiveと言います。反対に、奨学金に応募した場合でも合格率が下がらないシステムの事を、Need Blindと言います。
さて、ポモナは国内生に対してはNeed Blindですが、留学生に対してはNeed Sensitiveです。アメリカの他のトップ校も、殆どがこのシステムを採用しています。そのため、アメリカのメディアも「奨学金を節約したいから留学生を多く受け入れているのでは?」などと、大学を叩きます。しかし実際にDean of Admissionの話を聞いた所、Need Sensitiveにしなければならない理由は、経済危機が恐ろしいからとのこと。実際のところ、PomonaはほとんどNeed Blindですが、そういう肩書きをつけることは出来ない。経済危機が起きて、OBを中心とした基金からの収入が激減した場合、むやみやたらに留学生へ奨学金を配っていたら、対処が効かなくなるからです。いざという時にお金を出せなくなってしまう事を防ぐために、Need Sensitiveという名目にしている訳ですね。
奨学金を貰ったとしても、思った額が貰えないというパターンがあります。しかし、日本の学費が異様に低いという点を忘れてはいけません。冷静に、ポモナというリベラルアーツカレッジの環境、教育の素晴らしさを考えてみれば良い。日本の学費の3倍、払わないといけないかもしれない。奨学金を貰わない場合の6倍よりかはマシですし、3倍だけの価値があるのは、間違いありません。
3. 海外での大学プロモーション
アメリカの大学は、全米各地の高校に訪問し、大学の宣伝をします。留学生を多く受け入れる大学は、外国の高校にも積極的に訪問し、宣伝を行います。しかし、ポモナのAdmission Officerが日本に来て宣伝をするという事例はまったくありません。
理由は、渡航費を補填してもらえる他の国でのプロモーションに注力しているから。9月号で述べた、中国のアメリカ大学受験を牛耳っている新東方という会社があります。このような会社は、Admission Officerが中国に行き学校の宣伝をするための資金を、全部賄ってくれるらしいです。出せる奨学金に限度があるように、Admission Officerの渡航費にも限度がある。故にAdmission Officerも、スポンサーがついている国には行きやすいのです。中国では、どうやら様々な高校を巡っているようです。反対に日本へ訪問した事は、ここ数年無いと言っていました。
以上がAdmission Officeの裏事情と言った所でしょうか?ではまた12月号でお会いしましょう。
|
|
この記事の先頭へ戻る
◇ 2013年10月 若者の変化と個人活動家
◇ 2013年9月 海外大学受験のトレンド作り
◇ 2013年8月 東大と他大を見て思う事
◇ 2013年7月 駒場のリベラルアーツカレッジより