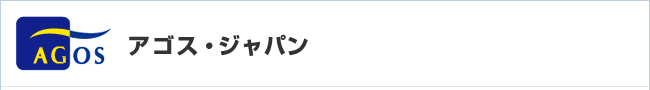2017年3月 ペルー旅行〜総集編〜
2017年2月 ペルー旅行〜クスコからマチュピチュ〜
2017年1月 リベラルアーツの授業〜Double majorの意義〜
2016年12月 2017年の漢字「奇」
この記事を折りたたむ
|
2016年12月 2017年の漢字「奇」
こんにちは。
ブログの投稿が毎回少しずつ遅くなっていてすみませんでした。
この月のブログも年末分ということでなるべくペースを上げて書いていきたいと思います。
皆さん大晦日はどのように過ごされましたか。大晦日といえば年越しそばを食べ、家族で食卓を囲いテレビを見るというような風景を僕は思い浮かべてしまいます。
僕は今回学校に戻ってきたのが元旦だったので、ばたばたした大晦日でしたが毎年大晦日になると、一年どう過ごしてきたかということを振り返っています。
ということで今回は今年を振り返って思ったことそれに加え、今年一年の方向性に綴っていけたらと思います。
2016年の漢字「新」
一年生の冬休み
一年生の一学期を終えた時は今年と同様日本に帰ってきましたが、帰って来るなり毎日のようにアメリカに帰りたいと思いながら日本にいました。日本に帰って来るときこそは、日本の懐かしさにとりつかれ一ヶ月はつかの間の休憩にしようと思っていましたが、何もしないで長時間休憩することがあまり得意でなく、何かしていないと気がすまない性なので結局落ち着かない冬休みとなってしまいました。
今はこの“落ち着かなかった”冬休みをとてもプラスに捉えています。少なくとも最初の秋学期をアメリカで過ごし、良い感触をつかんでいたのでしょう。
そして、これは新しいものに出会いたいという好奇心の表れで、この状態は幸い一年間を通して保つことができました。では、この好奇心はどのように僕の学校生活を変えていったのでしょうか。
休みの間のモチベーション
19年間生きてきてこの一年間でとても大きく変わったのは本を読む量がとても増えたことです。これは一つ勉強をする上でモチベーションを保つことができた一つの要因でした。学期が終わっても、燃え尽きる前にたくさんの本に触れ次の学期への架け橋にしていました。これはアメリカに来て一つ良かった点だと思います。まとまった休みが取れるというのはとても良し悪しがあって、それがすべての人に良いように働くわけではありませんが、人によってはむしろとても多くを学ぶことができる期間です。休みの期間に学べたことは、何時間もかけてでも話すことができない、とても貴重な知識となりました。
人
アメリカの人、そして世界各国から集まる留学生との出会いはとても貴重でした。そして、今まで会ったこともないような風変わりな人に出会えたことも新鮮でした。日常レベルで些細なことからも文化レベルの違いを読み取ることも容易にできました。例えば一年目のルームメイト。教授の両親を持つ彼は幼い頃から本に触れ勉強をするという環境が身近にあったのだと思います。彼は卒業に必要な単位はほぼ高校でとってしまい、1年次から大学院レベルの授業をとっていました。学識者に見られる風変わりな行動などは偏見ではなく彼の随所に見ることができましたが、彼が図書館から借りてきた本について部屋で話すことができたのは僕のモチベーションをある意味維持してくれました。
ルームメイトだけではありません。小規模のリベラルアーツとはいえ1日に一人友達を作っても四年で全員とは友達にはなれません。そのような環境で一番1年次に心がけたことは友達を作ること。生徒会のディスカッションに顔を出したり、クラスでは横に座った人には話しかけるようにしたり、スポーツを始めたり、フラタニティに入ったり。色々な人に会えば会うほど、新しい思考回路を持っている人に会ったり、複雑な家庭環境の下で生まれ、確固たる意思を持って勉強している人にも出会うことができました。人間いくら環境が変わっても自分の意思や信念を変えることはできませんが、新しい人の出会いは自分の成長に大きく関わり、自分の人間性を豊かにしてくれた一つの要素でした。
リベラルアーツでの寮生活において人との関わりは不可欠です。リベラルアーツでは友達と喧嘩しても1日に一回は顔を合わせてしまうような環境にあります。人と関わらないと成長にもつながりません。そして、今までに会ったことのない“新”しい友達は今でも増えています。
挑戦
Freshman yearも含めた去年はどちらかというと、新しいものに出会うという機会に恵まれていたものの、それに対応するのに精一杯でした。「こんな面白いことがあるんだ」と考えさせられた機会は山程ありましたが、その延長としてどのように自分を環境にフィットさせていくのかという所までは頭が回りませんでした。今年はこれを乗り越えて自分の力で何かを変えていく爪痕を残していくことを目標に頑張っていきたいと思います。そのような意味では学校における貢献度を去年よりさらに意識して色々な活動に取り組んでいきたいと思います。
Sophomore Yearの壁
Sophomore Yearは面白いほどにFreshman Yearと異なります。皆が何か得体の知れないものにとても真剣になりだす時期です。それが勉強になる人または課外活動になる人などなど様々ですが。
それが僕の場合どう変わったか。端的にいうと全ての側面で変わろうとしているのが伺えます。いや、もしかしたらそれはどの人にしてみても一緒なのでしょう。Sophomore YearになってFreshman Yearが入ってきてからというもの、Freshman Yearに少し頼り過ぎていたFreshmanInternational Studentとして、特別扱いされることに少し頼り過ぎていたのだと思います。それがSophomore Yearになってから一変し、次のステージに前進している様な気がします。一番の苦労は人との会話です。一年生の頃は極力わからなかったら聞き返すということを徹底していました。それは先ほども言ったFreshmanInternational Student としての言い訳だったのでしょう。しかし、二年生になってからはなるべくそれを言い訳にしたくない。そこそこ英語も出来る様になったから人の話をじっくり聞き、しっかりとした応答をすることを心がけています。どうやらここの文化ではたくさんの情報を提供することで、相手に安堵感を与えるというのが話し方の主流です。確かにこの方法でもとても有益な会話をすることが出来るでしょう。しかしながら、一人の友人に僕がとても“話がうまい”と思う人がいます。彼はいつも僕が話しているときはじっと僕をみて話す機会を存分に確保してくれます。そして、僕が話し終えると間を入れ、自分の考えを話し出します。これはどこの文化の人と話そうと僕がいつも理想としている話し方です。
“信頼”
つかもうと思ってもなかなか掴めない、意識してもなかなか手に入れることができない何かだと思いますが、人間誰もが欲しいもの。自分のカラーを前面に出すこと、人とコミュニケーションを積極的にとるのも全て最終的には“信頼”を勝ち取るためにやっているのではないでしょうか。
2017年の漢字「奇」
今年は去年とは違う年、「新」しいものを吸収した上でそれプラスのことを実践していきたいと思います。それは人によってそれぞれですが、自分が更にここにきてよかったと思える年にしたいと思います。
今月はここらへんで
|
この記事の先頭へ戻る
2016年11月 東京キャリアフォーラム
2016年10月 アメリカの文化的側面〜会話形態の違いから〜
この記事を折りたたむ
|
2016年10月 アメリカの文化的側面〜会話形態の違いから〜
ちょうど1年前のこの時期にPositive Crisisという題名でブログを執筆しました。ブログを書いていなかったらアメリカに来て経験したことを鮮明には思い出せなかったでしょう。このアゴスの学部進学生を対象にして設けられているブログは海外の大学を目指す高校生のみならず、僕たちの成長を記録する一つ優れた手段となっていることにとても感謝しています。たまに自分が書いたブログを書いていると昔あったことを思い出すことができたり過去の軌跡を回顧しています。日記ではないので日々あったことを新鮮な情報として残すことはできませんが、書く側からしてみても、僕たちは毎回留学を経験していない人に向けてあたかも留学を経験しているかのような情報をお届けできるように頑張っています、なぜなら留学生活の内情を知っているのは留学生の特権であり、それを広めていくのも留学生だからです。
さて、前述した通り、留学し二ヶ月たって色々客観的な目線で物事を見だすようになったのもちょうど1年前。留学生活を始め落ち着いてきたといったほうが的確でしょうか。
しかしながらこの“落ち着いてきた”時期と同時にCulture shockを経験したのも間違いないです。幸いそれ以降、徐々にここの生活に慣れてきて、今に至るわけですが、二年生になると一年生を見る。その時にどうしても自分の1年前の時期に照らし合わせてしまいます。
寮生活という環境はBoarding schoolにでも行っていない限りアメリカ人の生徒でも顔を強張らせてしまうような、誰もが経験したことのない未知の世界です。況してや、文化の違う国から来た生徒にとってはこの時期はとても大変です。
従って今回はここに来て日々思っている文化的側面について書いてみたいと思います。
会話
僕がここに来て一番苦労したのは言うまでもなく言語であったでしょう。そしてこれは僕だけではないはず。たくさんの留学生が避けることができない障害だと思います。
この問題はTOEFLで何点取れたらこの問題を克服することができるのかということは関係なく、包括的なコミュにニケーション能力と言えるでしょう。言語学の世界では言語はLangueとParoleに分けることができます。まず最初にLangueは“ある言語社会の成員が共有する音声・語彙・文法の規則の総体(記号体系)”その一方Paroleは“個人・場面によって異なり、言いよどみ、言い誤りなども含む”(Wikipediaより)という定義があります。
言語といってもその能力を測る物差しは様々です。
言語の研究に於いてはこのLangueに重点が置かれています。なぜならLangueという概念は人に関係なく極めて普遍的で誰にでも当てはまる概念だからです。文法などの論理的思考にみられるものがこれに当てはまります。
しかしコミュニケーション能力が高いかどうかを判断する材料(簡単に言えば英語ができるかどうか)としてはこのParoleを外すことは出来ません。このParoleにおいて何を基準にコミュニケーション能力を図っていかなければならないかという質問にDell Hymesという言語学者が提言をしました。人間の言語に対する能力においてはPragmaticsという実際に言語そのもの、言葉をどう発するかという能力を計るものそして、Communicative competenceというPragmaticsとは背反して存在する能力が存在します。
前述したよく耳にするTOEFLの質問に見られるように多くの日本人がコミュニケーション能力の中心はPragmaticsにあるというように捉えがちです。しかしながら、アメリカの文化に飛び込んで人の信頼を得ていく上で一番大切なのはこのCommunicative competenceだということを長い時間を過ごせば過ごすほど感じます。このCommunicative competenceとは喋る人によって、それに相応する話し方を選ぶ能力のことです。
Communicative competence
簡単な例でいくと、教授と話すときはCould, Wouldを用いた問いかけをする。もっと極端な例で言うと教授に向かってFuckなどの下品な言葉は用いませんね。Fuckとはとてつもなく下品なイメージがあると思いますが、このことばを用いたイディオムはたくさん存在し、変な話、生徒間の会話では頻繁に出てくる言葉です。このことに関しては、まず気をつければ(気をつけなくても)ミスを避けることが出来ます。
しかしながら、一番僕がここに来て難しいと思っていて努力してもなかなか成長できないこと、それは人の信頼を得るための言葉の選び方です。この議論においては日本語でも同じ事が言えるでしょう。テレビで見るコメンテーターなど、僕もアメリカにいる時ですら、コメンテーターが議論をしている動画をYouTubeでみたりする事があります。人の話し方というものは人間そのものを表しているかのようなとても大切なものです。
アメリカでの例でも考えてみましょう。例えば今Hotな話題である大統領選の演説。あの二人がスピーチを行っている最大の目的は人々の信頼を得ること。大統領が国民の投票によって決まるアメリカではスピーチは彼らの明暗を左右するとても大きなイベントです。内容に焦点を当ててスピーチを聞くのが本当の聞き方でしょうが、一つ視点を変えて彼らの言葉遣い、立ち振る舞いについて焦点を当てて見るととても面白いということに気づきます。まだ僕には到底できることではありませんが、彼らの話している言葉や文法というのは僕が授業でペーパーを書いているような文章を話しています。簡単な例で言うと語句を強調するとき日常会話ではso, veryなどといった語句を用いることが多いと思います。しかし、大統領選のスピーチではsignificant, tremendousなどという語句を用いることがとても多いです。これらの語句は知っていてもなかなか打ち砕けた日常会話では発することはまずない、仮にこれらの語句を使うととてもformalな印象を他者に持ってしまいます。しかし、discussion, speechという場ではこれらの言葉遣いというのは他者に信頼を覚えさせるのにとても有効な手段なのです。これらは一見とても微小な変化に見えるかと思いますが、実際無意識に人々の心を動かし、信頼を勝ち取るためのとても有効な手段なのです。
そしてこのCommunicative competenceは僕の解釈では話す内容のみならず、body language, 会話の感覚、抑揚など色々な要素が含まれていると思いますし、これは特に僕が一年生の終わりから意識し出したことです。しかしながらこれは特に英語だからより気にしていることではありますが、日本語でのコミュニケーションにおいてもとても重要な“能力”です。
Communicative competenceの大切さ
僕はこのCommunicative competenceが信頼を勝ち取るのにとても重要な要素であるということを最近強く感じています。
特に一年生の友達が今この問題に直面していて、僕の一年生の時期をあたかもそのまま見ているかのような感覚になりました。彼が直面していたのはCommunicative competenceの欠如によって、母国語で話したときに他者が彼に対していい抱くイメージと彼が英語で話したときアメリカ人が彼に対して抱くイメージにとてつもないギャップが生じているという問題。彼は実は日本人で僕自身彼とたくさんの会話を積んできて、礼儀正しくて落ち着いているという印象を受け、その一方でも言いたいことはしっかり話していてとても好感を持つことができるしっかり者というイメージを抱いていました。しかし、彼がアメリカにきて慣れない英語を話すと、どこで笑ったらいいかわからず表情があまり出なかったり、大人数で話すとなかなか会話に入り込めなくて、何を言っていいか迷ってしまうという状況に直面、そして他者につまらない人だと思われているかもしれないという気持ちに襲われる。ということは彼が直接打ち明けてくれました。中でも一番彼を悩ませていたのは他者からの信頼を会話から得ることができないということでした。
僕も一年生の頃相当悩んだ問題だったのですが、このCommunicative competenceというのは驚くほど信頼の獲得に直結します。僕の一年生のときは彼と同様listeningに全く対応できず、会話に混じると気の利いた返答が出来なかったし言葉を選んでから口に出すタイプなので、なかなか人の信頼を得るのに苦労しました。アメリカではとにかく話して間を埋めることが大切なので、言葉を発することで信頼を得るというのはとても大切なことです。
会話方式の違い
さて、なぜ留学生がきてこの問題に直面するのでしょうか。英語の言語自体に問題があるのはいうまでもなく、そもそもの会話形態が国間によって少しずつ違うことに気づいてきました。
アメリカの会話形態
アメリカの会話の様子から気づいたことは大きく分けて二つありました。一つ目はアメリカでの会話形態をシンプルに表すと、とにかく話すことに美徳があるということです。彼らがグループで会話をする時は必ず誰かしらが会話で生じる沈黙を埋めようとしています。一方日本ではこれが正反対である程度の沈黙を重んじる文化、それでなくても、沈黙を破ることに美徳を感じる文化ではなさそうです。しかしながらアメリカの会話の中では時たま楽な思いをすることもあり、例えば一対一で話して、先に質問をしたら一が十で返ってきます。この他にも会話の始まりにもとても面白いものを感じます。今でこそ慣れましたが、この小規模の学校に在籍していると授業まで歩いている途中に友達とすれ違ったりします。その時に必ず“what’s up”や“how is it going?”などに見られる会話のinitiationがあります。学校に来たてのfreshman yearの時は“how is it going?”と言われた時にその日にあった詳細の出来事を話そうとして笑われたことがありました。これらの会話のinitiationは特にそれといった意味はなく、とにかく会話のキャッチボールをしたという点に意味があるのです。よく留学して、とにかく会話することを心がけなさいというのはこういうところからきているのかなと思いました。もちろん、僕は文法も支離滅裂でとにかく話すということはあまり良いと思いませんが、ある程度の線引きをして積極的にコミュニケーションをとろうとすることはとても大切だと思います。これらの日常生活から読み取れることは全てアメリカ人の会話をとにかく重んじる気質を表しているのです。
次に自己主張という側面から見える彼らの話し方がとても興味深いものがありました。とにかく会話の中でも自分のことを話すため、“I”を使う回数がとても多くてとても驚きます。そしてその他にも例として、今年はだいぶ慣れていきましたが去年頭を悩ませていたのが、ご飯などを食堂でオーダーした時に“You don’t need a copy of receipt right?”と聞かれて、いらなかったら“No”ということです。日本語だったら少なくとも僕は“レシートいらないですよね”と質問されて、いらなかったら“はい”と答えます。なぜこの違いが生じるのか。これは先ほど述べた“I”が中心なアメリカの文化から説明ができます。アメリカ人が“No”という時は主語の“I”が省略されているのです。したがって答えは“No”になる。しかしながら、この質問に対して日本人が“Yesはい”と答えるのは質問された時に自分たちがレシートを受け取るかどうかというところでは考えておらず、レジ打ちの人がレシートを渡すかどうかという思考回路で質問の受け答えをしているからなのではないでしょうか。ここからも彼らの“I”を重んじる文化に気づかされました。
このように、今回はほんの二例について話しましたが、会話形態の違いというのは日頃の日常会話を深く観察していたら気づくものもたくさんあります。
|
この記事の先頭へ戻る
2016年9月 なぜ物理を勉強するのか
2016年8月 留学生の長い夏
2016年7月 リベラルアーツと総合大学
2016年6月 一年を振り返って〜東京にて〜
2016年5月 Varsity 〜アメリカの学校でのスポーツ〜
2016年3月 “人種のるつぼ”NYへ“ NY, where diversity meets
2016年2月 フラタニティの賛否
2016年1月 学内雇用から垣間見えたこと
2015年12月 牽制としての正義
2015年11月 食生活と各国の進学費用
2015年10月 Positive Crisis
この記事を折りたたむ
|
2015年10月 Positive Crisis
こんにちは!10月です。
ブログの更新が大変遅くなってすみません!
いつも導入部分何を書こうかと考えていますが、今までのブログを見返していたら全部天気のこと書いていました(笑)今月こそ違うことを書こうかと思っていたのですが、やはり天気のことは触れておきたいです。というのも一ヶ月程前に初雪を観測しました!朝夜は氷点下が普通になってきました。この寒さだと先が思いやられます・・
さて、今回は主に文化について重点を置いて書いてみたいとみます。
・How international students adjust to college life
今回この話をしたかったのには動機があって、まずこの画像を見ていただきたいです。

お分かりだと思いますが、縦軸が気分、横軸が時間の二次元グラフです。つまり、Culture Shockがどのタイミングでくるか、それを表したグラフです。しかしながらこのグラフを一番初めに見たときに思ったことがあります。“もうCrisisに来ているのではないか・・”
しかしどうでしょう?個人的な考察としてこの時期を気分が下がる時期だという定義付けをするのは少し間違っていると考えます。最初の1、2ヶ月はかなり主観的な視点でアメリカと日本の良し悪しを判断していたように思います。そして次の段階であるCrisisの時期にくるのは一般的に2、3ヶ月後だと言われています。2、3ヶ月したら個人的にアメリカと日本を冷静な視点から二者を比較することができる時期になるのだと思います。そして僕は今おそらくCrisisの段階に来たのではないかと思っていますが、それはこのグラフとは反して”Positive Crisis”の時期に差し掛かっているのだと自分では考えています。
この時期も同様に必ずしも気分が高揚した時期だとは言い難いです。勿論、夏のプログラムに参加してHoneymoonの時期を楽しんだという言い方もできるのだとは思いますが、その一方、授業が始まってからの生活を考察すると最初のプログラムそして秋の授業の最初は、かなり主観的な手段を率先して選んでいたのだと思います。すなわち日本で今までやってきたことをそのまま当てはめてどうなるかを試していた時期でした。リーディングが課されると隅から隅まで精読し、わからない単語は一語一語調べて書き込んでいく、結果かなりの時間をリーディングに割き、結果終わらない・・なんてこと頻繁に起こっていました。そんなことからなかなかみんなにサッカーやパーティーに誘われても行けなかったり・・そんな日々でした。授業を受けたらすぐ日本の授業と良し悪しを極端に比較してみたり。
本当に話したいのはここからの”Crisis” の時期です。
・Crisis
今やっとこの時期に差し掛かってきたかと思っています。個人によってどの状態からをCrisisと呼ぶかは分かりませんが、積極的に折衷的な思考をすることができるようになる時期だともいます。まさに最近これができてきたのかと思います。
一番これが顕著に出てきたのは勉強面だと思います。例えば、リーディングに関して、毎回ディスカッションのためのリーディングが必要なのですが、次回の授業で議論するトピックは大体教授が教えてくれます。その次回の授業で議論するであろうトピックを詳しく精読して、あとは内容をざっくり読んで把握するこれはまさにアメリカにきて学んだ折衷的な考え方だと思います。そして徐々にリーディングに割く時間が短くなってきたのを心なしか感じることができます。そしてそのセーブできた時間を社交面に使うことが少しずつ可能になりつつある時期です。
そしてこの時期に差し掛かり少しずつ能動的に話しかけられる機会が増えてきましたが、より一層文化的な側面にsensitiveになってきたのも感じます。これは最初の時期にsensitiveではなかったと言いたいのではなく(文化の衝突を避けるために敢えて色々なことを話さなかったのだと思います)それを受け入れることができる自分が強くなってきているということを意図して言っています。
・Core Groupの重要性
この学校にはCore Groupという、全てのFreshmanがランダムにグループに分けられて、毎週月曜日にお互いのことを話しあったり文化的な側面を確認するという機会が設けられています。1グループには必ず”Core Leader”と言われる上級生の二人がつき、ミーティングを取り仕切ります。実は先月号で記事に書いたFreshman Studiesのクラスの生徒はこのCore Groupのメンバーです。
ある週のCore Groupのミーティングで、今から質問する内容にYesなら一歩前に進み、Noなら一歩後に戻るというゲームをしました。質問の内容は主に自国の文化的な側面、自分の家庭状況で辛い思いをしたことがあるか、ないか、そのような質問です。そして辛い思いをした人が後ろに下がるように質問が作られています。さてこの質問を一通り終えてどのような結果が出たでしょうか?14人程いた中で僕は前から三番目にいました。個人的には予期せぬ結果でしたが、深く考えてみると文化的な側面で苦労したことがなかったというのをふと思いました。質問の中には人種差別を受けたことがあるか、性差別を受けたことがあるか、あまり日本では馴染みのないトピックで、それに関連したトピックが出てきたときは何も言えませんよね。苦労したことがないのでおもむろに重い足取りで仕方なく前に進めていました。このゲームの最後に“裕太は自分の位置見てどう思った?”と聞かれ、素直に“幼少期から両親がいて、好きな勉強ができて、中高も私立の高校に行けて、何よりここで勉強できる。そして日本はみんなアジア人だし、正直性的指向が違うということをカミングアウトした人を見たことがなかった”ということを正直に述べました。
・Intersectionalityについて
聞き慣れない単語だともいます。しかし、最近関心を集めているワードで、それはこのアメリカならではの文化的側面を考察しようという姿勢の現れなのだと思います。
ネットの辞書の定義には
Intersectionality is a sociological theory seeking to examine how various socially and culturally constructed categories of discrimination interact on multiple and often simultaneous levels, contributing to systematic social inequality. Intersectionality holds that the classical models of oppression within society, such as those based on race/ethnicity, gender, religion, nationality, sexual orientation, class, or disability, do not act independently of one another; instead, these forms of oppression interrelate, creating a system of oppression that reflects the "intersection" of multiple forms of discrimination. (Madigan, 2011)
訳すと
インターセクショナリティとは、システム的に社会の不平等に貢献している、さまざまな社会的そして文化的に構築された差別の分類が、どのように多層的に、そしてしばしば同時的に交差しているのかを分析する、社会学の理論のひとつです。インターセクショナリティによると、人種/民族、性、宗教、国籍、性的志向、階級、あるいは障害など、社会における抑圧に関する古典的なモデルは、それぞれが独立して機能しているのではなく、これらの抑圧の諸形態は関連しあっており、さらに、差別のさまざまな形態の「交差」を反映する抑圧のシステムを作り出すとされています。
要するに上記に説明したゲームはこの全ての差別が個々人にどのように影響しているのかを目に見える形で垣間見ることができた実験です。お互いに尊敬の念を痛くためには個々人のそのような背景を知ることが必要ですが、特にアメリカの文化に慣れていない留学生は最新の注意を払わないといけないともいます。それが今から述べる”Microaggression”というものに関わってきます。
・Microaggressionについて
この単語を端的に説明すると多文化の無知によって時に人に不快な思いをさせるような質問を無意識的にしてしまうというものです。
Core Groupの友達が一人実体験を元にしたとても分かりやすい例をあげてくれました。彼女はタンザニアからの留学生ですが、高校生のときにアメリカに来たのだといいます。彼女がアメリカにきて、たくさんの人に自分の出身を説明すると「インドから来たのかと思ったよ」ということを頻繁に言われたらしいです。確かに彼女はアフリカのタンザニアから来たのに黒人ではないのです。彼女が強調していたのはアフリカにいる全ての人が黒人だという前提を皆に持たれていて、最初の時期はたくさんの人に言われて、とても不快な思いをしたと言っていました。
他にもいい例があります。恥ずかしながら自分も知らなかったのですが、”Where are you originally from?”という質問が失礼だということです。Core Groupで話して確かにそうだなと思ったのですが、彼らはあくまでアメリカの国籍を持っていてアメリカで生まれ育っているのです。大げさかもしれませんが、それを言われることによってアイデンティティを否定されたと解釈されたと思う人がいてもおかしいことではないのです。
・まとめ
さてここまで話してきて少しでも”Positive Crisis”に少しでもどんなことを学んだかということを皆さんにお伝えすることができたでしょうか。
つい最近も勉強面の話をすると、何人かのOffice Hourの時間を質問を十分に理解できていないのに打ち切られることがありました。そのことを友達に相談すると、”We have a lot of nice professors that you haven’t met”といわれました。そして、「この教授は実は凄い熱心で生徒のために膨大な時間を割いているといるよ!」ということを教えてくれました。まだまだ学校の中を把握できていない状況の中にいると思います。
ここまで話して一度上記のグラフを見直して欲しいです。本当にこんな単純でしょうか。僕は細かいCulture Shockを見つけ、その度にたくさん修正し、徐々に適応していくものだと信じています。

このようなグラフの方が正しいのではないでしょうか。
時間が経つにつれて振れ幅が小さくなっていき、最終的に微小値になっていくのだと信じています。従って結論を述べると、僕は最初に載せたグラフのどこにいるのかよく分からないです。しかし、徐々にこの振れ幅をなくしていっているのです。
お気づきでしょうか?この下に載せたのはLC振動回路の電流と時間の関係のグラフです笑
高校生活をふと思い出しました。懐かしいです。また年末皆さんあってください!!
では、今月はここら辺で失礼します。
|
この記事の先頭へ戻る
2015年9月 トライメスター制授業のシステム
2015年8月 SIISと勉強、クラスメイトの苦悩
2015年7月 ギャップターム生として
2015年6月 自己紹介・進学決定の経緯
|