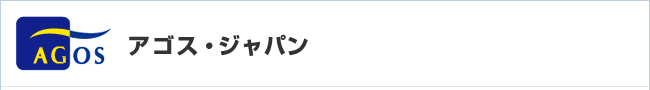◇ 2018年5月 卒業
◇ 2018年4月 集大成としての卒論
◇ 2018年3月 卒論執筆記録
◇ 2018年2月 知識のインプットとアウトプット
◇ 2018年1月 最終学期!
◇ 2017年12月 リベラルアーツからの応用力
◇ 2017年11月 Honors Thesis近況報告
◇ 2017年10月 4年間の大学生活
◇ 2017年9月 いよいよ最終学年
◇ 2017年8月 最後の夏休み
◇ 2017年7月 自己分析と表現力
◇ 2017年6月 海外大学進学という「選択肢」
この記事を折りたたむ
|
◇ 2017年6月 海外大学進学という「選択肢」
6月号です!
夏休みに入り、日本に帰国してから早一か月が過ぎました。
今月号は、大学3年生の総括として振り返ってみたいと思います。
この1年間は、新たな挑戦を通して、アメリカの大学で過ごした最初の2年間をより客観的に見ることができたように感じます。改めて、一つの「選択肢」として自分が選んだ海外大学進学という決断を振り返ることができました。
○アメリカ大学進学という選択肢
まず「アメリカの大学に進学した」、という選択肢について。
これは、3年生の前半である秋学期に交換留学で英国・スコットランドに行ったことによって、客観的に振り返ることができました。
昨年の9月~12月号で交換留学での経験について詳しく紹介させていただきましたが、この1学期間の交換留学を通して、アメリカと英国の大学の違いがよくわかりました。
もともと、アメリカの大学を志望したきっかけは、高校1年が終わった春休みにいくつか有名大学のキャンパスを訪れたことです。この時、世界のアカデミアの中心であるアメリカのパワーを感じ、自分もこんな環境で世界中から集まる「知」と「人」に触れたいと強く思いました。そうしたアメリカのエネルギーに惹かれ、アメリカの大学を中心にカナダ、英国、オーストラリアの大学の受験システムや教育制度を調べ始めました。
その中で、アメリカの大学が大切にするリベラルアーツの精神に触れました。この「多様な学問を学ぶ中で視野を広げ、繋がりを見出す中で新たな価値を生み出す」という姿勢に共感し、アメリカの教育システムが自分の性格と自分が思い描く4年間の大学教育に最も近いと考えたわけです。
実際、アメリカの大学で2年間を過ごし、まさにリベラルアーツを体現するような学びをしてきたと思っています。まず第一として、「国際関係学専攻・海洋学副専攻」という、普通では考えられないような組み合わせが大学の仕組みと自分の意思によって可能となっていること。もちろん、どちらか一方を専門的に追究していくことはどこでもできたことだと思います。しかし、その両方を自分が満足するまで横断的に学べる環境が整っているのはやはりリベラルアーツの特権なのかなと思います。
そしてより一般的な視点に立つと、自分の責任と計画性において、4年間の大学での学びを完全なオーダーメードで組み立てることができるのも魅力的です。とりあえずいろんな学問を少しずつ勉強してみた後、本当の意味で自分の興味を見極めたうえで、それを自分が探求したい分だけ探求できるという制度が整っています。
例えば自分の2年生の時のルームメートは、入学当初は生物学専攻を考えていましたが、その後国際関係学専攻、そして最終的に2年生の終わりでは物理学専攻に決めました。彼は最初の2年間で様々な科目を履修して、色々な教授と出会い、最終的に自分が納得した学問に出会えたということです。この、まずいろんな選択肢をしっかり知れる、という点において、アメリカの大学が有する教育システムは魅力的だなと改めて思います。
こうした、アメリカの大学の特徴を改めて感じることができたのが、3年生秋学期の英国への交換留学です。今まで、主観的にアメリカの大学のよさを感じることは多々ありましたが、それを客観的に他の選択肢と比べることは出来ませんでした。アメリカの大学が英国の大学よりも優れているという話では決してありませんし、英国の大学でいいと思ったこともたくさんあります。ヨーロッパ、そしてスコットランドならではの雰囲気を全身で感じ、生活できたのもやはり交換留学の醍醐味です。それにプラスして、自身の好みとマッチした選択を他の選択肢も経験したうえで改めて自分として客観的に評価できたのは、非常に貴重な経験でした。
ちょっと勉強の話に終始してしまいましたが、教育システム以外にもアメリカか英国の大学どちらかを選択した先には色々な違いが存在します。そもそもその国に長期間住むということ、そして周りの人々、学生生活、教授との関係性など、アメリカに行っていただけでは知り得なかった、他の選択肢の先にあることを実際に体験することができたという意味で、交換留学はとてもいい経験です。
○リベラルアーツ教育という選択肢
続いては、「リベラルアーツ教育」について。
前項ではアメリカの大学の特色としてのリベラルアーツを振り返りました。それに加えて、リベラルアーツ教育とある意味対比をなすのが「研究」です。今年に入ってから何回かにわたりHonors Thesis(卒業論文)などを紹介してきましたが、まさに3年生の春学期は新たに「研究」と出会った学期でした。
大学に入る前にも、長期的なリサーチプロジェクトで課題として自分でいろいろ調べたりして論文を書くことは何度もありましたが、基本的には常に授業を受け、与えられた課題をこなすことに終始していたわけです。それに対して、今回のHonors Thesisでは一からすべてを自分で行います。それだけでなく、研究機関としての大学に所属する一員として、またアカデミアの世界の一員として研究を行うことが求められることを実感しました。
すべてを鵜呑みにせず、一歩立ち止まって一つ一つ真偽を検証する姿勢を鍛えられるのが、教育の姿ですが、あくまで知識を受け取る方であり、消費者としての立場に終始しています。その一方で、学問を創造する立場に立つには、今まで知らなかった色々な作法があって、アプローチの仕方があることを学びました。
一番苦労したのは(苦労しているのは)、アカデミアでは仮説を立て、それを科学的な手順に則って丁寧に丁寧に証明していかなければいけないことです。普段、調べた情報を自分の主張を軸にまとめて執筆するエッセー課題などのレポートとは大きく違い、緻密に証明を積み重ねていく本格的な研究は独特です。特に、国際関係学と海洋学を統合させて、新たなものを作り上げようと奮闘している自分にとって、(3、4月号で繰り返し強調しているものの、感覚の問題なのであまり共感してもらえないかもしれませんが…)何もかもが初めてで、本当に学ぶものが多かったように感じます。
これまでの大学生活で、研究という選択肢に積極的に触れることができなかったことは少し後悔でもあります。どうしても高校までの選択肢である、授業を受ける、課外活動に参加する、というようなことに目が行き気味で他の選択肢の存在を発見しにくかったということもあると思います。それが、こうして3年生の後半である春学期に新たな選択肢と出会い、実際に経験することができたのは非常に大きかったです。また、こうして別の選択肢を実践することで、もともと知っていた「教育」という選択肢を客観的に振り返ることができました。
○まとめ:選択肢
「選択肢」について、まとめておきたいと思います。
普通、人生において何か決断を下して一つの選択肢を選ぶと、もう一つの選択肢のその先を知ることはありません。海外大学進学を例にとると、アメリカの大学に進学した場合、自分が英国の大学に行っていたらどうなっていたのか、知る由はないです。そうなると、必然的に果たしてベストな選択ができたのか悶々とすること大いにあり得ます。
実際、高校卒業後の5月に進学先をウィリアム・アンド・メアリー大学に決定する際に、自分自身が悩みに悩んだ経緯から、他の選択肢だったらその後どんな人生だったのか、答えの決して出ない問いを考えたこともありました。そうした問いに、ある程度答えを導きだしてくれるのがこの「交換留学」です。
そういった面において、交換留学という制度は、「他の選択肢を実際に体験して、選択の善し悪しを検証する」という、人生の他の場面では考えられないようなことを可能にしてくれる特異なものです。
簡単に言うと、「せっかく交換留学のチャンスがあるなら挑戦してみなよ」という点に収まるのですが、交換留学ってすごいことなんだなーとしみじみ感じました。
「研究」に関しても同様です。繰り返しになるのであまり詳細には書きませんが、研究という選択肢を知ったからこそ、今まで当たり前のように受けてきた「教育」をより客観的に知ることができました。
常に多くの選択肢を確保しておくことは非常に重要です。
また、こうした新たな発見があったのも、自分に選択の余地があったからであることを忘れてはいけません。選択肢が複数存在していたからこそ、自分にとってベストだと思う道を求めることが可能になったわけで、このことに感謝しないといけないと感じます。
海外の大学へ進学するというのは、それ自体を目的化してしまうのはちょっと違っていて、あくまで一つの選択肢に過ぎないということを認識するのも大事です。海外の大学に進学することで失う選択肢があるかもしれませんが、得る選択肢も非常に多く、海外の大学に進学した先にいろんな可能性が広がっているという事実に価値があるのかなと思ったりしました。
選択肢が広ければ、それだけパッと何かやりたいことができた時に実際に実現させられる機会も広がるので、やはりどんな形であれ、できるだけ選択肢の幅を広げる努力をすることは重要です。
こうした姿勢は、まず多様な学問や価値観と出会うことを目指すリベラルアーツの精神とも一致するのかなと思いました。
以上、6月号では3年生を振り返りながら「選択肢」について考えてみました。
では!
|
この記事の先頭へ戻る
◇ 2017年5月 アメリカの大学の特徴「寮生活」
この記事を折りたたむ
|
◇ 2017年5月 アメリカの大学の特徴「寮生活」
5月号です!
5月中旬に3年生を終えて日本に帰ってきました。
帰国後の2週間と6月の1週目はいわゆる「就活」をし、無事に自分が満足いく形で終了することができたので、少しホッとしています。
こちらに関しても機会があれば今後紹介していきたいと思います。
さて、そんなこんなで遅くなってしまいましたが、今まで紹介していなかった3年生春学期に関することを今回はお話ししたいと思います。
○Room Selection
毎年春に行われるRoom Selectionは次年度に住む寮を決定する重要な行事です。
通常の上級生向け寮に住むプロセスを経験するのは実は今回が初めてだったので、今月号で紹介しようと思った次第です。
1年次は全員Freshman Hallsと呼ばれる一年生向けの寮に住まなければいけないので、7月ごろに全員にアンケート調査が行われます。このアンケートでは、一人一人の生活習慣(部屋をきれいにするタイプか、音楽を聴きながら勉強するタイプか、などなど)を調査し、似た習慣を持つルームメートを大学側がマッチングしていきます。希望すればもともと知り合いの友達と住むことも出来ます。その後、住む部屋とルームメートが通知され、連絡を取り合うことができるという仕組みになっています。そのため、1年次には自分でどの寮のどの部屋に住みか選ぶことができません。
2年生以降になると、Upperlevel Hallと呼ばれる寮に住むことになります。それと同時にキャンパス外に自分でアパートや家を借りて住むことも可能です。しかし、ウィリアム・アンド・メアリー大学では寮の数が充実しているという点と、周囲も静かな住宅街ということでキャンパス外に住むことの利点があまりないという点から、大部分の人がキャンパス内の寮に住んでいます。最近では近くにあったホテルを大学が買って、寮として利用したりしていることもあり部屋の数も増えているので、希望すればほとんどの場合寮に住むことができます。
自分の場合、2年次は日本語を学びたいと思っている学生が集まる日本語ハウス(Japanese House)に住んでいました。2年生のころに書いた記事でも少し紹介しましたが、こちらはSpecial Interest Housingといって、一般の寮の前、2月ごろに入寮の希望を出し、志望理由などを書いたあと面接を通して寮に入れるかが決定します。そのため、通常のRoom Selectionより前に独自のフローで次年度住む寮を決めることができます。
また、3年次は交換留学でセント・アンドリューズ大学に行っていたので、春学期に住む寮はメールで簡単に希望を伝え、大学側が空いている部屋を用意してくれた形になったので、こちらも通常のフローではありませんでした。
では、一般的な寮の決定方法はどうなっているのか、新4年生ながら今回初めて経験した手順をお伝えします。通常の場合、授業の履修登録のようにオンラインで与えられた時間に部屋を選びます。
まず、2月に来年度も寮に住むことを大学側に申し出て、デポジット($200)を払い、Housing Contract(寮の利用契約)に合意します。この利用契約は、入寮から大量までの決まり、持ち込んでいいもの、寮内の物品を破損した場合など、トラブルが発生した場合どのように対処することになるのか文面で明記されており、毎年内容が変わるわけではないものの、必ず合意する必要があります。
そして、3月下旬にランダムにタイムスロットが個別に割り当てられます。これは、
・月曜日〜火曜日午前は4年生
・火曜日午後〜水曜日は3年生
・木曜日〜金曜日午前は2年生
という様に学年ごとに割り当てられている日にちの中を、さらに午前9時から30分ごとに分割されたタイムスロットが一人一人にランダムに割り当てられるという意味です。つまり、月曜日9時がタイムスロットの人はすごくラッキーで、キャンパス中のどの寮のどの部屋も選べるというわけです。徐々にいい部屋から埋まっていき、木曜日の夕方とかになると余っているあまり人気のない部屋を2年生が選ぶことになります。
4年生の場合、月曜日の午前中から火曜日の午前中まで、どの時間帯が自分に割り当てられるかは完全に運で、このタイムスロットによってだいたいどれくらいいい寮に住めるかが決まるといっても過言ではありません。というのも、人気の1人部屋は数が限られているため、月曜日中にはすべて埋まってしまうからです。また、新しくできた寮や、先ほど紹介したようにもともとホテルだった寮などは、部屋数は多いものの早い者勝ちなので、だいたい2人部屋でも火曜日いっぱいには埋まってしまいます。アメリカの意外に年功序列なところが見てとれます。
そして、4月中旬に部屋をオンライン上で決定します。30分ごとのタイムスロットなので、自分の割り当てられている時間の30分前にまず空いている部屋を確認し、ある程度目星をつけたうえで、タイムスロット内にオンライン上で部屋を選択し、登録します。そのため、授業登録の時のような緊張感がありますが、同じタイムスロットに割り当てられている学生数は授業登録の時ほど多くはないので、アクセスが過度に集中せずページが固まることはありません。それでも、タイムスロット開始から数分遅れると残っていたいい部屋が埋まってしまうので、ヒヤヒヤですね…1年間生活する寮の部屋が決定される重要な瞬間ということもあり、学生生活の大きなイベントです。
○まとめ:寮に住むということ
アメリカや英国の大学に通う学生にとって忘れられないのが、この「寮生活」です。特にウィリアム・アンド・メアリー大学では寮に住むことが当たり前のようになっていますが、東京など都市にある大学と比べると改めてその特異性を感じます。
1年生のころは、初めてアメリカ人と24時間生活を共にすることはとても新鮮に感じていて、日々の生活の中から学びがたくさんありました。何気なくお互いの勉強の状況やその日の出来事などを会話したり、一緒に夕飯を食べに行ったり、結果としてルームメートは一番コミュニケーションをとる相手になります。1年生のころのルームメートとは今でもたまに一緒にご飯を食べたりしますし、何だかんだ言って大学での最初の思い出を共有するのでお互いにとって大事な存在です。
大げさに言えば、「交渉力」も身につくわけで、同じ空間を共有する際にライトや音、空調など些細なことでも、どこまでは妥協できるのか、もしくはどこからはしっかり自分の好みを伝えるべきなのか、そういう身近なコミュニケーション力も鍛えることができます。
3年生になってからは上級生に人気の1人部屋に住むようになりましたが、それでも大学の仲間の大多数がキャンパス内に住んでいることによって生まれる一体感のあるコミュニティーはとても素敵だと思います。
リベラルアーツ教育は何も学問に限られたことではなく、こうして寮生活を通した24時間教育を以て完結するのだなと強く感じました。
ということで、今月号では寮について紹介いたしました。
6月号では、大学3年生として過ごした1年間を振り返ってみたいと思っています。
では!
|
この記事の先頭へ戻る
◇ 2017年4月 「教育」と「研究」
◇ 2017年3月 4年間の学びの着地点:Capstone Experience
◇ 2017年2月 専門を決めてから一年…
◇ 2017年1月 交換留学から帰ってきて
◇ 2016年12月 スコットランド編:交換留学を終えて
◇ 2016年11月 スコットランド編:非日常に身を置く「留学」
◇ 2016年10月 スコットランド編:学問を深く深く
◇ 2016年9月 スコットランド編:異なる大学システム
◇ 2016年8月 HLAB特別号その2
◇ 2016年7月 HLAB特別号その1
◇ 2016年6月 海外留学について
この記事を折りたたむ
|
◇ 2016年6月 海外留学について
6月号です!
実は、3年生の秋学期で交換留学へ行くことが決まりました!行き先は今何かと話題のイギリスです。9月から4か月間スコットランドのセント・アンドリューズ大学で学ぶことになります。
「留学先からの留学」という形になりますが、今月号ではウィリアム・アンド・メアリー大学における海外留学についてお話ししたいと思います。
○なぜ海外留学なのか
ぼくが9月から留学をするというと、アメリカでも日本でも多くの人がすでに留学しているのに!と驚きます。しかし、すでに留学している場合でも大学では分け隔てなく海外留学の機会がある以上、その機会を活用しない手はありません。
自分が海外留学に行こうと思った理由はいくつかあります。まず第一に、そもそも自分がアメリカの大学に進学しようと思ったのが、日本に限らず世界中から知識を得たいと思ったからです。実際英語で得られる情報は日本語で得られるものに比べて圧倒的に豊富であるし、先進的です。それ以上に例えば春学期履修していた国際安全保障学の授業であれば、将来的に国務省や国防省に入ってアメリカの行く末を担っていくような学生と共に、DCの安全保障学の中心にいた教授から学ぶことができたのは非常に貴重な経験です。文字情報以上に膨大な知識を得るにはやはりその場に行って人と話をすることが大切になります。そうした本来のアメリカ大学進学の目的の延長線上に、今度は様々なものの発祥の地、中心の地でもあるイギリスの大学に行って同じように様々な知識や情報を体で感じたいと思うようになりました。
2つ目に国際関係学を学んでいる以上、アメリカ以外の視点からもこの学問を見てみたいと思うようになりました。特にイギリスの場合、英国学派と呼ばれる歴史や政治思想を重視するアプローチ方法があるので、実際にどこまで大学でそれが実践されているのかはわかりませんが、新たな視点から国際関係学を学んで自分の理解を深めてみたいと思います。
3つ目に何より長い歴史を持つヨーロッパで過ごしてみたいと思うようになったのも正直なところです。ウィリアム・アンド・メアリー大学はアメリカでももっとも歴史の長いバージニア州に位置し、大学周辺には建国の中心となった遺構が数多く残っています。ヨーロッパにはそれ以上に千年以上の歴史があるところが多く存在すると思うので、そうした歴史を感じながら、今まで、そしてこれからの国際関係を考えてみたいと思います。
4つ目に勉強面だけでなく、やはり留学を通して得られる価値観も大切にしていきたいです。アメリカに2年間いると、アメリカの人々の考え方やその地で生きる「勝手」が徐々にわかってきます。アメリカの大学におけるチームの運営の仕方から大統領選の話、地元で一番おいしいサンドイッチチェーン店まで、こうしたことは実際にアメリカ人の友達と一緒に時間を過ごさないと感覚としてつかめてこないものが多いです。このように勝手がわかっている地域を世界の中で増やしていくことで、今後いろんなところで活躍していけるようになりたいと思っています。この留学ではイギリス、そしてヨーロッパの勝手がわかるように人々と交流を重ねていきたいです。
○セント・アンドリューズ大学について
セント・アンドリューズ大学はスコットランドの首都エジンバラから車で1時間半ほどにある街、セント・アンドリューズにある大学です。1413年創立で、オックスフォード大学、ケンブリッジ大学に次いで英語圏では3番目、スコットランドでは最古の大学になります。セントアンドリューズはゴルフ発祥の地として有名で、全英オープンで使用されるOld Courseと呼ばれるゴルフ場はゴルフの聖地といわれています。
学部7000人ほどの中規模大学ですが、45%がイギリス国外出身、またアメリカとのつながりが強いことから15%がアメリカからの留学生といわれていて、非常に国際色豊かな大学です。最近の卒業生で言うとイギリス王室のウィリアム王子とキャサリン妃がいます。
自分がセント・アンドリューズを選んだのは国際関係学が非常に盛んだということと、海洋生物学が単独の学科として存在するからです。アメリカとは全く違う環境でこれらの学問がどのように扱われているのかとても楽しみにしています。また、600年以上の歴史を持つ大学ということで、近くには大聖堂の遺跡があったり、ゴルフの発祥の地だったり、すぐ近くには砂浜があったりと、とても素敵な街のようなので9月以降セント・アンドリューズ大学の魅力をたくさんお届けできればと思います。
○海外留学について
日本の大学では近年1年間の交換留学という形で海外の提携校に留学することが比較的人気になってきていて、大学や学部によっては必修のところも出てきていると思います。アメリカでも交換留学の重要性は十分認知されていて、アメリカの大学を選ぶ際、海外留学の機会が多く、多様な提携校が存在することは進学の一つの決め手になります。それくらい、海外留学は大学にとって大事なプログラムでもあります。ウィリアム・アンド・メアリー大学でも同様で、この大学では約半数の学生が何らかの形で在学中に海外留学を経験するといわれており、これはアメリカの大学の中でも非常に高い比率です。
特に、2019年卒業からスタートした新しい大学カリキュラムであるCollege Curriculum では、3年次に海外留学かそれに準じる形で異文化での経験を積むプログラムを履修することが学生全員に求められることになりました。その結果、今後ますますウィリアム・アンド・メアリー大学では海外留学が盛んになっていくことになりそうです。
ウィリアム・アンド・メアリー大学には3種類の海外留学が存在します。まず一つ目が夏休みに1か月ほどの期間で行われるW&M Summer Programsです。基本的には海外の「大学」に留学に行くというよりも、「都市」に留学するという形でウィリアム・アンド・メアリー大学の教授が現地ならではのクラスを教えます。現在15か国で18のプログラムが行われています。
そして学期もしくは1年間の留学する場合、学費の支払先によって種類が別れます。ウィリアム・アンド・メアリー大学に通常通り学費を支払う場合の留学がTuition Exchange Programになります。大学が州立大学のため、主に州内の学生がこの制度を利用します。3種類目がAssisted Enrollment Programです。これは、多くの場合海外の大学の学費のほうが安いため、直接留学先の大学に学費を支払う場合の留学方法です。どちらの制度であっても留学できる大学とTuition Exchangeでしか提携していない大学もあります。合わせて11か国16大学と提携しています。
例えば、日本の大学だと慶應大学と秋田の国際教養大学の2校と提携しており、9月からの1年留学と4月からの1学期留学の2種類あります。どちらもTuition Exchangeのため、ウィリアム・アンド・メアリー大学に学費を払って留学し、日本の2つの大学からも日本人が毎年母校に学費を払ってウィリアム・アンド・メアリー大学に1年間の交換留学に来ます。
そんな海外留学ですが、ウィリアム・アンド・メアリー大学ではReves Center for International Studiesが海外からくる留学生の支援とともに海外留学に関しても管轄して行っています。何かわからないことや相談があればいつでもReves Centerの職員の方にメールで質問をすることができるだけではなく、Reves Centerの建物に行けば過去に海外留学を経験したStudent Advisory Boardという学生が常駐していてプログラムの調べ方や応募用紙の書き方なども教えてくれます。職員の方々もタイミングがよければ詳しい話を聞かせてくれます。
○応募プロセス
次に大学における海外留学のプロセスについて順を追って紹介したいと思います。
a.留学フェア
毎年9月の土曜日に大学内ではReves Centerが主催する留学フェアが開催されます。このイベントでは、それぞれの提携校がブースを持ち、その大学に留学経験のあるウィリアム・アンド・メアリー大学生とその大学から留学中の学生が大学の魅力や向こうでの生活を紹介してくれます。
この留学フェアを通して、多くの場合どこに留学したいかイメージすることができたり、実際にその大学に行ったことがある人と知り合いになることができたりと、留学へ向けた最初のステップを踏み出すことができます。
b.ワークショップ
ウィリアム・アンド・メアリー大学では、留学を希望する学生は2回のワークショプに参加することが義務付けられています。1日1回図書館かReves Centerで開催されていて、過去に留学経験のあるStudent Advisory Boardの学生が1時間ほどのセミナーを行ってくれます。1回目は海外留学制度や準備の仕方について、2回目では志望校を決めた後の具体的な応募方法などについて詳しく教えてくれます。
自分が行きたい大学に留学したわけではなくても、実際に留学経験のある学生から経験談などを聞くことで留学までの準備で何をしなければいけないのかイメージがつくいい機会になります。また毎日開催しているので、「必須」となっていますが都合のつくときに2回参加するだけでいいのでそんなに負担ではありません。
c.応募用アプリケーション
通常留学に出発する前の学期の中ほど(9月からの留学であれば3月、1月からの留学であれば10月)がアプリケーションの締め切りになっているので、それに向けて準備を進めていきます。アプリケーションは独自のオンラインシステムに大学受験の時のような要領で進めていきます。オンラインのフォームに必要事項を記入し、留学の動機や目標に関するエッセーを4つほど執筆します。それに加えて、大学の事務から取り寄せた成績証明書や普段お世話になっている教授から授業での様子などについて推薦状を書いてもらいます。
志望大学によってはGPAの足切りラインがあることもあり、成績は言うまでもなくとても重要ですが、交換留学の際はエッセーで留学の目的が明確化されているかどうかが最も重視されるといわれています。
推薦状は高校の時と同様に、学業面での自分自身の姿を教授に書いてもらうのですが、やはり学生数の数が大きいだけあって高校の時よりも難しいように感じました。できるだけ自分のことをよく知っている教授を作って印象を強くしたうえで、アポを取ってお願いをしました。
d.出発前オリエンテーション
3月中旬に応募が締め切られ、2週間ほどで結果が出ます。
無事に海外留学に行けることなると、学期の終わりのほうで出発前オリエンテーションが行われます。このオリエンテーションは大学から海外留学に出発する全員に向けてのものなので、一緒に同じ大学に行く学生や留学先の大学についてなどは教えてもらえないのですが、もっと一般的な「海外に長期滞在するとは」みたいな形で留学する際のマインドセットを教え込まれます。
e.単位認定制度
多くのアメリカの大学生が留学する背景に、留学のしやすさがあります。特に留学をしやすくしているのが、留学先の大学から持って帰れる単位に関する仕組みが整っていることです。ウィリアム・アンド・メアリー大学の場合、出発前と大学に帰ってきた後の2回単位認定を申請することのできるタイミングがあります。
留学先で履修したクラスについてクラスの内容や難易度が分かるシラバスや試験などがあれば、それを各学科の学科長に提出しウィリアム・アンド・メアリー大学で該当するクラスとの類似性が認められれば自分の大学で履修したのと同じ扱いを受けることができます。大学が提供していない内容のクラスでも申請をすれば認めてもらえることが多くあります。特に歴史に関しては一定の大学であれば自動的に歴史の授業として認められます。また、専攻の要件で選択科目の中に入っているものに関しても同じ内容をカバーしていると認められれば留学先で履修したという扱いを受けることができ、留学をしないで大学に残った場合とそんなに差異はありません。ただ、留学先で取得した単位については反映されるのは単位だけで、実際に取った成績はGPAなどに含まれません。
事前に単位として認めてもらえれば、履修したものが確実に帰国後反映されるというのがわかっているので、安心して授業を選択することができます。
このような形で留学に向けた準備を大学にいる間に終わらせ、休みの間に寮や食事、航空券など実際に留学先の大学で必要な手続きなどをオンラインで行っていくことになります。
以上、アメリカの大学における海外留学についてご紹介させていただきました。アメリカだけでなく様々な場所で経験を積むことができるのが海外留学です。アメリカの大学に進学予定の方はぜひ検討してみてください。
では以上で6月号とさせていただきたいと思います!
|
この記事の先頭へ戻る
◇ 2016年5月 バージニアの海岸より
◇ 2016年4月 どんな要素で大学を選ぶのか
◇ 2016年3月 多様性を表現する場
◇ 2016年2月 得た知識を処理する力
◇ 2016年1月 学びの道しるべ「専攻」
この記事を折りたたむ
|
◇ 2016年1月 学びの道しるべ「専攻」
新年あけましておめでとうございます!
さて、1か月の冬休みもあっという間に終わり、1月20日から春学期が始まりました。
冬休みの間は色々忙しかった一方で、年末年始ということもあってたくさんおいしいご飯を食べたり、テレビを見たり、19単位の怒涛の秋学期の疲れを取ることができたかなと思います。ちょうど東京を出発するときも天気が悪くて雪が降ったりしていましたが、ウィリアムズバーグに帰ってみるとこっちもこっちで雪が降ったりと、どこにいても同じような天候が待っています。今年は暖冬だということなので、今後2月にかけて少し寒くなりつつも、あまり雪で学校が休校となったりしないことを祈りたいです。
実は先日、正式にウィリアム・アンド・メアリー大学における国際関係学専攻として手続きを行いました!!これで今までのInternational Relations major (maybe...??) みたいな雰囲気の自己紹介から卒業して、胸を張ってI’m International Relations major! といえるようになりました!
ということで2年生も後半に入り、いよいよ今までの入門クラスを土台として徐々に専門的な分野へと学びが積み重ねられています。また、今回自分が手続きを行ったように周りの2年生がみんな大学での専門となる専攻を決めるのもこの時期です。ということで、今月号では改めてアメリカの大学の専攻の仕組みから話を始めたいと思います。
○アメリカの大学の専攻の仕組み
アメリカの大学の制度について説明するときに、よく「入学時には学部学科を決めなくてよくて、2年生の終わりに専攻を決める」という風に表現するのですが、それをもう少し具体的に、正確に話してみたいと思います。
a.「入学時には学部学科を決めなくてよい」
入学したてのころにこの留学レポートでも少し紹介させていただいたのですが、そもそもアメリカの大学には原則学部学科を受験するという概念がありません。エンジニアなどをのぞいた一般的な分野を勉強したい場合は、みんな共通のCollege of Arts and Sciencesやそれに近い名前の学部に入学します。一応、大学側も入試段階である程度新入生の学業面でのバランスを確保したいため、願書に受験段階で希望する専攻を3つほど候補として書く場合が多いです。ただ、その場合でもUndecidedというチョイスがあったりするので、必ずしも願書で選択した専攻を最終的に選ぶことは求められていません。現に、自分の周りの友達も半分以上が1年の秋学期に出会った時と今では違う専攻を考えているといっても過言ではありません。
意外と多くの人にとって大学生活の最初の2年間で専攻したい分野を変えるきっかけとなるのが、他分野との出会いです。高校時代にある程度興味分野が定まっていたとしても、国際関係学やビジネスなど高校時代には全く触れていなかった分野を勉強することで、新たな興味が広がるきっかけとなる場合が多いです。特に、ウィリアム・アンド・メアリー大学では留学レポート2014年10月号でご紹介したGeneral Education Requirement(注:2015年度入学以降はカリキュラムが変わりました)を通して全学生に必ず幅広い分野に触れさせることで、常に気持ちをオープンに大学生の段階で自分を見極めるチャンスを与えています。一般的なアメリカの大学ではリベラルアーツカレッジでも総合大学でもリベラルアーツ教育を大切にしてGERに近い卒業要件を設けているところが多いので、主にまだ専攻が決まっていない最初の2年間でアメリカの学生は大学の要件を満たすべく幅広い科目を取ることになります。
まとめると、入学時から学部学科にしばれられない分、専攻が決まっていない最初の2年の間に、専攻以外の卒業要件として様々な分野を知る機会がある、ということになります。
b.「2年生の終わりに専攻を決める」
冬休みに日本で周りの友達から、3年からゼミに入るから今はそれに向けて準備をしているという話をよく聴きました。いわゆる最初の2年が教養課程で後半が専門課程という風になっているところも多いと思います。2年生の終わりに専攻を決めるというと、そういった意味でその感覚に近いかと思います。しかし、実は「2年生の終わり」というのは厳密に言うとちょっと違って、自分の大学の場合は39単位取得時から専攻を宣言すること(Declaration of major)が出来て、54単位取得時までには必ず専攻を宣言しなければいけないという風になっています。卒業するのに120単位必要で、正規生として毎学期12単位以上取らなければいけない形になっているので、遅くともみんな2年生を終えるまでには宣言することになるわけです。自分の場合、1年生を終えた段階で35単位持っていたのですが、2年生の秋学期を終えた段階では54単位になってしまったので、春学期が始まって早急に宣言する必要がありました。このように、アメリカの大学における専攻というのは、所属する場所というよりも4年間をかけてどんな分野に特化して勉強していきたいのか道筋を立てさせてくれるものといった感覚が強いので、極端な例を言えば、自分で専攻をデザインして大学側に正式に認めてもらうことも出来ます。
○国際関係学専攻
そもそも、「専攻(Major)」というのがどういうものなのか、大学の国際関係学専攻を例にご紹介したいと思います。
まず、ウィリアム・アンド・メアリー大学にはMajor/ Minor(副専攻)合わせると50ほどの分野があります。それぞれが専攻もしくは副専攻として学生は自由に選ぶことができます。ちなみに、この大学で人気トップ5の専攻は、政治学、心理学、生物学、英語、金融だそうです。
国際関係学専攻として卒業するには、定められた専攻要件(Major Requirements)と呼ばれるものがあります。卒業までの4年間のうちに決められた科目、もしくは決められた選択肢の中から科目を選ぶことで、最終的に国際関係学専攻を修了したと認められます。大学の中でも専攻が大変だといわれている国際関係学ですが、それだけ要件も他の専攻に比べて多いです。ではここで、とても長いので実際のリストの抜粋を載せたいと思います。あくまでウィリアム・アンド・メアリー大学の国際関係学専攻の要件ですが、どの大学のどの専攻でも同じようなものがあると思うので、あーこういう感じなんだと感覚がお伝えできればうれしいです。
Part A: Core Curriculum (7 courses) 7科目すべて必修
Part A represents the core of the IR major, and includes basic requirements in Government, Economics, and History. All courses must be taken, and no substitutions are allowed.
GOVT 150/204: Introduction to International Politics
GOVT 328: International Political Economy
GOVT 329: International Security
ECON 475: International Trade Theory and Policy
ECON 476: International Finance Open Econ Macro
HIST 192: Global History since 1500
INRL 300: International Relations in Disciplinary Perspective
Part B: Methods (1 course) 一つ選択
Part B includes courses designed to familiarize students with the basic methodological tools of disciplines contributing to the IR major. This course meets the Major Computer Proficiency requirement. Students who intend to write an Honors thesis in IR should select the methods course that provides the necessary tools to complete the thesis. It may be fulfilled with any of the following courses:
BUAD 231: Statistics
GOVT 301: Research Methods
ECON 307: Principles and Methods of Statistics
PSYC 302: Experimental Methods
SOCL 352: Methods of Social Research
など8クラスから選択
Part C: Social and Cultural Contexts (1 course) 一つ選択
Part C emphasizes the role that social and cultural contexts play in international relations, and exposes students to relevant disciplinary approaches. Students may fulfill part C with any of the following courses:
ANTH 330: Caribbean Cultures
ANTH 335: Peoples and Cultures of Africa
GOVT 311: European Political Systems
GOVT 312: Politics of Developing Countries
HIST 325: Race, Culture, and Modernization in South Africa
HIST 328: Modern Japanese History
SOCL 312: Comparative Sociology
SOCL 313: Globalization and International Development
など27クラスから選択
Part D: Capstone (1 course) 卒業論文、リサーチ、インターンシップなどから選択
To fulfill part D, each student must successfully complete an independent research project. This course meets the Major Writing Requirement. This requirement may be met by completing one of the following:
INRL 495-496: Senior Honors in International Relations
INRL 480: Independent Study in International Relations
Three credit directed internship in contributing department (approved IR topic only, and must not be Pass/Fail)
Part E: Electives (2 courses) 2つ選択
IR majors may choose any two courses from the list below, provided that no more than nine of the twelve total courses required for the concentration may come from the economics and/or government department. All the courses in Part C listed above can also count as Part E courses.
ANTH 476: National Formations and Postcolonial Identities
BUAD 417: International Banking and Trade Financing
ECON 342: Global Economic History
ECON 483: Development Economics
GOVT 322: Global Environmental Governance
GOVT 324: U. S. Foreign Policy
GOVT 326: International Law
HIST 243: Europe Since 1945
HIST 319: The Nuclear World
HIST 435: America and Vietnam
RELG 323: Warfare and Ethics
SOCL 408: Migration in Global Context
SOCL 427: Globalization and the Environment
など47クラスから選択
Second Language Requirement 第二言語か第三言語まで学ぶ必要があります
The IR major requires intermediate proficiency in a modern language other than the native language of the student. The student can meet this requirement in two ways:?
Continuation of the modern foreign language used by the student to meet the College requirement to three courses above the level of 202. The courses must be taught in the target language.?
Starting a second modern language in addition to the modern language used to meet the College requirement. The student must achieve the 202 level in both of the languages, and one course over the 202 level in one of the languages. The courses must be taught in the target language.
という様に(長い引用恐縮です)、専攻要件といってもPart Aの7つの必修科目以外に膨大な選択肢があるので、自分の興味のあるエリアに特化して自由に組み合わせることもできます。
これらの科目は、国際関係学専攻を宣言してからでないと取れない訳でもなく、1年生の入学当初からどんどん入門クラスを取っていく必要があります。そのため、ある程度は他の専攻の場合も同様で最初の段階から専攻したいものを意識しつつ入門クラスを取る場合が多いです。
つまり、4年というスパンの中で決められた要件に従って計画的に時間割を自分で設計し、こなしていくのがMajor「専攻」といえると思います。
○Declaration of Majorの仕組み
その中で先ほど触れたように所得単位が39単位から54単位である間に専攻を宣言することによって、学校側がそれぞれの学生が何を目指して授業を取っていっているのかを把握するための手続きとしてDeclaration of Majorが存在するという様に換言することも出来ると思います。
そして、ここからは実際今週自分が行った手続きをご紹介したいと思います。
まずもうすでに54単位取得してしまっている自分は早急に宣言をしなければいけなかったので、冬休み中に学校のホームページを読んで研究していました。また、専攻を宣言する際に、Major advisorと呼ばれるアドバイザーを国際関係学関連の授業を教えている教授に頼まなければいけないので、誰に頼めばいいのかという部分が一番この手続きで難しい部分です。
通常、アドバイザーになってもらう教授は今まで国際関係学関連の授業で教わった教授、自分が一番話しやすい教授、自分の興味分野に近い研究を行っている教授などを意識して選んでいきます。自分は今までにあまり国際関係学関連の授業はまだとっていないので、国際関係学を専攻している3年生の友達にアドバイザーの候補を見せて相談に乗ってもらいました。それを踏まえ、さらに国際関係学のDepartment Headの教授のオフィスアワーを訪れてさらに相談に乗ってもらい、最終的にアドバイザーになってもらう教授を決めました。その後アドバイザーになってほしい教授とアポを取り、実際にアドバイザーになってもらうために交渉をします。この際、Declaration of Major Formと呼ばれる宣言の申請用紙を持っていって、卒業までにどのクラスをどのタイミングで履修して専攻要件をクリアするかという計画表をもとに今後の学習計画を組み立てて、申請用紙にサインをもらいます。その紙を今度は国際関係学のDepartment Officeへ提出し大学側が事務手続きを済ませると、晴れて大学の学生情報のところにInternational Relations Majorと表記されるわけです。
自分は、やはり将来的には国際関係学と副専攻に考えている海洋学を何かしらの形でつなげたいと思っているので、国際関係学の中で環境や政治経済が専門の教授にお願いすることにしました。もともと彼が教えている、Global Environmental Governanceという授業も面白そうなので来年取ってみる予定だったこともあり、ぴったりでした。また、教授も実際あってみたところ明るく親切な先生だったので、今後ちょくちょく話に行きたいと思います。
いよいよ国際関係学専攻として本格的な大学での学びが始まります!早速今学期の授業もなかなか密度が濃くて大変ですが、いろいろ考えるところもあって面白いです。また、勉強だけではなくて残りの2年半の大学生活を有意義に過ごせるように、ここだからこそできることをたくさん見つけて色々な経験を積んでいけるようにしていきたいと思います。
今学期の授業紹介はいつも通りまた来月行わせていただきます!
では2016年初投稿は、学業面で新たなステップを踏み出すこの時期に改めて「専攻」の仕組みをご紹介させていただきました!今年も引き続き留学レポートをどうぞよろしくお願い致します!
|









|
この記事の先頭へ戻る
◇ 2015年12月 国際関係学と創造力
◇ 2015年11月 2年生ながら「就活」について
◇ 2015年10月大学での自分の役割を考える
◇ 2015年9月 2年目の秋
◇ 2015年8月 HLABを終えて
◇ 2015年7月 リベラルアーツと自分
◇ 2015年6月 夏休み突入
◇ 2015年5月 Freshman Yearを終えて
◇ 2015年4月 外から見た日本
◇ 2015年3月 春学期の様子
この記事を折りたたむ
|
◇ 2015年3月 春学期の様子
3月号です!
寒さも和らぎ、少しずつ春の足音が聞こえてきています。
最高気温も20度まで上がる日が徐々に増えてきました。
が!それと同時に、やっぱり避けては通れない春の風物詩が僕を苦しめようとしています…
というわけで、今回は春学期前半の出来事などを主に紹介していきたいと思います!
○花粉
これに関してはやはり日本だけではないようです。
周りの先輩からウィリアムズバーグにも花粉があるとは聞いていたのですが、僕はもともとスギ花粉だけで、どうやら杉は日本原産なので、こっちでは大丈夫かと思っていました。しかし、暖かい日には朝起きた時から鼻がむずむずして、たまに目もかゆくなります。噂によると、ウィリアムズバーグはアメリカの建国発祥の地のようなものなので、全米各地から様々な木が贈られてきていて、そういった木がいろんな花粉を一斉にばら撒くため、特に花粉がひどいそうです。アメリカ人も今まで花粉症じゃなくてもここにきて花粉症になることが多いと聞きました。しかも、こっちではよほど深刻な感染症でもない限り(そもそもそんな人は外を歩かないと思いますが)マスクをしないので、誤解されないためにもマスクは避けたいです。正直、アメリカに来れば毎年の花粉症から逃れられるんじゃないのかとひそかに期待していた部分もあるので、ちょっと残念ですが、日本から持ってきていた薬でなんとか耐えしのいでいきたいと思います。
○Charter Day
話しは戻りまして、2月の上旬の出来事です。
毎年、2月8日には時の英国王、ウィリアム3世とメアリー2世が、英国の植民地であるバージニアに大学を創立する勅を出した日としてCharter Day Ceremonyが行われます。今年は8日が日曜日だったため、式典は6日に行われました。簡単に言うと創立記念日です。
1693年2月8日にウィリアム・アンド・メアリー大学が誕生したということで、今年で322歳になりました!ちなみに1693年というのは、日本で言うと元禄6年になります。松尾芭蕉が奥の細道の旅を終えて4年後です。アメリカで唯一Charter(勅許)によって創立した大学ということで、学生みんなが誇りに思っています。以下が実際の勅書の抜粋です。
William and Mary, by the grace of God, of England, Scotland, France, and Ireland, King and Queen, Defenders of the Faith, and so forth. To all to whom these our present letters shall come, greeting.
Forasmuch as our well-beloved and trusty subjects, constituting the General Assembly of our Colony of Virginia, have had it in their minds, and have proposed to themselves, .... and establish a certain place of universal study, or perpetual College of Divinity, Philosophy, Languages, and other good Arts and Sciences, .....
..... That when the said college shall be erected, made, founded, and established, it shall be called and denominated forever, The College of William and Mary in Virginia; ....
In testimony whereof, we have caused these our letters to be made patent. Witness ourselves, at Westminster, the eighth day of February, in the fourth year of our reign.
実際の式典では大学の学長を始め、学部長などが中世ヨーロッパのようなガウンを着て壇上に上がりました。そして、現在の総長(Chancellor)であり、ロバート・ゲーツ元国防長官のスピーチもありました。1965年に大学を卒業し、ブッシュ政権・オバマ政権の時に国防長官を務めた方です。こうして、伝統ある大学で遠い昔の卒業生たちに思いを馳せながら大学の誕生日をお祝いできるのはとても素晴らしいことだと思います。また、伝統を大切にしながらも、それに固執して硬くならず、楽しく面白く大学の伝統を楽しむ、そんな校風がとてもウィリアム・アンド・メアリーのいいところです。
○WMIDMUN
2月の下旬には11月号でご紹介した国際関係クラブの活動の一環である、WMIDMUN、William and Mary Middle School Model United Nations(ウミドムン)の運営にスタッフとして携わりました。今回はクラブが主催する中学生模擬国連大会です。11月にスタッフとして携わった、高校生大会WMHSMUNなどなんでも略しちゃうので、話していてどっちがどっちだかわからなくなってしまうことがあります…
今回担当する会議は、国連アジア太平洋経済社会委員会です。主に会議監督、議長のサポートとして、日本の模擬国連で書記官に相当するポジションを行いました。アジア太平洋の、食糧問題、自然災害への対応、人口減少などについて議論をするため、日本の福島原発なども話題に上りました。基本的に、Novice Committeeといって、模擬国連の初心者が多く集まる会議なので、ゆっくり丁寧にルール
を説明しながら会議が進められました。それでも、模擬国連は慣れていなくてもスピーチなどを通して、相手に効果的に主張を伝えることをしっかり心得ている参加者が本当に多かったです。また、交渉の場面でも周りをまとめて引っ張っていく生徒、色々なところに行って交渉をする生徒など、それぞれが目的をもって活躍していたところがとても印象的でした。特にこの会議ではアジア太平洋の大きな国から小さな島国までさまざまな国の「大使」として行動しなければいけないので、中学生という早い段階から、自分が今まで聞いたこともなかったような国の人の立場になって国際問題を真剣に議論するというのはとても貴重な経験だと感じました。
○春休み
3月の第二週目は前後の週末も含めまるまる9日間の春休みでした!
秋学期は4日間の秋休みと、5日間の感謝祭休みとでわかれていたのですが、今回はガツンと長期休暇を取ることができました。そこで、僕は長らく楽しみにしていたワシントンDCへ行ってきました。秋休みにも2日間だけDCに滞在していたのですが、限られた時間の中で目玉中の目玉だけを見て終わってしまったので、今回はガッツリDCを堪能しました。
アメリカの首都であるワシントンDCは大学から車で3時間ほどのところにあります。この近さがウィリアム・アンド・メアリーの良さだったりもします。国際関係に限らず政治系に強い大学なので、DCにはDC Officeと呼ばれる小さなキャンパス(事務所)があって、1セメスターや長期休暇時にDCで授業を取ることも出来ます。また、Charter Dayにゲーツ元国防長官が総長として毎年出席しているように、卒業生のネットワークもとても強いという風に聞いています。
また、DCにはスミソニアン博物館群といってアメリカの中心となる大規模な博物館が数多く集まっています。しかもほぼすべてが無料なので、とてもお得に時間を過ごすことも出来ます。というわけで、今回はひたすら博物館に通い詰め、博物館だけでも11か所、その他にも色々なアメリカの政治の中心地をめぐることができました。中でもとても印象に残っているいくつかをご紹介したいと思います。
a. ニュージアム
ニュースのミュージアムということで、ニュージアムといわれています。博物館正面には権利章典(The Bill of Rights)とよばれる国民の権利を規定したアメリカ合衆国憲法修正第1条から10条までの中の言論、宗教、集会の自由などを保証する第1条が大きく書かれていています。アメリカ政治学の授業で国民の権利について習ったばかりだったので、とても新鮮でした!
実際の展示内容としては、歴史的瞬間を捉えるという意味での「報道」を、歴史を変えた出来事と共に紹介していてとても興味深かったです。実物のベルリンの壁の一部や、歴史的ニュースを報道した新聞の一面などが1600年代の物から現代の物まで展示されています。こうして、実際に歴史上の出来事に触れた本物の新聞記事を前にすると、歴史というものが決して過去の関係ないものなのではなくて、自分に直接つながっているものであり、また実際にまだ頭の中に鮮明に記憶されている4年前の東日本大震災を伝える新聞記事が同じように並べられているのを目にすることで、これも歴史の一つとなって未来につながっていくと感じ、改めて歴史の本質を見た気がしました。
b. 印刷局(Bureau of Engraving and Printing)
簡単に言うと紙幣を印刷しているところです。それだけなんですが、新鮮でいろいろ勉強することができます。印刷しているところを見学できるツアー自体は無料なのですが、3月から8月までは混雑するため、8時配布開始の整理券を手に入れなければいけません。工場では、5ドル、20ドル、100ドル紙幣がどんどん印刷されているところを見ることができたのでとても面白かったです。最初は紙幣16枚で1つの大きな紙に印刷されていて、それが後で一つ一つに裁断されていくのですが、印刷の途中の部分でまだ色が完全についていないものや、中央の肖像だけ入っていないものなど、色々なステップの紙幣は普段見ることができないので、こういう過程を見ることで、今まで何気なく使っていたお金に対して新たな視点を持つことができました。
ちなみに、ツアーガイドの人に聞いてみたところ、100ドル札は一枚作るときに11セントかかり、1セント玉は1セント以上かかるそうです。そのことについてマクロ経済の教授と話したところ、どうやら、100ドルとして世に出回る紙幣を印刷することで、政府は99.89ドルの収入があり、それは国の収入になっているそうです。マクロ経済で習っている概念と日常生活がつながった一瞬でもありました。
c. 日本について考える
博物館を訪れる中で日本に関する紹介があると、どうしても敏感に反応します。特に、国立航空宇宙博物館に展示されている零戦をはじめとした日本の戦闘機や、美術館で紹介されている日本美術などは特に興味がわきます。来月号で詳しく話そうと思っているのですが、ベタな話ではありますが、やはり異国の地にいると自分の母国についてどう考えられているのか、どのように紹介されているのかがとても気になるし、意識させられます。特に、今まで太平洋戦争で日本軍が使用した戦闘機などはみる機会がなかったので、様々なことを考えさせられました。アメリカの知識と財産が詰まった博物館群で日本について考えることができたのは、いい経験だったと思います。
○Academic Advising
春休みが終わると、いよいよ今学期も折り返し地点です。中間試験やらライティング課題やらに追われているとあっという間に期末試験がやってきて、早くもアメリカでの大学生活1年目が終わろうとしています。1月号の今学期の目標でも書きましたが、どうしても目先の課題などで一杯いっぱいになってしまうとあっという間に日々が過ぎてしまいます。一日一日を振り返って大切に過ごしていけるように心がけたいです。
さて、そういうことで早くも秋学期の授業登録が迫ってきています。1年生の場合は、必ずAcademic Advisorと呼ばれる教授と授業登録の前にミーティングを行い、一般教養課程(GERと呼ばれています)などの要件を順調に満たして行けているかなどを話し合います。ウィリアム・アンド・メアリー大学では全生徒にAcademic Advisorが割り当てられます。専攻を宣言するのは、たいてい2年生の春学期なので、それまではPre-Major Advisorが付き、専攻を宣言する際に自分で専攻を希望する学科の教授にお願いしてMajor Advisorに付いてもらいます。今は、まだ専攻を宣言していない段階なので、Pre-Major Advisorに色々サポートをしてもらっています。こうして、8月のオリエンテーション時、10月の春学期履修登録時、3月の秋学期履修登録時の計3回は最低でもアドバイザーの教授と会わなければいけないことになっています。
Pre-Major Advisorの場合は、自分が考えている専攻の分野の教授ではなく、ランダムに割り当てられていて(入学前に専攻希望調査のようなものはありますが、たいてい2年を終えるまでに専攻したい科目が変わることが大いにあり得るので)、僕のアドバイザーは美術史学科の教授です。メールでアポイントメントを取り、ミーティングへ向かいました。約束の時間に教授と会い、当日は暖かかったということで外を散歩しながら2人で話し合いました。ちゃんと名前も覚えていてくれて、最近どう?とか、何か困っていることある?などとても親切にいろいろ聞いてくれます。こちらとしても、何か大学でどうすればいいかわからない時に一番身近な存在がPre-Major Advisorなので、漠然とした疑問や不安なども色々話すことができます。
正直、自分が希望する専攻についてよく知っている教授を割り当てる仕組みではないので、細かい履修要件の話などをすることは出来ないのが不便な点ではありますが、アドバイザーがよく知る国際関係学だったら国際関係学の教授に連絡を取ってくれて、詳しい専攻の話を聞くことだってできます。また、全然自分が専攻に考えていなかった学科の教授といろいろ話をすることで、一年の時から限られた分野の教授とだけ交流があるよりも、視野が広がることは確かだと思います。何より、僕のアドバイザーはとても親身になってくれるので、ありがたいです。
というわけで、春学期前半の様子をお届けしました!
日本では桜も咲き始め、新たなスタートの時期でしょうか?僕も気持ちを新たにして残り1か月半、有意義に過ごしていきたいと思います!
ではまた来月!
|
























|
この記事の先頭へ戻る
◇ 2015年2月 新たなスタート
◇ 2015年1月 学期を終えて見つかった自分
◇ 2014年12月 考え方を学ぶ
◇ 2014年11月 いつでもどこでも学びがある生活
◇ 2014年10月 リベラルアーツの精神
◇ 2014年8月・9月 伝統を重んじる精神と積極的態度の重要性
|